夢幻のフムスノア MUGEN NO HUMUSNOVA
小説氷河期の終わり、人は自然と戦い新天地を目指す。
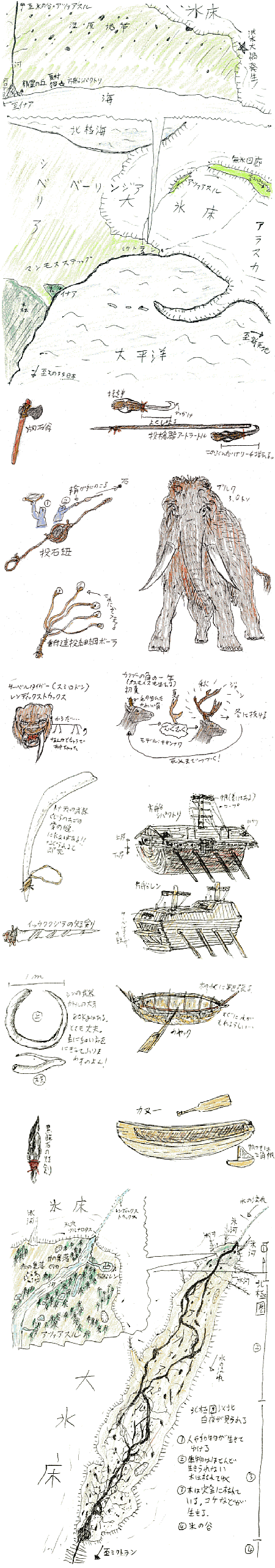
 第一章 虹脚狩人 VENATOR
第一章 虹脚狩人 VENATOR
白い熊は、飢えていた。
とにかく獲物のすくない春だった。
雪の穴から出てしばらくたつが、これまで食べたのはアザラシがわずか二頭。他には、餓死した我が子だ。
今、足下は浅い河だ。産卵の赤いサケが遡上してくる。彼女は、茶毛の仲間がする漁を思いだした。
やってみるか。
サケを追い回してみる。だが、子孫を残そうと懸命なサケはすばやい。やったこともないサケ漁は成功しなかった。
白い熊は徒労を感じ、中州で休んだ。
なんという体たらくか。
私は、子のように飢え死ぬのだろうか。
と、そのとき、熊の瞳が、遠くからやってくる獣の一群を捕えた。
鈍い。獣たちはなにか重いものを引いており、本来の速さを発揮できずにいる。
――あれなら、今の体力でも。
おりしも彼女の周囲では、霧がたちこめはじめていた。
霧が、餓獣の身を隠した。
* *
極北の大地に、夏がきていた。
みじかい夏は、命が輝ける唯一の季節。それゆえ、あらゆる営みがせわしい。
海は氷の覆いから開放され、藻のかきまぜる海が蘇った。つねに風吹く大地は、いっせいに地衣やコケで緑に染めあがった。緑の舞台は整った。
だが、役者である動物が、ほとんどいない。子育てのアザラシも、潮吹きのクジラも、巣営の渡り鳥も、地味な夏毛に変身した四つ脚たちも……
景色だけが、いつも通りだった。
それは内陸も同じだ。永久凍土層に阻まれ地に潜れぬ雪解け水が、沼や湿地となって溜まっている。そんな大地の中心を、北から南に走る河があった。
蛇のようにくねくねと曲がる河は、南の海をめざしていた。やがて東西に伸びる海岸線の手前で枝別れし、扇状に開いた広大な河口デルタを形成していた。水量は少なく、ほとんどの筋で多くの中州が生まれている。
そして河口の東端の川筋では、濃い霧の雲が生まれていた。
* *
霧が流れる中州を、二台のカリブー(トナカイ)ゾリが走っていた。
それぞれの軽ソリを一〇頭のカリブーが引き、二人ずつが乗り込んでいる。人は全員が、カリブーの革服を着ている。フードと袖襟、裾以外は、なめされて毛がなく、白灰色ですべすべだ。
「カマク叔父さん――」
ふいに、後方のソリから少女の声がした。
「――止まって!」
声に反応して、前のソリが止まった。
そこに後方のソリが横付けする。
砂礫を弾く音が消え、水音だけが残った。
「なんだ、ミティ」
先に止まったソリで、操り綱を握る壮年の男が、少女に話しかけた。
ミティは風でなびく黒髪に手を添えた。
「カマク叔父さん、今は、渡るのよそうよ」
「なぜだ? この筋を渡れば、二日がかりの大河渡りが終わるのに」
ミティは、おちつきのない視線でしきりにあたりを見回した。
「感じるんだ」
「ふうむ……この水量だ、いまさら雪解けの洪水は考えられぬし……また地の揺れじゃないだろうな」
「……わからない」
カマクは、おおきな腹をゆすった。
「きっとまた、地の揺れにちがいない」
「でも、気になるの。戻ろう」
「ミティ、渡れば、すぐに《夏村》に着く。ひさしぶりに酒が飲めるのだぞ」
ミティは頬をふくらませた。
「私、あんな臭くて苦いのいらない」
するとミティの隣の、のっぽ男が、
「ミティさんはまだ若いですから」
それに続くように、
「精霊の水は、大人だけが美味しいと感じる――ね、親方」
と、カマクの隣にいる、腕っ節の強そうな男が言った。
親方カマクは幸せそうな顔をしてうなずき、カリブーの操り綱を打った。カマクの木ソリは、ゆっくりと動きだした。
「というわけで、出発だ」
カマクのソリは、目の前にただよう霧塊に入って見えなくなった。
「酒サケさけ……この酒の悪霊!」
ミティは、霧塊に向けて舌をだした。
これに、ミティのとなりののっぽが軽く困った顔をした。
「私も、ミティさんが感じたのは地の揺れだと思います」
「だけど、アシ、なんか違うんだ、これは」
「気持ちが高ぶっているからでしょう。旅の終わりが近いですから」
「そうかなあ」
「ケツァさんに会えますからね」
「ケツァに!」
とたん、ミティは頬を両手で押さえた。
「うん……はは、そうだったよね」
そして元気な声で、
「アシ、出発して。悪霊に遅れちゃう」
と拳を振り回す。
アシは微笑みながら、綱を打った。
* *
過去の氷河が運んだ礫が積み上がってできた、小高い丘があった。丘の南側は日が当たり、ぽつぽつと新緑に覆われている。
その緑を、一人の少年が踏み締めた。少年は、アザラシ革を縫い合わせた、簡素な毛皮服を着ている。
やがて少年は、丘の頂に立った。
頂には、一本のトーテムポールが立っていた。いろんな動物の浮き彫りが、色鮮やかに塗られている。そしてトーテムの頂点では、翼を広げた黒いカラスの彫りが、ひときわ大きくはばたいている。
カラスは、南の海を見ていた。
少年は、そのカラスを見上げた。
「オオワタリガラスの精よ……あなたは、今も父さんを見守っていますか?」
少年の、意思の強い黒い瞳に、オオワタリガラスが写った。しかし瞳は、カラスなど見てはいなかった――
* *
「――さん、父さん。鳥だよ」
「ほう。今年も、鳥の渡る日が来たか」
「すごいね、鳥って。空を飛べるもん」
「ところでケツァ、あの鳥たちはどこから来ていると思う?」
「え……海のむこうかな。ふしぎだなあ」
「いい子だ……いいか、あの海の彼方にはな、氷原を越えた先にはな、見知らぬ大地が、だれも踏みしるしたことのない、前人未踏の新天地が広がっているんだぞ」
「……だれも行ったことがないの?」
「そうだ。だが、俺が行く」
「えっ……父さんが行くの?」
「ああ。今日、決まった」
「危ないよ。知らない場所なのに」
「わかっている」
「ならなぜ行くの? テスカ父さん」
「……そりゃあ、狩場が増えるからさ。《権利》をめぐるちんけな争いもなくなる」
「すごい、それって、すごいよ。僕も行く」
「駄目だ。おまえが挑戦するには、あと一〇年は待たないとな――」
「一緒に行けないの?」
「ああ。ケツァはここに残るんだ」
「嫌だよ。テスカ父さんが行くと、ぼくひとりぼっちになる。母さんの精霊も寂しがる」
「……だいじょうぶだ。俺はかならず帰ってくる。革紐を足に結んだ鳥が渡ってきたら、俺がもうすぐ帰ってくる印だ……」
「ほんとう?」
「ああケツァ。約束しよう」
「母さんの精霊にも約束してよ」
「コヨルにか……約束しよう」
「コヨル母さん、見ているかな」
「ああ、見ているさ」
「ねえ、新天地って、どんなところなの?」
「そうだな……シャーマンのキアが言うには、新天地は虹の土地で、虹の精霊ケツァールが治める土地だそうだ」
「ケツァール……僕の名に近いね」
「そりゃそうさ、新天地の加護があるよう願って付けた名だからな」
「僕って、虹なんだ」
「ああ、ケツァは虹そのものだ。とにかく俺は、新天地で虹の精霊ケツァールを探す」
「きっと奇麗だから、すぐに見つかるよ」
「ああ。そして精霊王ケツァールと、永住の契約を結ぶ。応援してくれ」
「うん、こちらでいちばん偉いオオワタリガラスさんの精に祈るよ」
「頼んだぞ。よし、これをやろう。お守りだ。気を込めてある」
「これって象牙……ありがとう! テスカ父さん、大事にす――」
* *
……少年は追憶から戻ってきた。
オオワタリガラスの彫刻が風にきしむ。
「あれから、一〇年たちました」
ケツァは下を向き、左拳を開いた。
そこには、象牙から削りだした首飾りがあった。表面に色褪せた絵が描いてある。海に漕ぎ出る小舟。舟を操る男は、海上を飛ぶ鳥を見上げている。ていねいな仕事だ。
「もらったときは白かったのに……」
胡桃色に変色した首飾りをなでてみる。
握っていたので、生暖かい。
そしてケツァは、視線をトーテムのカラスが見つめる方角にずらす。
「とうとう革紐の鳥は渡ってこなかった」
灰色の海は強い風に波立っていた。夏でも見上げる高度に至らない極北の太陽は、白く寂しい光を海に投げかけていた。
「俺は……俺は、もう追いかけてもかまいませんよね――」
流れる雲の合間を、ムナグロの群れが飛んでいた。また一つの群れが、新天地から飛来してきたのだ。
「――テスカ父さん」
ケツァは、首飾りを握りしめた。
* *
地震が起きた。
河の水面に複雑な波紋が立つ。カリブーたちが悲鳴をあげ、足をすくませた。
ソリは次の中州を目前にして、河中で立ち往生してしまった。運悪く霧が濃い場所だったので、臆病なカリブーは二重におびえ、耳をしきりに揺らせている。
「しずまれしずまれ」
「はいどうどう」
カマクと、弟子の力持ちにのっぽは、ソリから降り、慣れた手つきでカリブーをなだめている。
ミティも叔父らにつづこうとソリから降りた。深さはくるぶしまでしかない。
おおきな水溜まりみたいだ。
そう思ったとたん、ミティは揺れと水に足をとられた。
「あ」
水しぶきが散る。
ミティはしりもちをついた。下半身がびしょぬれだ。
「ひやっ」
冷たさに、おもわず体が硬直した。
「ゆ、油断しただけなんだから」
ミティはひとりごとを言った。と、そこに、霧の中から一頭のカリブーがあらわれた。めずらしい黒毛だ。
「キキンナク」
キキンナクは、地震に動じていなかった。
黒のキキンナクはミティに近づくと、鼻をミティと合せた。目が合うと、キキンナクはミティの鼻をなめた。
「心配してくれるんだ、キキンナク」
ミティは、キキンナクの首元を見た。
「自分で綱を噛み切ったんだね」
ミティはキキンナクの生え変わりはじめたばかりの袋角をさすった。秋には立派な火炎状の角になるだろうが、今はまだ頼りない。
「ありがとう。私はもういいから、奥さんの、ヤチナウトのそばにいなよ」
人の言葉がわかるのか、キキンナクはミティの元からゆっくりと去った。
キキンナクが霧に消えると、ミティは靴紐をほどき、革靴を脱いで水を捨てた。
――えっ
「なにっ!」
ミティは急に、手足に悪寒を感じた。それらは体の中心めがけて神経を伝わり、脊髄に達した。通常でない感覚は、背の神経束を駆けのぼる。そして情報が脳に飛びこみ、ミティは理解した。
ミティは、霧に叫んだ。
「危険が迫る! みんな、すぐに逃げて!」
一呼吸の間を置き、カマクの声がした。
「ミティ、危険はこの地の揺れじゃなかったのか?」
揺れはおさまりつつあった。
「やはり違ったの! もうすぐ来る!」
ミティは大声で警告を発すると、靴を履き、カリブーたちのところに急ぎ向かった。
* *
風に乗って、声が聞こえた。
地震をやりすごしてから、丘を下りはじめていたケツァは、反射的に身構え、耳をすませた。風は強く、うるさい。さいしょは聞き違いかと思ったが、
……ァァ……
まちがいない。
ケツァは方角を確かめた。西の河の中州だ。なんと、濃霧がたちこめている。しかしケツァは、躊躇も見せずに駆けだした。
丘の日陰側を跳ね下った。
そして口笛を吹いた。
すると間近で、重低音がこたえた。
日の洗礼から隠れ、風に耐え吹き残っている腐り雪の中から、巨大な影が出現した。
ケツァは止まった。
「ブルク!」
影の口元から、草が落ちた。
「すまんが、食事はおしまいだ」
影は不満げにのっそりと動きだした。
* *
飢えた熊は、雌のカリブーに噛みついていた。あわれなカリブーは、すでに息も絶え絶えだ。だが熊は、獲物に止めをすることができない。怖れを知らぬ黒い雄カリブーが、しつこく挑発しているからだ。
白い熊は口に獲物をくわえたまま、黒いカリブーを威嚇する。
「……キ、キキンナク、やめて!」
ミティは恐怖に震えながらも叫ぶが、キキンナクは主人の言葉を受け入れない。なにしろ白い熊がくわえているのは、つがいの半身、妻のヤチナウトなのだ。
ヤチナウトは、背中から噛みつかれている。後ろの半身はすでに動かず、首と前脚だけをさまよわせている。血が脈々と水に落ち、白い熊の周辺は赤く染まっていた。
もはや、助からない。
「やめてよう、逃げて……キキンナク」
ミティの顔はくしゃくしゃだ。
ミティの前には、姪を守ろうとするカマクが槍を構えている。カマクの二人の弟子も、武器を持って白い熊を囲んでいた。無事なカリブーたちは、ソリに繋がれたまま、びくびくと身を寄せ合っている。
やがて緊張に耐えられなくなった白い熊は、ヤチナウトを放って、キキンナクを追いだした。
キキンナクはすばやく逃げる。
そのすきに、ミティはヤチナウトに近づいた。ミティは、水に横たわるヤチナウトを抱いた。ミティの服が、血を吸って染まる。死に瀕したヤチナウトは、弱々しく鳴いた。
「危険がわかっていたのに、ごめんね……」
ミティの涙が、ヤチナウトの顔に落ちる。
ヤチナウトは口から血の泡を吹くと、ゆっくりと目を閉じ、痙攣して動かなくなった。
ミティは、ヤチナウトの遺骸を抱き上げ、背後のカマクに、
「叔父さん、この子、特別なキキンナクの妻だから、食べないでね」
「……わかった」
二人は、感慨に似た想いにひたっていた。
だが、ミティは急に眉を逆立てた。
「また来た、危険だよ!」
そして後ろを振り返った。
なんと、白い熊がキキンナクを無視して二人に襲いかかって来ていた。
しかし、ミティとカマクは、足が竦んで動けない。ミティの視界に、赤い口が迫る。
と、そこに風を切る音がした。
続いて、にぶく刺さる音だ。
熊の動きが止まった。
「今だ。親方、お嬢、逃げろ!」
力持ちの弟子が矢を放ったのだ。矢は白い熊の腰に刺さっていた。
「ありがとう、ヤハラン!」
カマクは礼を言うと、姪とともに白い熊から離れた。
熊はしかし、いっとき動きが鈍っただけで、すぐに追撃を開始した。
「獲物を奪われたと勘違いを――ミティさん、ヤチナウトを捨てるのです」
アシが遠巻きに言ったが、
「いや! キキンナクが哀しむ!」
ミティは、頑として譲らない。
ヤハランはさらに矢を放つが、白い熊はいっこうに気にとめなかった。キキンナクが注意を逸らそうとしても通じない。
「……うわっ!」
いきなり、ミティが小石で転んだ。
ヤチナウトの亡骸は宙を舞い、近くに落ちた。カマクは痛がるミティを心配しつつ、後方からの脅威に槍を構える。むろん、かわいい姪を守るように背に配して。
白い熊は警戒し、ゆっくりとカマクとの距離を詰める。アシ、ヤハラン、キキンナクも近づく。
また、緊張の状況が生まれた。誰も語らない、叫ばない。すべての元凶である白い熊でさえ。
そのときであった。
静かに、大地が揺れた。
皆は、神経を集中させた。
なにかが、近づいてきていた。
だが、あたりは霧、正体はつかめない。
状況は切迫している。敵か、味方か……
その中で、危険感知能力者であるミティだけは、喜びの表情であった。
「……感じない。これは、味方だよ」
音がした。しだいに、大きくなる。
音と揺れは、激しさを増す。なにか、大きな、巨大なものが走ってきている。
ふいに、霧の一部に、影が生じた。
三本の腕を持つ巨人だ。
皆は、影に注目した。
ミティは思った。
雲男の精霊?
三本の腕を持つ、奇妙な雲男……
だが、そんな精霊はいない――いるとすればそれは――
霧が、破れた。
あらわれたのは、茶色の小山だ。
腕のうち、二本は白い牙。そして、一本は長い鼻。自由に動く長鼻であった。
ミティは、やはりというように、喜びの顔で、
「マンモス!」
と、大声をあげた。
それは毛象、マンモスであった。若い個体で、牙はまだ大人の腕ほどだ。
体は、白い熊よりはるかに大きい。
そしてマンモスの背中、頭に近い部分に、ケツァが乗っていた。
ミティがうれしそうな声で、
「ケツァ!」
「ミティ……それにカマク爺も」
ケツァは驚いたようにミティやカマクらを見た。そして白い獣を見て、また驚いた。
「氷の熊! なぜ氷上の王が河原に」
だが今は、考える余裕はない。
白い熊――氷上の王は、マンモスを敵と判断したようだ。
吠える。強敵に対して興奮することで、闘争本能を呼び起こしていた。威嚇のために立ち上がる。大きい。
ケツァは動じず、石刃の槍を用意した。
「ブルク!」
鯨髭の鞭でたたく。ブルクは鼻を丸め、突進した。
マンモスと氷の熊が、交差した。氷の熊の牙は、マンモス・ブルクの牙に阻まれた。弾力ある牙がわずかにしなり、火花が散る。
氷の熊の体勢が崩れた。隙だ。
「せいやっ」
ケツァは、槍を投げ下ろした。手もとには、投槍器アートラートルが残る。投槍器によって確保されたリーチで、常より勢いを増した槍は、氷の熊の肩に深々とつき刺さった。氷の熊は不意な痛みに暴れた。ヤハランの矢はぶ厚い脂肪を突破できなかったが、ケツァの槍は肉まで達したのだ。
「今だ、早く乗って」
カマク、ミティ、アシ、ヤハランは、急いで後脚からマンモスの背にのぼった。
「毛を掴んで――ブルク、出発」
ブルクが歩く。走るときとちがい、音はしない。隣をキキンナクが駆ける。
「カマク爺、氷の熊は?」
「槍を折り抜きおった。また来たぞ」
ミティが、こわばった顔をして、
「ケツァ、ヤチナウトの仇をとって。ブルクで踏めば簡単でしょ?」
だが、ケツァは首を横にふった。
「ミクトランのタブーだ。氷上の王とは氷雪の上で対決しなければならない。土や水の上で殺せば、悪霊になって祟る」
「なら、どうやって退けるの?」
「それが問題だよな……」
ケツァはすこし考えた。
「何か奴を引きつけるものはないかな」
するとアシが、指を立てた。
「あの氷の熊はかなり飢えているようで、獲物に固執しています」
「獲物?」
「カリブーのヤチナウトです」
「やってみます」
すると、ミティが怒った。
「ケツァ、氷の熊に与えるつもりね」
「……ごめん」
「いやよ、埋葬するんだから!」
ミティはケツァの邪魔をしようとした。
「だめだ」
カマクが、姪を押さえた。
「ミティ、氷の熊の精霊は、ヤチナウトを望んだのだ。ここは、精霊の輪に任せよう。人が埋めるのは、人だけでいい」
「叔父さん……」
ミティは、皆を見回した。誰もが頷いた。
「……後で、キキンナクに謝ってね」
「わかった」
カマクは、姪の頭をなでた。
「よし、ヤチナウトを探そう!」
ケツァはブルクを走らせた。足下は水、砂、水、砂と目まぐるしく入れかわり、水飛沫と砂ぼこりが霧の河口に飛び散った。
「どこ?」
「見えないよ」
周囲を探すが、霧が濃くてヤチナウトの遺骸は見つからない。氷の熊は執拗に追ってくる。
ケツァは、祈った。
――父さん、母さん、力を貸してくれ!
やがて、あまりに激しい水飛沫によるのか、小さな虹が出現した。
ケツァは虹に注目した。
――テスカ父さんは、虹の精霊ケツァールを探しに行った。もしや……
「コヨル母さん、おれの目に宿れ!」
ケツァの叫びが、通じたのか――
虹の脚に、かすかに茶色が重なった……
「虹よ、ケツァールよ、おれに力を!」
ケツァは即座に、マンモス・ブルクを虹脚の方角に向かわせた。
「いるのか?」
「見えないよう」
カマクとミティが不審がるが、ケツァは構わない。確信している。
「アシさん」
「はい、こちらの準備もできてますよ」
指が器用なのっぽのアシが、罠輪結びの縄を用意していた。荷運び用にブルクの腹に巻いてあったものだ。
「投げ縄なら、まかせな」
それを、力持ちのヤハランが受け取り、頭の上で回しはじめた。
そして霧がわずかに晴れた先に、カリブーの死体があらわれた。
「すごいっ!」
ミティが、感嘆の声をあげた。
「なんとも、本当にいたとは」
カマクも感心している。
だが、ヤチナウトとマンモスの距離は、ほとんどない。ヤハランは目を見開いた。
「くっ」
ヤハランは狙いつけざま、縄を投げる。ほとんど真下方向だ。汗が飛んだ。
みんながヤハランの縄元を見た。縄は――縄は、ぴんと張った。
「重いっ、押さえろ!」
ヤハランは体勢を崩しかけた。
アシとカマクがあわてて縄を握った。
氷の熊が、一段とおおきな声を出した。ようやく獲物のことを思い出したようだ。
ブルクは、ヤチナウトを引き回した。
ヤハランは、頃合を見計らって縄を離した。ヤチナウトはたちまち失速し、ある中州で止まった。
ケツァはブルクを止めた。氷の熊はもはや追ってこない。
ケツァはほっと安心したが、
「キキンナク!」
ミティが、悲鳴をあげた。
キキンナクは、熊に向かっていた。
ケツァは、いやな想像を巡らせた。
氷の熊は、すでにヤチナウトを喰らいはじめている。もしキキンナクが氷の熊の神聖な食事をじゃましたら、また逃走劇を演じなければならない。
だが、杞憂であった。
キキンナクは、氷の熊の領分を侵さないていどの距離を保ち、しばらくヤチナウトの様を見つめ、そしてケツァらのところに戻ってきたのである。
「別れを、してきたんだね」
まっさきに迎えたミティが、顔をくしゃくしゃにしてキキンナクを抱いた。
風が生まれた。霧の霞が流れ重なり、氷上の王と贄を隠した。
* *
ケツァとマンモスの案内で、カマク一行は《夏村》に到着した。
集落が見えたところで、先導のケツァが止まった。ブルクから下りて、まじめな顔つきでカマクに近寄った。
カマクにミティ、二人の弟子も、真剣な顔をしている。
「カマク爺、精霊に報告しましょう」
ケツァはカマクに矢を渡した。
カマクは緊張ぎみに矢をかかげ、
「オオワタリガラスよ、我を受け入れよ。我は霧の森イナアのカマク。この地に繁栄をもたらすために来た」
そして矢を地面に刺した。
「盟友の矢をもって、証拠とする」
カマクはケツァに、イナアの矢を渡した。
「我はミクトランのケツァ。カマクを案内する者。イナアの精霊に、カマクとその同胞を預かったことを伝える」
そう宣言して、イナアの矢を空に投げた。
「風よ、言霊をイナアに届けよ」
ケツァは、しばらく耳をすませていた。が、風はなにも言わなかった。
ケツァはほっとして破顔した。
神聖な、精霊への報告が済んだのだ。
「精霊は呪わないそうです。ようこそミクトランへ、正しき者、カマク爺」
「一年ぶりだな。どうだ、方船は」
「元気です。四度目の冬も耐えました」
カマクは安心したようにうなずいた。
「ワシの仕事も、今年かぎりだな」
その言葉に、ミティがぴくりと反応した。
「今年で、さいご……」
「どうしたミティ」
「い、いや、なんでもないよ」
* *
やがて一行は、集落に入った。
そこは南の海に面した漁村であった。
村の入口も、すべての家の入口も南に面している。陽光を得るためだ。
村の人は、笑顔でカマク一行を出迎えた。皆、アザラシやセイウチの革の服を着ている。それはケツァの服と同じであった。
そんな出迎えの輪の中から、カマクに一人の老人が近づいてきた。ジャコウウシ・イッカク・カリブー・ムースの角、氷の熊・雪のオオカミ・イヌの牙を体中に飾り、頭にはオオワタリガラスの羽根飾りをさしている。
カマクは、イナア式の礼をした。
「アトル族長、またやっかいになります」
老人――アトルは、カマクに笑いかけた。
「舟の翁、いつも遠くからすまぬな」
「ここには、職人の喜びを刺激するものがありますからな」
舟職人カマクは、挨拶もそこそこにして、さっそく荷下ろしにかかった。
ソリの干草の下からあらわれたのは、ほどよい太さ、長さに切りそろえられた、針葉樹の木材であった。
多くの人々があつまり、木材をさわった。
「よいよい、よい品だ。床板を櫂に回せる」
「西の河の流木はろくなものがないでな」
「ありがとよ、舟の翁」
カマクはあきれたように、
「おだてても何もないぞ。ワシは自分の仕事をするだけだ。とにかく酒をくれ」
「相変わらずだな」
「めずらしく海が穏やかなところにクジラが出た。漁が終わるまで、まあ待ってろ」
「とにかくようやくシパクトリが完成だ」
人々はいっせいに、海辺の一画を見つめた。そこには、二〇艘ほどの小舟に囲まれて、大きな船が鎮座していた。
四角い、木製の方船だ。
下半分は巨大な針葉樹をそのまま丸木舟のようにくり貫き、上半分は残った木材で小屋状にしている。入口は船の中ほどにあり、その高さまで盛土の傾斜進入路が確保してある。そして目立つのは、帆柱の存在であった。
カマクが、つぶやいた。
「シパクトリ、前の秋以来だ……一日も早く、おまえが海に浮かぶ姿を見てみたい」
「浮かぶさ」
となりに、アトル族長が来る。
「こいつは舟の翁だけでなく、ミクトラン族の夢を吸い込んでいるからな……それに、もともとは新天地から流れてきた巨木だ――」
そしてアトルとカマクは、回想に浸った。
――五年前の初夏。
巨大な地震とともに海流が逆転し、新天地からの流れになった。浜には、新天地からいろんなものが流れ着くようになった。
ある日のことであった。息を飲むサイズの、赤と緑の塊が漂着した。あまりにも大きくて、さいしょは新種のクジラかと勘違いしたほどであった。だが調べていくうちに、それが針葉樹の巨木だと判明した。幹の太さはマンモス二頭分、樹高は六〇人分にもなる。もちろん、誰もがはじめて見る。
シャーマン・キアが叫んだ。
「すばらしい。新天地が……前人未踏地の精霊が、これでおおきな船を作って、やって来い、と言っている!」
そして何かがしめしあわせたかのように、この日を境に、潮の流れは元に戻った。
よって皆はシャーマンの預言を信じた。
よし、船をつくろう。
だが、ろくな木材がないミクトランには、資源節約の極致である革張舟の技術はあっても、木を贅沢に使う舟のノウハウはない。
そこで、以前から交流のあった、西南の霧の森を中心とする、草原と湿原に住むイナア族に、木舟職人を求めたのだ。
一季節後にやってきたカマクは最初、巨木を見て仰天した。
「イナアのはるか南で見られる、アカスギに似てるが……なんとでかいスギだ」
巨スギの年輪は三〇〇〇本もあった。
「樹齢《両手指の三〇〇倍》年かい。これはこれは……腕のふるいがいがあるね」
こうしてカマクは、ミクトラン族が夏に集まってクジラ漁をする期間だけやって来て、方船建造の指揮をとることとなった――
アトルは、感慨深げな顔をした。
「そして、この夏でいよいよ完成だ。新天地に、若者たちを送り出せる」
一方カマクは、納得しかねるようだった。
「……アトル、本当に行くのだな」
「もちろん」
「俺は職人だから仕事をこなすことしか知らぬが、これだけは言わせてくれ。もしかして精霊王オオワタリガラスは、方船シパクトリの完成を望んではいないかもしれぬぞ」
「――どうしたのだ、カマク」
「西の河で、氷の熊に襲われた。流木拾いで居合わせたケツァが助けてくれたが」
「なんだと、なぜ氷上の王が河に……」
「飢えてさ迷っていたようだ。だいいちこの夏のミクトランは獣が少なすぎる。食い物は大丈夫か。宴会なぞ開かんでいいぞ」
「それは心配ない。流氷が溶けきって海が荒れるまでに、アザラシの群れを三つたいらげた。みんな干して貯蔵してある」
アトルは集落の東外れを指さした。
カマクが見ると、そこにはねずみや獣よけの高矢倉が一〇棟ほど組んであり、張り革のように干肉が吊ってある。
「なんともすごい量だな」
「ミクトラン族はたびたび飢餓を乗り越えてきた。獲物がすくないときは、精霊の許しを得て、タブーである群れの狩り尽くしをするまでのこと。これに夏のクジラを加えれば、来年まで十分に持つさ。いいか、宴会はする。精霊たちが心配するだろ」
「ならいいが……他に気になるのは、地の揺れがあまりにも多いことだ。一日に何回、起きているのだ」
「それは俺も気になっているところだ。地の揺れは、冬至ごろから激しくなってきた」
アトルは、カマクに顔を近づけた。
「じつはあまり大きな声では言えぬがカマク……反対者がいるんだよ、カマクと同じ理由でな。だがな、獣が減ったのは、地の揺れが原因だとおれは思っている。地の精が怒ったとして、何ができる。せいぜい、ねずみをけしかけるていどだろう」
カマクはアトルの言葉に何を感じたのか、すこしきつい声で、
「アトル族長は、精霊を侮っているのか」
「……そういうわけではない」
アトルは、ため息をついた。
「いろいろあるんだ。精霊はこれまで邪魔などしなかったではないか――とにかく、方船を一刻も早く完成させることが急務だ」
カマクは、いぶしんだ。
「……他になにかあるのか、アトル族長」
「いや、気にするな、舟の翁」
そしてアトルは、手を叩いた。
「さあ、宴の用意をしようではないか。それに報酬の話もある。今夏もソリいっぱいの象牙でどうだ? とけた土のなかから、つかいきれんほどマンモスの骨が出るでな」
* *
崖状の浜で、ケツァは海を見ていた。
すこし沖に、コククジラが一頭いる。頭を出しては、海面にたたきつけて遊んでいる。おおきな水飛沫が散る。タイムラグを置いて、音が届く。
「ケツァ、ここにいたの」
そこに、ミティがきた。
「カリブーたちはもういいのかい」
「北の岩場に放したよ。地衣を食べてる」
「あそこはいたずらねずみの巣だぞ」
「キキンナクが追い払ったわ」
ケツァは笑った。
「さすがだな。あいつは勇者だ」
「勇者は、ケツァだよ」
「ブルクがいたからさ」
「それでもすごい。ところで、やっとマンモス使いになれたんだ。いつから?」
「狩長に認められたのは春さ」
「まだ新人君なんだね」
ケツァは答えなかった。
だまって、海のほうを見ている。
ミティは、すこし気まずそうにしていたが、いっしゅん目をつむって勇気を奮わせると、ケツァのとなりに立った。
「ねえ、ケツァ……本当に、行くの?」
「それか、聞きたかったことは」
ケツァは、ようしゃなく返してきた。
ミティの額に、一筋の汗が垂れた。
「――とっても危険なんだよ」
「俺は、新天地行きに志願する」
「!」
「ミティはやはり反対か」
「だって……誰も成功したことないのに」
「今回は方船シパクトリだ、いままでの小舟じゃない。新天地冒険は、俺のすべてだ」
断言され、ミティは何も言えなくなった。
ケツァは、つづけた。
「見ろよ、この崖を。浜はみんな崖だ。《砂浜》なんて、見たこともないし、口伝の世界にしか残っていない。それに氷河が年々氷床の奥にひっこんでいる。陸の氷が溶け、海が溢れているんだ。イナアには山がある。だが、ミクトランはすべてが低い。逃げる場所など、どこにもない。だから……」
ケツァは、東の方角を見た。
そこには、地平に青い、青白い壁がそびえていた――それは氷であった。地平線の奥までつづき、さらに彼方まで、すべてが氷。陸地を覆う、あらゆる命を拒絶する大氷床が、ミクトランの大地の、北と、そして東に広がっていた。ミクトランは、北と東を氷床、南を荒海に挟まれた、地の果てにある袋小路の大地……
「……だから氷の彼方にある、南東の新天地に、虹の新天地に、行かなくてはならないんだ。そこには誰も、住んでいないのだから」
ケツァは、やや興奮ぎみに独白を終え、気を落ちつけるように黙りこんだ。
ミティも、何か考えているようであった。
二人はそのまま、海を見つめた。
遊びつかれたのか、コククジラは背中だけ出して潮を吹いていた。クジラの背はフジツボに覆われ、白いしみとなっている。老いた個体だ。
そのクジラに、五艘の小舟カヤックが近寄っていた。だが、モリ師がモリを構えたところで、クジラがいきなり動いた。尾で水面を叩いたのだ。
波立ちでカヤックは揺れ、数名のモリ師が海に落ちる。舟の一艘は転覆までした。
その隙に、クジラは潜ってしまった。
「あーあ、宴会のクジラはお預けだ」
後ろから、若い女の声がした。
ケツァとミティはふりかえった。
気が強そうな少女がいた。背はミティよりわずかに高い。
「トラル」
「ケツァ、漁の連中がもどってくるから、出迎えろだって」
「わかった」
ケツァはミティにすまなそうな視線を送った。そしてミティにだけ聞こえる声で、
「ともだち、だろ。わかってくれ」
と言い置き、集落のほうに走りだした。
一方、ケツァがいなくなって、少女トラルはミティを睨めつけた。
「あんた、よそ者なんだからね」
そして、ケツァの後を追った。
残されたミティは、
「なによう、サーベルタイガー娘!」
と息巻いた後、一転して落ち込んだ。
「ケツァ……わたし、この夏だけなんだよ。いっしょにいられるの」
その直後、また地震が起こった。
ミティは、抵抗もなく前のめりに倒れた。
「ともだ……なん……やだよ――」
顔を、地に伏した。
* *
大地が揺れている。
だが、慣れっこのミクトラン族はなにも感じないかのように、平然としている。
漁師たちが戻ってきた。骨と木の枠にアザラシの革を張っただけの軽いカヤックを数名で抱えあげ、あちこちが崩れている崖状の海岸を駆けあがっている。
それを迎える人々。地震に動じないということ以外は、平穏な人の営みだ。
ケツァとトラルは、漁師の中から友人を見つけた。
「ロック!」
「ケツァ、トラル」
櫂を背に抱えたまま、少年ロックは走ってきた。びしょ濡れだ。
ケツァとトラルは、ロックを見て笑った。
「君だけみごとに濡れたな。狩りだけでなく、漁もやっぱり下手糞だ」
「見てたよ、一方的に遊ばれたわね」
これにロックは悔しがった。ふんばり、
「くそ。あんな年寄り二度と狙わねえぞ!」
と叫んだが、格好悪くバランスを崩した。
「うわっと」
トラルにもたれかかった。
「何するんだよ、このスケベ」
トラルは、ロックをぶった。
しりもちをついたロックは抗議した。
「俺のせいじゃない、地の精霊が悪いんだ」
地震は、まだつづいている。
ケツァが、
「クジラもそうだけど、油断していただろ」
と言って、ロックが立つのに手を貸した。
「……そうかな、俺はいつも通りだぜ」
「そうよ。その間抜けなのが、いつもなの」
「ひどい、トラル」
トラルは笑って、
「そうそうロック、いい知らせよ。イナアの客人をもてなす宴会がはじまるって」
とたんに、ロックの表情が明るくなった。
「えっ、精霊の水が飲めるのか」
ロックは、櫂を投げすて、集落の中心に走っていった。
「元気ねえ」
「氷解の祭以来だからな」
ケツァとトラルは、ロックの後を追った。
地震は、ようやくおさまった。
* *
すっかり落ち込んだミティは、下を見てとぼとぼと歩いていた。そしていつの間にか、カリブーたちを放した北の岩場に来ている。
ミティは、何気なくキキンナクを探そうと顔をあげた。
とたん、ミティは目を見開いた。
誰かがいた。
岩場の、すこし高くなっている部分だ。
女だ。白地に黒青黄緑の四原色が複雑に混ざった草織服を着ている。ミクトラン族でも、イナア族でもない。はじめて見る。
ミティは、涙を拭った。
よく見ると、女はカリブーたちに囲まれている。キキンナクも、その中にあった。
「懐いている……」
その声で気づき、女はミティを向いた。
美しかった。
黒い長い髪が風になびき、艶光が流れる。
女は、やさしげに笑いかけた。
そして音もたてずに、流れるように身を沈め――
しずかに消えた。
ミティは呆然としていたが、すぐに我に帰り、高みに駆けあがった。
だが、もはや女はどこにもいない。
ミティは、両頬を押さえた。
「物語みたい……」
そして、近寄ってきたキキンナクの背をさすった。
「まさか、精霊?」
ミティは、しばらく立ち尽くしていた。
* *
闇が訪れる前に、宴がはじまった。
とはいえ、時間的にはすでに夜。極北の夏は、やたら日が長い。
広場にいくつもの火が焚かれ、五〇〇人ほどの老若男女が騒ぐ。肉の焼けるにおいが充満し、春に仕込んだ乳酒が振舞われる。
主賓はカマクやミティたち、イナア族の者であった。弟子であるのっぽのアシと力持ちヤハランは、すっかりできあがっている。
「こらあ、図に乗りおって。貴重な精霊の水を、そんなにがぶがぶと」
師匠カマクが怒るも、アトルは許す。
「いいって。酒は精霊に会える薬だ」
「へへ、わきゃるねへぞくちょおさまわ」
「おうよ、あし、せいれえにくわんぴゃい」
カマクは頭を掻いて、
「すまんな、アトル族長」
「なあに、いい仕事さえしてもらえば」
時がたつにつれ、日は落ちはじめ、世界が黄昏色になった。
宴会は盛りあがる。
子供は遊び、イヌは走る。男は踊り、女は楽器を鳴らし、老人は歌った。単調な、しかしリズミカルな音の流れが、延々とつづく。いつしか若者たちは体に興奮をたぎらせ、酒の引力にまかせて愛を語った。即席のカップルが数組、月明りの闇に消えてゆく。
そんな中、ケツァは昼間の活躍が知られ、武勇伝を幾度も話す羽目になっている。
宴会はつづく。
狩りをイメージするあらあらしい男の踊りに、やがて恋愛に乗りきれない半人前の少年少女がペアで混じった。ただ楽しみたいだけなのか、あるいは最後の口説きを試みているのか。いろいろな想いを胸に、踊り舞う。
輪には、ようやく座談会から開放されたケツァもいる。相手は、トラルだ。二人とも熱気に汗を飛ばす。激しい。
だが、ふいにトラルが踊りをやめた。
「どうしたんだい、トラル」
「ケツァ、気が抜けてる。もういや」
トラルは輪の外で手を叩いて騒いでいたロックを引きよせた。
「ロック。踊れ」
「うひゃあ。なんの精霊のまちがいだ」
「うるさい、踊りたくないのか」
「い、いや。俺はうれしいぞ、トラル」
「ふんっ」
うれし涙のロックをパートナーに、トラルはまた踊りに加わった。
「なんだよ、自分から誘ったくせに」
さすがにむくれたケツァは、また武勇伝を聞きたがる誘いの腕を、酒に酔ったふりをしてかわし、宴会の場から離れた。
そのケツァに、待っていたとばかりに近寄った者がいた。
ミティであった。
* *
日は急速に暮れ、一番星が輝きだした。
いつしかカマクは族長アトルら長老組に混じり、呑気に酒を交わしていた。
「つまりさ、この精霊の水、酒に目がくらんで、ミティの感知を見くびったってわけさ」
「それは舟の翁が悪い!」
「そうじゃそうじゃ。一体何のためにミティちゃんを連れてるんじゃ」
「道中の危険を知るためだろ」
「それを信じないとは、馬鹿な野郎だぜ」
長老たちのお叱りに、カマクは笑った。
「――そういえば、一つ驚いたことがあった。ケツァの目、なんともすごいな。霧に隠れたカリブーを見つけたのだぞ」
「まあ当然だな。ケツァには、死んだ母のコヨルが、精霊として宿っているからな」
「ケツァの眼力には、誰も叶わねえよ」
すると族長アトルが、口を開いた。
「もしや、舟の翁、おまえの姪の力も、精霊が関係しているのかよ」
カマクは首を振って、
「わからん。ただ、ミティの母はナミといって、異邦の精霊使い、シャーマンだった」
「シャーマン……我が一族のキアと同じか」
「そうだ。一八離れた七番目の弟ヴェイは冒険好きでな。一五の時に、海沿いに南へ南へと下ったのだ。そして二年して霧の森イナアに帰ってきたとき、俺たちより肌の濃い、快活な女を連れてきた」
「それがナミか」
「言うには、あたたかなアカスギの大地で貝を食べる民のシャーマンだという。ナミは潮流や獣の群れの位置、天気を読めた」
「そのぐらいの力、俺にもあるぞ」
「それは経験の技だろ。ナミのは能力だ。見なくても感じとれるんだよ。しかもすごい率でな。イナアの狩人も漁師も、それはよろこんだ。六年前、事故でヴェイと一緒にあっさり死んじまったが――」
カマクは真顔になった。
「これ以上は、勘弁してくれ」
「つらい思い出のようだな。もう聞かぬ」
「すまん、アトル族長……」
そしてカマクは、土器杯を揺らした。
「けっ、いまだに尾をひいてやがる……」
さみしげな独言であった。
* *
本格的な夜の闇が訪れ、夜空に天の川が浮きあがった。
ケツァとミティは、北の岩場にいた。
ケツァが、何気なく言った。
「用ってなんだい、ミティ」
ミティは、星を見上げた。
北天には、すこしいびつな形をした北斗七星やカシオペア座が瞬いている。
「うらやましい。星はきれいだから」
「…………」
「ねえ」
「なんだい」
「だれか、好きな子、いる?」
唐突な問いかけに、ケツァの思考回路はふきとんだ。
「なっ、どうしたんだよ、ミティ」
ミティは、ケツァに抱きついた。
「だからあ、聞いたでしょ」
ケツァはようやく異様な臭いに気づいた。
「ミティ、酒を飲んだな」
ミティは、目が座っている。
「答えて。好きな子いるの?」
ケツァはミティの体温を感じ、赤面した。
「なんでいきなり……」
「聞いたら答える! イナアの掟だ」
「ここはミクトラン族の地だ」
「答えないと、霧の悪霊が連れてくぞ」
「顔を寄せるなって……」
「けらけら。まあいいわ、なんかすっきりしたから許したげる――」
ミティはケツァから離れ、近くに座った。
ケツァはミティを警戒している。
と、二人は星空に踊る光に気がついた。
緑。緑の筋光が、星々の間を流れる。
オーロラの、嵐だ。
勇む光が、闇の大地におぼろ光を投げる。
南の夏村でも、皆が顔をあわく染めて空を見上げる。宴はいっとき中断だ。
それにしても――
ミティは思う。
いつのまにはじまっていたんだろう。
ミティは、口を開けて呆然とした。
伸び、たゆむ光の乱舞。流れる川の水のように、もや煙のように。ふくらみ、ちぎれ、つながり、またふくらむ。大きくなり、小さくなる。緑はやがてうすくなり、白から赤色へと移る。そして次にはまた緑に戻る。
天を東西に貫き、踊っていた。
ミティはつぶやいた。
「いいね、光の精霊って。気紛れだけど」
ケツァが頷いた。
「ぜったい奴ら、何も考えてないぞ」
「巨木も、地の揺れも、あふれる海も? 海だけなら、イナアも同じだよ。海沿いの丘の木が、みんな斜めに生えてるんだから。嵐のたびに、端から波に呑まれていくんだ」
「精霊は、なにがしたいのだろう」
「知らない……ねえケツァ、私、昼間ね、ここで精霊を見たんだ」
「精霊?」
「きれいな女の精霊だった。長い髪をして、土と空と夜と草の色の服を着ていたよ」
よろこんで説明するミティに対し、ケツァは顔をひきしめた。
「……まさか、アツァアスル族」
「へ。なにそれ」
「ほらっ、ミティが熊に襲われた、あの河の上流に住んでいる。話したことあるだろ」
「ええっと……」
ミティは、記憶を探った。
「……そうそう。外を嫌う、偏屈な一族」
「なんかちがうぞ。まあ合っているが……」
その時であった。
ごっ……
地の揺れ――また、地震が来た。
激しい、突き上げるような揺れが。
ケツァもミティも立ち上がれない。
「座っていたからよかったけど……ケツァ、すごい揺れだよ」
「ああ、こいつはこれまでで最高だぞ」
宴の場ではちょっとした混乱に陥っていた。革テントが象牙の支柱ごと次々と倒れる。
石が転がり、海は波立つ。
耳をつんざく音はいつまでも続く。岩場のケツァは耳がだんだん痛くなってきた。
「一日でこんなに地の震れが――」
いつの間にか、ケツァとミティは抱き合っている。
「ケツァ」
「――はじめてだ。いったいどうしちまったんだ、ミクトランは。誰か教えてくれ!」
「教えてほしいか?」
「ああ、教えてく……誰だ?」
「わかった」
その声は、離れたところから聞こえた。
「教えてやろう」
ケツァとミティは、硬直したまま、声のほうを向いた。
そこには、女が立っていた。
二人は息を飲んだ。女は、オーロラの照り返しでもよくわかる原色の服を着ていた。とても長い黒髪が風に揺れている。間違いない。昼間、ミティが見た女だった。
ミティが、戸惑った声をあげた。
「う……そ……」
地震は、激しい。誰も立てない。
なのに女は、木のように直立していた。
ケツァは、思わずたずねた。
「地の……精、ですか」
女は無感動に首を傾げた。
「はて、いきなり人外呼ばわりされるとは。私はそれほど変か?」
ミティがうなずいた。
「だって、立ってる……なんで?」
「秘密だ」
これに対してなにか言いたげなミティを、ケツァが抑えた。
「ところであなたはアツァアスル族ですか」
「うむ。その通りだ」
「ケツァ、やはり偏屈一族なの」
ケツァはあわてた。
「ミティ、変なこと言うな」
女もいっしゅん口を閉じた。
「……おもしろい娘だな。まあよい、ところで、この地がどうなっているのか、知りたいのであろう」
「あなたは何か知っていますか」
「ああ。もうじき大きな禍で水没する」
女がさらりと、真顔で言い切ったので、ケツァは言葉の意味を受け入れかねた。
「……水没する? ミクトランが?」
「ああ」
「たしかに、海辺は波の精霊に喰われています。《両手指の一〇倍》年もたてば――」
「そんな悠長な話ではない。氷原から、水が噴き出すのだ」
「水が噴き出すって……」
「やはり知らぬか。いいか、この地の揺れは、水が氷と岩の狭間にくさびを打ち込むことで起こっている。早ければ明日にでも……」
その時、
「ケツァ、ここにいたか!」
と叫びながら、一人の青年が走り寄ってきた。激しい地震はまだ続いている。この青年もただものではない。
「トナティ狩長」
「ケツァ、マンモスがおびえて……ん?」
青年トナティは、女を認めたとたん、険しい目つきになった。
「これはとんだ珍客だ。アツァアスル族がなんの用だ。精霊が認めぬよそ者が!」
女は肩をすくめた。
「いいか、若きマンモスの戦士。長老の誰かに聞いてみろ……きっとわかるだろう」
そして、ふいに消えた。女は最後まで、無表情で感情を表に出さなかった。
トナティは二、三歩追ったが、
「ちっ、逃げ足の速い……」
と吐き捨て、ケツァに手を差し出した。
「ほら」
「すみません」
ケツァはトナティの助力によって立ち上がった。だがトナティは、もう一人には手を差し向けなかった。
「こらあ、こんな可愛い私を忘れるな!」
「イナアの女か。もう立ってるじゃないか」
「はっ……」
ミティは両拳を握り、一人で立っていた。
「行くぞ、マンモスを落ち着かすんだ」
そしてトナティは、さっさと集落のほうに戻っていった。
地震はいつのまにか終息していた。
オーロラの嵐も散り、おぼろ光が空の闇に溶けつつあった。
* *
集落に戻りながら、ミティはすっかり腹を立てていた。
「トナティって、かっこいいと思っていたのに、思っていたのに! なんて失礼な男」
ケツァは苦笑した。
「トナティ狩長は狩り一筋で女が苦手なだけなんだ。あまり悪く言わないでくれ」
「ああいう便秘の精霊みたいな手合いが、不幸な家庭を築くの。わかるでしょ、ケツァ」
「……聞いてない」
* *
地震のせいで宴は中止された。
家がいずれも革張りのテントでしかないこともあって、さいわい死者は一人も出なかった。皆は暗がりの中で苦労してテントを建て直すと、疲れて寝てしまった。
ケツァとミティもいつしか、ひとつのテントでまどろみの中にいた。トラルとロックも同じテントだ。トラルはミティとケツァの間に、割り入るように場所を取っている。
トラルとロックがいびきをたてはじめたころ、ミティがおもむろに口を開いた。
「ねえ、起きてる?」
「なかなか寝られないよ」
「本当になるのかな」
「……水没か?」
「うん」
「朝になったら、族長に聞いてみるよ」
「アトルさんに?」
「でも二日酔いになってなければいいな」
「そうね……ケツァ、私のナミ母さんの生まれた南の地にね、火の山があるの」
「どうしたんだ、突然」
「いいから聞いて……火の山って、時々怒って、なんでも溶かすどろどろの岩を出すの」
「不思議な話だ。もしかして、それが氷を溶かして洪水を起こすって?」
「わからない……洪水って聞いて思い出しただけなの。恐かった」
「ミティ……何の事か知らないけど、恐いなら、寝ればいい」
「寝るぅ? ……変なの……ふふっ」
「あ、笑ってるな」
「ありがとう、お休み」
「へっ……お、お休み、ミティ」
* *
極北世界の早すぎる朝は静かにおとずれた。それからしばらくして、ミクトランの夏村は活性化した。人々が朝の仕事をする中、ケツァはテントから出て、東の氷原を見た。
うす青い氷床は、何の変りもない。
しかし、静けさがなんとなく無気味に感じられる。
「やはり、何も起こらないじゃないか」
そう自分に言い聞かせて、族長のテントに向かった。
族長アトルのテントは、数々の動物の頭骨で飾られていた。アトルは、テントの前で、ムース鹿の頭蓋に腰掛けていた。
「アトル様、おはようございます」
「おおっ、ケツァ。昨日の英雄譚を、ぜひまた聞かせてくれ」
「はい、また今度……それで、じつは、教えていただきたいことがあります」
「めずらしいアツァアスルの女のことか」
「……もう知っていましたか」
「トナティから聞いた。くわしいことはケツァが話に来る、ともな。その通りになった。あいつの言葉には無駄も誇張もない」
「……そうですか。では……えっと……」
「何をためらっておる」
「はい……実は、これらの地の揺れが、だ……大洪水の予兆だ、と、彼女は言ってました。早ければ、今日にでも起こる、と」
最後のほうは自信なさげに、声が尻すぼみに小さくなった。
しかし、洪水、という言葉に、アトルは激しく反応した。
いつもの落ち着きが影をひそめ、アトルは明らかに狼狽や、あるいは取り乱しに近い表情への激変を見せた。
「……洪水大禍が、来る。ばかな、あれはまだ起こらぬ……時間はあるはずなのに……たしかに、地の揺れが来ている。それに……アツァアスルが、教えてくれる? 知り得ているのか……どういう……ことだ?」
アトルは、がたがたと震えだした。まるで一族の伝承の奥底に封印してあった、禁忌が解かれたように。
ケツァは、あまりの効果に自分も驚き、アトル同様に心を乱した。
「ア、アトル様、どうかしましたか」
アトルは、いきなり叫んだ。
「封印の口伝よ、精霊よ、何を考えている。早すぎるぞ、まだ再現するなよ!」
「アトル様……」
「ケツァ……おまえは、重大な情報を伝えてくれた。すぐに長老会議を招集する」