憑依注意報!
小説幽霊になった憲は、幼馴染みの智真理を守るべく憑依し、犯人を捜す。
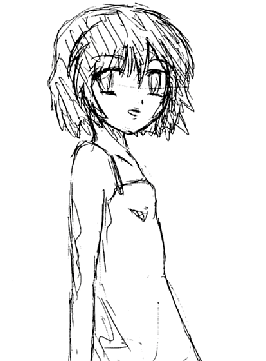
 第一章 殺人注意報!
第一章 殺人注意報!
「ねえ……死んだこと、ある?」
突然そんなことを聞かれて、すぐに「はい」と答えるやつはいないだろう。
相手が友人や後輩なら「はあ?」と聞き直し、問いを繰り返してきたところで小馬鹿にするのが関の山。
たとえ先輩や魅力的な異性であっても、機嫌取りでまともに答えるやつはすくないのではないか?
なにせ、「死んだこと、ある?」だ。
まず体験したと話せることじゃない。いや、無理な話だ。臨死体験とかがあるが、あれは「死にかけた」の範疇だと思う。
死ぬということは、その先がないこと。
もうそれで終わり。
本当の「死」とは、もはや弔うしか未来がないという、絶望的な状況だろう。
それゆえ無理な話、というわけだ。
だからオレは、今の状況をとても不思議に思っている。
オレに「死んだこと、ある?」と問いかけてきた桂川女史の顔が、ちらりと浮かんだ。
そのときオレは、桂川に「誰にもありえません」と言ってのけた。当然だと思っていた。
だが……
せいや!
盲点だった……たしかに、この状態なら有り得た。
「死んだこと、ある?」
「はい」
そう答えられる状態。
オレには、意識がある。
そして――
あのときオレは、自分の死体を見下ろしていたのだ。
* *
太平洋に面する河地市の街は、三方を山地に囲まれた平野にある。
平野には三つの細い山峰が侵入していて、市街の形を複雑にしていた。その山峰筋のひとつの先に、先山はあった。
先山――標高二〇六メートル。
頂から見れば、三二〇度もの大パノラマで河地市の市街や大海原を一望できる。街の中に張り出した山。それゆえ先山という。
後方には谷を挟んで標高二五〇メートルほどの中山があり、そのさらに奥がようやく山地らしい地形に連なっている。
さて、先山はつい三年前までは標高が二一二メートルあった。頂からの景色も、今ほどの広範囲は木々が邪魔して見れなかった。
この三年でなにがあったのか?
まず五年前、山頂に続く遊歩道が封鎖され、看板が立った。
【工事予定地につき立ち入りを禁ず】
市はあらたな遊歩道を整備し、中山までの迂回路を作った。
先山の頂から中山の頂へとつたう定番の遠足コースがなくなったが、近隣の小学生はかえって喜んだ。
登る山はふたつよりひとつのほうが疲れないし、遊ぶ時間が増えていい。
小学生の幸せをよそに、先山にはどこかの測量会社が入り、土地の境界を厳密に測っていった。
同時に土地内の木々にマーカーが付けられ、その種類と太さが記載された。
四年前、工事がはじまった。
黄色い工事車両が次々と先山の麓に集められた。木を切り山を削り、ある部分は盛り足して、道が整備された。
道は一年で山頂まで達した。
山頂部の木々はほとんどが切られた。そして五台ほどのショベルカーが山頂をゆっくりと削り、あるいは埋めてなだらかにしていった。
二年半前、山頂には運動場がふたつは作れる平地が誕生していた。
大量の建材が運ばれた。
杭を打ち基礎が作られ、鉄骨を組み、コンクリートを流し込み、建物となった。
こうして二年前、私立先山高等学校の校舎がお目見えとなったのだ。
あとは生徒を待つだけだった。
そして現在……学校創立二年目の晩夏。
* *
九月半ば――二学期が始まって二週間が経とうとしていた。
運動部のいくつかは、来る秋の各競技大会に向けて練習に余念がない。放課後、先山高校のグラウンドはこつこつと練習にいそしむ生徒で溢れている。
「はっ、はっ」
土煙の中、汗にまみれた肉の集団が二つの勢力に分かれ、頭をつつき合わせていた。ラグビーのスクラム練習だ。
「はっ、はい、はいっ」
掛け声を一斉にあげ、調子を合わせて上半身に力をこめ、前に押す。互いの頭と肩とがこすれ、かなり音が出る。
スクラムはボールの主導権を得る重要なアクションなので、部員は皆真剣であった。
なにせ昨年は創部一年目で一年生だけ。頭数が足りず県大会に出られなかったのだ。その悔しさをバネに、今年は全国大会――花園ラグビー場を本気で目指している。
問題は今年の練習試合で、目下県内勢に底抜けで全敗していることだ。それゆえ身が入るというものだろう。
――と。
「せいや、避けろぉー!」
男とも女ともつかない中性的な高い声が、部員たちに届いた。
ラグビー部の面々はしかし、声を無視して肩と腰に力を入れ続ける。いや、真剣なあまり、ちっとも耳に入っていないのだ。
あるいは入っていたとしても――
「避けろってんだろ!」
声はより大きくなった。土を蹴る駆け足も聞こえてくる。
土を蹴る音?
「うむ?」
部長の野代は思わず顔を上げた。
こちらが避けるとしたら、おそらく近くの男子バレー部のボールくらい……普通なら屋内で練習するはずだが、創立間もない先山高校には、予算の関係で体育館がまだないのだ。
だが――バレー部は間借り練習しているテニスコートで、なにも変わることなくトス練習をしていた。
「せいやせいや、避けろー!」
土の音はますます大きくなっていた。
土!
テニスコートは土ではない。それゆえ野代は不思議に思ったのだ。
どこだ?
野代は首をうごかそうとしたが、スクラムを組んでいるのであまり動かせない。
「どうしたんで?」
向かいの副部長、前田が怪訝そうな顔で尋ねてきた。
「いや……なにか、近づいているようだが」
「はい?」
前田の動きが止まる。
部長と副部長の異変に気付き、他の部員たちもかけ声をやめた。
だが惰性でみな体だけは動いている。
「……なんだ?」
部員たちが声の正体を量りかねたとき、突如として前田の頭を誰かが踏みつけた。
「ぶげ」
溜まったものではない。
副部長はそのまま沈み、スクラムはすこし陥没した。
だがみな鍛えているので、スクラムは崩れはしない。密接に肩を寄せ合い、副部長にかかった負荷を支えている。
その重さは部長である野代にも掛かった。
「うぬぬ……なにやつ」
野代部長は前田の頭に乗る不届き者をゆっくりと見上げた。
靴は陸上部が採用しているランニングシューズ。白い短パンを穿いているので男子だ。上半身も学校指定の体操服だ。
顔は逆光なのであまり見えない。だが風が吹いて正体がわかった。なびく髪。独特のあの長い後ろ髪を持つ男子は、校内に一人しかいない。
不敵な一年の有名人。陸上部期待の新人で、せいや、という妙な口癖あり。
「おまえか――室崎憲!」
「だから言ったでしょ。避けろって」
憲は舌を出すと、前田の頭からぴょんと飛び降りた。まるで軽業師のように、空中で一回転してである。
音をほとんどたてずに地に降りる。
髪がふわりと空気を通しながら、肩に二度目の着地をした。
髪が収まった顔は、目元がわりとひょうきんな感じで目立っていた。鼻と口の配置バランスはよく、ハンサムとは言えなくもないていどの端正さだ。目のせいでどちらかと言えば個性的な顔立ちと言えるだろう。
だが、体のしなやかさと動きは一級品だ。
野代は一瞬やわらかい動きに見とれて思わず感心したが、すぐに顔に険しさを呼び戻した。
「きさま、前田に謝れ」
だがスクラムを解除せずに言う辺り、なにやら妙だ。ほかの部員たちも、当の被害者である前田も、組み合ったまま憲のほうを半ば面倒だなといった感で見ている。
なにやらこのラグビー部が怪しげな集団に見えてきた。
「すみませんでした野代先輩、前田先輩。そして諸子方々。それでは、せいや!」
憲は丁寧に腰を折って礼をするや、身を返すと走り去っていった。有名人を見送ると、ラグビー部の面々はなにもなかったかのように練習を再開した。
やはり妙に怪しい。
本当はなにもないのだろうが、熱中する連中は端から見るとどうしても怪しく見える。
* *
憲は野球部が練習するフェンスの脇で足を止めた。そこにはすでにランニングを終えた陸上部の面々が集まっている。
男女七名。そこに憲が加わって八名。
憲はその中で一番おおきな背中を見つけると、遊ぶリスのように小走りで近寄った。
開口一番、
「うひゃあ、本当に怒らないですよ部長!」
「わはは! そうだろそうだろ!」
熊さんのような声を張り上げ、背中がゆさゆさと一八〇度旋回した。あらわれた腹もでかい。
熊さんの腹、熊さんの手足、熊さんの目。
怖い熊でなく、かわいい熊さんだ。
知らない人には相撲部にしか見えない陸上部部長の勢多は、まさしく熊さんのように笑っていた。
「小生の観察眼に抜かりはないわ、わはは!」
「すごいや! あいつら完全に練習のことしか頭にないですね」
「わはは、だからこそからかい甲斐があるというものさ」
これで走り幅跳び県内三位の記録を持っているのだから、世の中不思議である。
「せいや、たしかにそうですね――そうそう、これで賭はオレの勝ちですよ。ふふん」
「わはは、おまえら言った通りだろう? お化け饅頭を小生とケンにおごれよな、わはははは!」
「せいや! 楽しみ」
憲と部長は勝ち誇って仲間たちを見渡した。
それに陸上部員たちは苦笑しつつも、頷くしかなかったのであった。だが――憲はともかく、勢多部長の食欲は底なしだ。小遣いの心配をする者が大半だっただろう。
「――なにしてんのよ!」
とつぜん、場に緊張が走った。
いや、それは主に約二名の緊張だった。
憲と勢多は、背中にちくちくと痛い視線を感じた。
軽快な足音が近寄ってくる。
だがそれは、二人にとっては地獄の使者に等しかった。
痛い視線は、なにやら息苦しい圧迫感を感じさせるほど強くなってきた。
憲はおそるおそる、振り向いた――
いた。
怒りのオーラを発散させる、マネージャーの十市智真理だ。ショートボブの活発な性格をよく表している髪と、赤いジャージがトレードマークだ。
ただ背が一四七センチと低く、憲を見上げる格好になっている。
大きな黒瞳におびえる憲を映し、智真理は灰色背表紙の部活動記録帳を振りかざした。
「天誅!」
ぱしーん。
憲は避けなかった。いや、避けられなかった。蛇に睨まれる蛙の状態だったからだ。
憲は痛みに頭を押さえた。
「っ……、なにすんだよ!」
「ふんっ。またバカやって、スパイクで相手が怪我したらどうするのよ」
憲は頭をさすりながら、靴裏を智真理に見せた。
「この靴にはスパイクなんかねえよ。ちゃんと選んでるって」
「ふんっ、たまたまかもね――ともかく!」
智真理は部員たちを睨み回した。
みな首をすくめたり、あるいはあらぬ方向を見たり。太陽を見てしまって慌てて目を押さえるうかつ者もいた。
「十市屋のお化け饅頭をおごるとやらの件は、一切無効とします」
それに部員たちは黙ってうんうんと頷く。
天から降った幸運だった。大食漢の勢多になけなしの小遣いを喰われずに済む。
勢多が恨めしそうにぼそり。
「別にいいではないのか? 十市屋はまさに十市君の家じゃないか。儲かるぞ」
「あいにくさま。お化け饅頭はべつに部長が食べずとも、いつも完売してます」
十市の勝ちだった。
「うぬぬ……」
このままではお化け饅頭をたらふく味わうという一世一代の野望が潰える。勢多はわずかな逆転の望みを託し、憲に振った。
「ケンよ――同棲している身だ。奥さんになにか言ってやってくれないか?」
しかし、ケンは勢多の要請に動かなかった。
憲の額に汗が一筋。そして小さく首を横に振って拒絶した。汗が飛んだが、また新たな流れが耳元に垂れる。
「なにが……」
智真理嬢の必殺の記録帳が振りかざされた。
「なにが奥さんですって! せっかくさっきは憲だけで見逃してやったのに」
本来の目的よりもそちらのほうが使用頻度が高いと噂されるハエ叩きアタックが、本日二度目の音を響かせた。
「ふごお!」
直後に三度目も鳴った。
「なんでオレまでー!」
「憲はついでよ!」
先山高校陸上部は、一年のマネージャーがすべてにおいて権力を握っているのだ。
* *
暗い。
ついでに狭い。
けっして広くはない部屋。
そこで、影が蠢いていた。
中肉中背。
暗がりで動いているので、比較の対称とするべきものがすくない。よってオレンジ色の薄明かりが照らす近くのドアと、床のタイルで影の大きさを判断するしかない。
普通の背丈、普通の体格。
そして張り出した肩から、おそらく男。
その人影は部屋の中に並ぶドアのひとつをゆっくりと開け、しゃがむとなにかをセットしはじめた。
だが――足音が聞こえた。
男は動きを止めた。
足音はしだいに大きくなり、やがてヒール独特のカツーンという響きが聞き取れるようになった。
男は動かない。
部屋はあいかわらず暗い。
男の顔は、ある方向を向いていた。
その先には、ひとつの扉があった。
縦長の部屋の入り口に唯一、磨りガラスの小窓を張った扉。
横にずらりと並ぶドアはどれも上下に空間がある適当な作りなのに、そこだけはちゃんと壁に一切の隙間がない。
そのガラスに横顔が映った。
髪が長い。女だろう。
音はもっとも大きくなっていた。
男は腰に手を添えた。
――と、小窓の女は消えていた。
音は小さくなっていた。
ヒールの音が聞き取れなくなった。
男は安心したように肩を数回上下させると、ふたたび作業を再開した。
* *
三〇分後……
あれ?
今年で四〇歳になる女性数学教師、仁科教諭はふと、トイレに行きたくなった。
おかしいわね。まだ大丈夫なはずなのに。
席を立ち、トイレに向かおうとした。
「あら、どちらに、仁科先生」
向かいの席に座ろうとしていた同僚だ。
「いえね、ちょっとあちらよ」
女性教師の間では、「ちょっとあちら」がトイレの暗号だった。
「あれ、方向がちがいますが」
「東は調整中でしょ、まだ」
「それなら終わったようですよ。たったいま図書室からの帰りで見ましたが、札はありませんでした」
「あらそう。じゃあいつもの東にしましょう」
仁科は職員室を出ると、女性専用の東トイレに向かった。
たしかに。
午後から扉に貼ってあった「調整中」の紙がなくなっていた。つい三〇分前にここを通過したときはまだ貼り紙があった。
このトイレ調整は朝の朝礼では知らされなかったことだ。もっとも先山高校は仁科がいままで働いたどの学校とも異なり、やたらと急な行事やイベント、仕事が多かった。
校長先生も教頭先生も穏和な方なのに、まるで若者のような性急さがこの学校にはある。まあまだ創立二年目だから、活力の裏返しだろうと仁科は取っていた。
仁科はトイレに入った。
いつもの指定席は奥のトイレ。そこは開いている。
と、ポケットから急に小銭が落ちた。
なぜ?
小銭は落ちるような入れ方はしなかったはずだ。
だが小銭はじっさいに落ち、床を転がる。
仁科は小銭を追いかけた。
小銭はころころとあるトイレに滑り込んだ。
仁科はドアを開けた。
あった。小銭は便器のそばに落ちていた。
仁科は小銭を取ろうとかがんだ。ヒールなのでバランスを取りにくい。
と、掴んだとたん小銭はつるりと滑り、なんと便器の中に落ちてしまった。
くそ!
仁科はおもわず便器のなかに手をつっこんでいた。若い子ならともかく、仁科は人生経験をそれなりに積み小銭の価値を知っている。だれもいなければ平気だった。
小銭はさらに滑り、前の深いほうに落ちた。
直接では見えない位置に落ちたので、小銭はよけいに取れない。
なによもう。
仁科は顔を便器のなかに入れた。
あった!
仁科は獲物を掴んだ。
うふふふ……あらなによこれ?
仁科の目前に、妙な黒いものがあった。
それは普通にトイレを使用している限り、まず見つからない死角に添え付けられていた。
「――ぎょえええ!」
仁科はおばさんパワーを爆発させて絶叫した。
* *
林のなか――
ちいさな画面に映るおばさんの顔に、若い男は舌打ちをした。
まさかいきなり見つかるとは。
まだ一人も撮してないというのに。
この一月かけた労作が、もう水の泡だ。
若い男はおばさんの画面を消し、機械のスイッチも切ってアンテナを畳み、装置をリュックに詰めた。
……混じっている。
世界は混じっている。汚れている。
だから、純粋なものを見たい。
絶対に見てやる。
……もうひとつある。
せっかく真似をしたんだ。
テレビであれほど放送したら、知識も増えてくる。
すべてテレビが悪いんだ。
ボクは悪くない。
ボクはテレビに教えられたんだ。
たしかにそのあと、ネットで情報を仕入れたけど。
でもボクは、情報の通りにしただけだ。
そしたらできたんだ。それだけだ。
ボクは……
* *
次第に暗くなり、黄昏のオレンジが山の稜線を浮かび染めた。
グラウンドにいた面々は練習を終え、陸上部もその中に混じって部活棟に戻ってきた。
体育館がまだないくせに、どういうわけかクラブ棟は完備している。陸上部は部員九名という都合で男女混合だが、更衣室を兼ねた部室は男子と女子で二つもあてがわれていた。
男子たち五名は、男子部屋にいるときだけ落ち着ける。なにしろ、あのマネージャーもさすがに入れない聖域だからだ。
「ふう……」
勢多部長は上半身裸で、肩にできた赤い腫れを掻いていた。
智真理の背丈では、勢多の頭にはハエ叩きアタックが届かないのだ。勢多の背丈は一九〇センチ近い。
「大変だったな、今日は」
「せいや、たしかに……オレは今日も、ですけど」
憲は頭のコブをいちいち確かめようとは思わない。一週間を置かず、そこに智真理の攻撃が炸裂している。
腫れの指定席といってもいいくらいだ。
「部長が食らったのはひさしぶりですね」
「うむ――さすがに夏休みを置くと、小生もつい忘れてしまう。なにがハエ叩きアタックのトリガーになるのか……あの爆弾をマネージャーに採用してしまったのは、小生の人生最大の誤りだ」
「でも、ちゃんと仕事はしてくれますよ。ほかの部のマネージャーに比べて、手を抜きませんし」
「毎度痛めつけられているのに、よくもまあ援護射撃ができるものだ。そうか――うんうん」
勢多はなにやら勝手に納得して勝手に頷いている。
「応援はするが、残念ながら小生自身にはたいした体験はない。あまり当てにはするなよ」
「うっ」
憲はおもわず唸った。
まわりの先輩や同級生もからかい気味に囃したてる。
困ったな……
これも毎度のことだった。
勢多をはじめ、陸上部の男子の面々は、どうやら憲が智真理を好きだと誤解しているようだ。
色気づいた連中はすぐに色事に結びつけたがるので、いちいち反論するのもアホらしい。
ムキになるほど、逆効果だ。
憲は智真理が好き。
それは十市智真理の家にすでに七年もお世話になっている関係上、つねに室崎憲についてきたゴシップだった。
でもゴシップとはロマンス的な匂いがあってはじめて成り立つものであり――常に角つき合わせている、しかも一方的に暴力を振るわれている身としては、なんとも相手にするのが億劫になるものだろう。
不幸なのは、智真理も女子たちからおなじように思われていることか。
智真理は憲が好き。
暴力は愛情の裏返しだというのだ。いまさら小学生でもあるまいに。
血の繋がらない結婚可能な男女がひとつ屋根の下で過ごせば、かならず恋愛関係になると思うあたり、みんな夢見がちな年頃で、なんとも平和なものだ。
智真理はどうか知らないが、憲は智真理に、姉弟のような感情しか抱けないと思っている。智真理は憲より二ヶ月ほどお姉さんだ。
いつもひどい目に遭わされているのに、いざ悪口を言われるとつい智真理を庇うのは、十市の家に養われているという負い目だろうか?
とにかくこの勘違いのせいか、憲も智真理も、恋の沙汰とはずっと無縁であった。
いずれにせよ憲は、からかわれることには慣れていた。
「ところでケン、十市君の夏休みを挟んだハエ叩きで思い出したが、また出たそうだぞ」
「はい? ――もしや出たって、まさか盗撮カメラが?」
「ああ。トンボを倉庫に戻したとき、警察が来てた。先生に話を聞くと、今回は教務棟の二階東トイレらしい。女性教師狙いだな」
そこは女子専用だ。
夏休みまえの一学期期末辺りから、学校を騒がせている盗撮騒ぎ。最初は噂だけだったが、七月初旬に実際に女子バレー部更衣室で小型カメラが見つかり、さすがに警察沙汰になった。
同時に近隣の学校でもいくつかカメラが見つかり、集団による金目当ての犯行だろうということで、警戒態勢が組まれた。
隠しカメラでわいせつな盗撮ビデオを作り、裏で売る。世の中にはそういった不埒な組織があるらしい。
今回の犯人は「カメレオン」と呼ばれている。毎回異なる隠しカメラを使うからだ。
残念ながら夏休みに突入して学校関係の警戒は無意味に近くなったが、今度は市民プールなどで相次いで発見され、女性の敵として、全国放送で特番が組まれたほどだ。
騒がれたのでさすがに懲りたのか、八月半ばになると、「カメレオン」の隠しカメラはぱたりと発見されなくなった。
だが――
「わずか一月の潜伏で、カメレオンはまた動き出したというわけさ。よりによってうちの学校がその最初のターゲットってわけさ」
「まったく女の敵だな。許せない。犯人を見つけたら、せいや! と痛めつけてやる」
憲の怒りに、他の部員たちもうなずく。
ふつうこういうビデオには若い男なら怒りの前に好奇心が向かいそうなものだが、先山高校の男性諸子に関しては事情が異なる。
なにしろ一連の騒ぎは先山高校が発端だったのだ。犯人として、高校の男子生徒や、男性教員が疑われても仕方がなかった。
ほかの学校でカメラが見つかるまでの約一週間、先山高校の男性陣はなんとも辛い日々をすごしたのだ。
それゆえ怒りしか湧かない。
これは正義というよりは、無実なのに疑われた、という面子や名誉の問題だった。
いや、部外者の犯行らしいと結論づけられるまで、男子の間でもお互いを疑い合っていたのだ。それに対する反動の怒りもプラスされていた。
怒りのせいか、着替えには時間がかかった。
憲はうすい鞄を掴むと、仲間に混じり男子部屋を出た。
陸上部の男子部屋はクラブ棟の二階にある。憲たちは階段を下りた。
下で、制服に着替えた智真理が待っていた。
先山高校の制服はブレザーだ。だが今は夏。智真理は半袖の白ブラウスに、灰色を基調とした、タータンチェックのスカートを穿いている。
ちなみに男子は上は半袖の白シャツに、濃灰色のありふれたズボンと平凡だ。
智真理の表情は、ほとんど無表情に見えた。
憲は長年の勘でわかる。
智真理になにかあった。
「――どうしたんだ、智真理」
「憲、ちょっとつき合って」
憲は無言で仲間に手を軽く振ると、先に歩き出した智真理についていこうとした。
「ほう……おくさ」
勢多部長は笛を吹こうとしたが――陸上部真の支配者である十市君に睨まれ、さすがにやめた。
* *
太陽が急ぐように落ち、終幕を迎えつつある黄昏の空に星がいくつかきらめきはじめた。本日は晴天で、星は存分に輝ける。
だがいくら空がきれいでも、風はやはり暑い。それが地球温暖化の影響かどうかは知らないが――
「暑いな。山頂だから夏が涼しいと思って期待してたんだけど、たかが二〇〇メートルでは、たいして効果ねえな」
憲は智真理の横顔をちらりと見た。
「…………」
なんの反応もない。
二人はクラブ棟から建設中の体育館と校舎棟の間を抜け、中庭を進みつつ現在は教務棟に向かっている。
先導する智真理はずっと無表情で、憲は事情も知らずについているだけだ。
まもなく最終バスが出る時間だが、どうやら間に合いそうにはない。
そうなると麓まで歩いて降りることになるが――自転車通学の憲は下の自転車置き場まで行けば済む話だが、智真理はバス通学だ。
憲はたいして賢くない頭を動員して、なんとか推理した。
「うーむ。どうやらオレに足になれと?」
「…………」
「駐輪場から農道を駆け下る自転車の速度は知ってるだろ? それでもあえて、乗りたいのか?」
「……仕方ないじゃない!」
「歩くこともできるが?」
「遅いからいやなの」
「いやなら乗るなよ」
「でも遅いのはもっといやなの!」
智真理は眉をつり上げて憲の胸を強く押した。憲は予想していたのでかるくよろけただけだった。
「いきなりプリントの印刷頼まれたんだもの。いざとなれば、私が憲と帰れることを知ってて頼んだのよ、玉城先生は!」
玉城先生は智真理のクラス担任で、この六月に結婚したばかりの女性教諭だ。
「今夜は典昭ちゃんの誕生日だから、絶対にパーティーをするんだって」
「新婚はアツアツだねー。だからって断り切れない智真理って、相変わらずなかなかのお人好しだな」
「……いいじゃない、別に!」
「へえへえ」
暗くてよく見えないが、おそらく智真理の顔は真っ赤だろう。恥ずかしさと、そして帰る際の怖さで。
先山高校の駐輪場は、公道から高校へつづく私道の登り口にある。
標高は五〇メートル。
自転車はそこから農耕車両優先道路を一気に駆け下るのだ。時速は軽く三〇キロには達するだろう。平地まで信号がないので、容易には止まれない自転車でも平気だ。
一方登るのは、じつは慣れればたいしたことはない。標高五〇メートルまでは、だいたい三ないし五分も粘ればすぐだ。
自転車通学の連中には、降りるときの速度が楽しみな者も多い。憲もその一人だった。
憲はいつも坂を下る。智真理は今日のように最終バスに乗り損ね、憲の後ろに乗って坂を下ったことがこれまで二度ある。
二人乗りの坂下りは危険な行為に思えるし、事実そうだろう。
だが校則ではべつに禁止されていないし、玉城先生も、まさか送る側が智真理を後ろに乗せて下るとは思っていないだろう。坂の下までいっしょに歩き、そこから二人乗りをすると考えるのが常識だし、憲もそう思う。
智真理はよせばいいのに、「歩くのは遅いからいや」と言って、毎回毎回、わざわざ怖い思いを選んで後で後悔していた。
「ねえ――」
二人が教務棟に近づいたそのときであった。
「――そこのおふたりさん」
憲と智真理に、凛とした声で話しかけた者がいた。
「はい?」
憲が声のほうを向くと、そこにはスレンダーな女子生徒が立っていた。教務棟の外壁に寄りかかり、視線はまっすぐ憲を見定めている。
自然、憲と女子生徒は見つめ合う格好になる。
その女子生徒は、二重瞼ではっきりとした目元を持ち、まるで日本人形のような卵形の顔立ちをしていた。さらさらな長い髪は、スカートまで達している。
正直――美しい。
だが、どこか儚さを感じる。
明日にも散りそうな、脆いバランスの上に成り立っているように見える美。それゆえ普通の男には触ることさえ許されぬ、まさに不可侵に思えそうな芸術。
「……桂川玲華女史」
憲は彼女を知っていた。
いや、校内で彼女を知らぬ者はいない。一年のアイドル。男性女性を含め、玲華女史を敬愛しない者はいないのではないのか? ふと、そう思ってしまう。
なにより彼女は、私立先山高校を作った、桂川グループの一族に連なる者だ。
桂川グループは林業から身を起こし、いまや金融業以外のほとんどの業界に一〇〇社ほどの系列を持つ、古くからの地元の名家だ。それがいきなり教育産業に手を広げたのが先山高校だった。
桂川女史に話しかけられたのは、憲ははじめてだった。あまりに現実離れした人なので、意識して近寄ったこともなかった。なによりクラスが違う。
だからいきなり聞かれた内容に、憲はさらに現実感を失っていた。
「室崎君。ねえ……死んだこと、ある?」
――なんだ?
桂川女史は、また口を開いた。
凛とした声で、非現実的な言葉を紡ぐ。
「死んだこと、ある?」
なにを聞いているのだ?
脈絡がない。あまりにも。
そんなことを、この美しい人がしゃべったというのか?
たしか入試ではトップだったと聞いた。
入学式では、入学生代表でかなり立派なことをすらすらと真顔で言ってのけた。
その後の中間、期末でも、二位に総合で二〇点以上は差をつけて、圧勝でトップを維持している。
憲は混乱しはじめていた。
これが桂川女史でなければ、一笑に伏せるところだろう。だが――なぜ、この人はオレに、変な質問をするのだろう。
こんな頭のいい、オレとは身分が違う、住む世界の異なる才女が……
まさか、夏休みの間でなにかあったのか?
そうか。きっと勉強のしすぎで熱にやられたんだ。かわいそうに……
こう考えてすぐに納得するあたり、さすがに鞄がうすい憲である。
憲はいつのまにか、気が楽になっていた。
当然であろう結論を言う。
「死んだことはないですね」
「そう――気のせいだったのかしら」
桂川女史は残念そうに小さく息を吐いた。
気のせい? どういうことだ。
なんのことかはわからないが、一見ではおかしそうには見えない。
知性の輝きは、瞳からも表情からも消えてはいないように見える。やはり残暑のせいでちょっとずれているのだと、憲は根拠もなく思った。
「どうして、いきなりオ……わたしに、そんな不思議なことを尋ねるんです?」
「不思議なの? 死んだことある、という問いが?」
「死んだらそれで終わり。だから――死んだことあると聞かれて、はいと答えるのは、誰にもありえませんよ」
「誰にもありえない……たしかに、そう思うこともできるわね。なるほど」
桂川女史はなにかぶつぶつ言いながら歩きだした。
憲と智真理のほうに近づく。
憲は思わず横によけた。そうしないといけない気がした。智真理も道を譲っていた。
桂川玲華は、二人が意識して開けたスペースをまるで当然のように自然な動作で抜けた。その先のロータリーには、いつのまにか黒い外車が停車していた。
ボディガードを思わせる体格の良い男が運転席から出てきて、後部ドアを開けた。
女史は運転手に会釈をすると、外車に乗り込んだ。
車が出る直前、女史は窓を降ろした。
「……室崎君、また話しましょうね」
そして車が出る際に、憲に微笑みかけたのだ。彼女は笑みとともに去っていった。
憲をどきりとさせるのに充分だった。
体の芯がぼうっと熱くなるのを、憲は自覚していた。
「せいや……」
ちいさく口癖をつぶやく。
ぱちん。
「なにぼうっとしてんのよ!」
智真理が正面にまわり、憲の頬を挟んでいた。
「あ……ああ、智真理か」
「智真理か、じゃないわよ。なによ、でれでれして」
「ああん? あんな綺麗な人を見たら、男なら当然だろ」
「――うーむ。それは一理あるわね。でもなにか悔しいわ」
「女として?」
「……言うわね。ふん、あれほど次元が異なるものに、いちいち嫉妬するほど無謀でも暇でもないわよ。ライバルはもっと身近じゃないと意味がないんだから」
「そんなものかね」
「それよりも。なんで憲にいきなり、あんな変なこと聞いたの? 死んだことあるかって。なにか暑さにやられたのかしら」
「お? 智真理もそう思ったか」
「げ、こんなことで憲と意見が合うなんて、明日は雨が降るわ。いえ、台風が来るにちがいない」
「ひでえ……さて、変なイベントで時間をくっちまった。さっさと行きましょうかね」
「そうね。用事を済ませましょ」
* *
二人はそのまま事務室兼外来者受付から教務棟に入った。靴を脱ぎ、スリッパを履く。
校舎はすでに門が閉まっていて、ここからしか出入りできない。山の上にあるとはいえ、例の盗撮事件以降、防犯体制はしっかりしている。
事務室には、若い男性が一人残っていた。遅番の平良だ。元自衛官という変わり種で、今年採用されたばかり。だが本人に言わせれば自衛官は最後の青春で、いまが社会人一年生だという。年下に飾らない口振りなので、男女共に生徒の人気は高い。
「どもー、平良さん」
「お、室っちか。なにか用か」
憲と平良は顔なじみだ。
平良は昼になると、プレハブ食堂のお兄さんに変身する。本格的な食堂は、現在建設中の体育館の脇に建てられる予定だ。
憲は食堂一番乗りを競う武闘派の一人である。それゆえ個人的な知り合いなのだ。
智真理が平良に、コピーの旨を伝えた。
「明日の早朝というのはダメかい?」
「両面印刷で全校生徒分なんです。しかも朝に必要なので、当日だと間に合わないらしいんです」
「仕方がないね」
平良は壁のボードに並ぶスイッチのひとつを下げた。
「コピー室のセキュリティを解除した。トイレや通路はいいが、ほかの部屋には入るなよ。センサーが反応して警備会社に自動で連絡が行く。それから駐輪場までは、帰りついでにオレのスーパーカーで降ろしてやろう」
「ありがとうございます」
「あ、どうも――でも、スーパーカーって、あの軽が?」
「うるせえぞ室っち。社会人一年生の給料で、ウン百万もするやつがいきなり買えるか。決めた、おまえは乗せない。かわいいほうだけ乗せる!」
「まあ、かわいいって」
半ば本気で照れる智真理をよそに、憲はあわてて手でイエイエとする。
「せいや、ごめん! ごめんっす」
「わかればよろしい」
平良はにっと笑い、胸を張った。
野球中継を見はじめた平良に八時までに降りると伝え、二人は階段を登った。
二階のコピー室につづく廊下で、二人は物々しい立入禁止の札を目の当たりにした。
「東トイレ、入れないのね。そういえば午後に、点検中の紙が貼ってたけど」
「あー。なにやら、カメラが出たって」
「カメラ?」
「例のやつさ。カメレオン。また再発だって」
「なんですって!」
智真理は大声を張りあげた。うす暗い廊下に甲高い声が響き渡り、憲はおもわず首と肩を縮ませた。
「うるさいじゃないか」
「……うう」
さすがに音の発生源も、自身の声に縮まっている。
智真理は仄かに光っている立入禁止の札を眺めた。
「――これ、河地署のものね。それで、どうして警察は帰っちゃったの?」
「明日にでも本格的な調査をするんだろ?」
「信じられない。犯人がまだ学内にいるかも知れないのに」
「それはないさ。カメラがいつ仕掛けられたかわからないけど、まさか今日というのはないだろう」
「そんなのわからないじゃない」
智真理は心底警察の対応に腹を立てている様子だ。まあいつ自分が被害者になるかわからない以上、しかたがないかも知れない。
放っておいたら朝まで怒っていそうな気配だったので、憲は智真理の注意をコピー室に促した。
コピー室に入ると、すこし涼しかった。
「やった! 冷房の効果が残ってる」
智真理の機嫌は気温であっさりと解決した。
「さあ、刷るわよ」
智真理は鞄を開くと、玉城先生から預かったらしいプリントを出した。
それでいくつかあるコピー機や印刷機を前に、行ったり来たり。
「えーと、先生方のぶんと予備を含めて三二五枚で、原稿を元にそれを表裏に……どの機械かしら」
「手間がかかりそうだな」
「ええ。印刷そのものはほとんど自動らしいけど」
「オレに出来ることは?」
「ないわよ。憲って機械さっぱりじゃない」
「せいや。言われてみればそうだ」
憲はコピー室を出ようとした。
「どこに行くの?」
「いや……この時間に学校をうろつける経験はそうないから、ちょっと体験しておこうと思ってね」
「警備会社の人が来ないようにしてよね」
「だいじょうぶ。心得てますって」
「それからもし変なやつがいたら、捕まえてね。きっとそいつが犯人よ」
「へえへえ」
憲はかるくあしらうと、部屋を出てぶらりと廊下を歩きだした。
* *
学内はすでに平良事務員によって戸締まりがなされていて、かつ非常灯を除いて照明は消えている。すでに外は暗く、空には星が数多く瞬いていた。
憲は非常灯の明かりだけを頼りに、学内を散策した。ほとんど興味本位だったが、いざ実際に誰もいない校舎を歩くのは、けっこう面白いものだ。
いつもは明るい時間にしかいない。
喧噪の中の校舎しか知らない。
外の風の音がする。木々が揺れる音もする。
教務棟は山頂部で切られなかった森の部分に一番近い。緑の揺れる音は、いつもの一生懸命な毎日では、そうそう感じることができない。
図書室の前を通り過ぎた。
そういえば教務棟にあったんだな。
いつも朝一で来るという図書委員は、このような静けさの空気を感じて、毎日なにを思うのだろう。
なにかに夢中である毎日。なにかに追われる毎日。
森に囲まれた山頂の学校。そこに通っていながら、ついぞ忘れてしまうなにか。
いつも誰かといっしょにいたら、考えることのないこと……
それは大事なことなのだろうか? あるいは、無駄なことなのだろうか?
忙しいことと充実を履き違えてはいないだろうか? あるいは考える余裕がないのは罪ではないのか? それとも気付かないのは、己の愚かさがあるのだろうか……
孤独だ――だが、不快ではない。
中学から陸上一筋で、もっぱら走ることにしか興味のない長距離走者の憲であった。
憲は走るときの孤独が好きだ。だから自転車通学を選んでいるのかも知れない。
体を鍛えるためというだけでなく、孤独を楽しむために。
だがその孤独のなかでも、いまのような心境は感じたことはない――感じたとしても、すぐに他の雑念に混じって消えてしまっただろう。
日の光の下にあって流れる風景とは、つまりいろんなものがむりやり目に入るということなのだから。
光か……
憲はいま、見えないものを見ている気分だった。
――死んだこと、ある?
ふと、さきほどの桂川女史の問いが浮かんだ。
もしかして彼女は、オレが見ていない世界を知っているのだろうか?
彼女というフィルターを通した世界では、死も生者が体験し、語ることができるあたりまえの現象なのかも知れない……
あ――夜景。
憲が廊下を回った先に、急に開けた光景。
それは河地平野に広がる夜景であった。
標高二〇〇メートルを超える高さにいる。
広域の夜景を見るのに、充分なポジションだろう。
まだ夜の河地市は本格的に動いていない。
だがあと三時間もした辺りが、もっとも美しいと勢多先輩から聞いたことがある。そんな時間まで学校に残れるのは文化祭の後夜祭だけだが、残念ながら文化祭は三学期。はるか先の話だ。
黄色の光の帯が街を駆けている。道路だろう。色とりどりの光が輝くあたりは、おそらく繁華街だろうか。中心街を貫くアーケードの周辺は、ぼおっとした淡い光に包まれていた。河川が走る部分はとうぜん暗く、かえって浮き上がっているのが予想外でおかしい。
よく部活を遅くまでして、この夜景自体はすでに幾度も見た。
だがさきほど変なことを考えてしまったせいだろうか、今夜の景色はいつもと異なって見える。
これが、オレに見える風景……
憲は苦笑した。
いくら見える世界が人によって異なるとはいえ、考えが突飛にすぎたな。
桂川女史の言葉は、やはり理解できない。
人が生きながらにして死んだことをどうやって語るというのだ。それができるのは、RPGの世界だけだろう――
憲の思考はそこで途切れた。
キャァァ……
憲の耳に聞き慣れた声が、しかし聞き慣れないシチュエーションで飛び込んできたからだ。
「智真理!」
憲は悲鳴に即座に反応していた。
憲は来た道を走った。
邪魔なスリッパを脱ぎ捨てる。
コピー室までの最短コースを頭の中で弾き出す。
こちらのほうが早い!
憲は目前に迫った図書室の扉をおもむろに開けた。
よかった、鍵はかかっていない。
そのまま図書室を駆け抜き、反対側の扉に。こちらは鍵がかかっていたが、中からなのですぐに開けられた。廊下に再合流する。
これで一〇秒は稼いだはず。
憲は走った。
智真理!
彼女とはじめて会ったのは、七年前、八歳のときだった。
両親が不慮の交通事故でいっぺんに亡くなり、憲は母方の遠縁が引き取ることになった。
それが十市の家だった。
最初に会ったのは港だった。
フェリーから降りると、そこに智真理がいた。ズボンを穿いていたし髪も短かったので、名前を聞くまで男の子だと思っていた。
その勘違いが理由で、最初の日から喧嘩していた気がする。
しかし智真理に危機が訪れたときは、憲は常に弾丸のように動いていた。
智真理も憲に危険が迫ればなぜか助太刀していた。
いずれも大半が近所の悪ガキたちとの格闘だった。
憲は親がいず、智真理は男勝り。いずれもからかいの対称だ。しかも二人はおなじ家に住んでいる――火種には事欠かなかった。
時はうつろい、悪ガキたちも成長し、分別がついて喧嘩しなくなった。
だが――
ひさしぶりに、智真理の危機だった。
幼いころの条件反射は、久しく眠っていただけだ。憲の本質は変わってはいない。
危機だ。
だから、助ける。
それだけ。
コピー室が見えた。
扉から漏れる光に、人影が映る。
動いている。
争いか?
憲は部屋に躍り込んだ。
光に目が慣れない。
二人いる。憲は確認するまでもなく、背の高いほうに勢いざま跳び蹴りをかました。
「がはっ」
男の声。やはり。
倒れる男の背中。深く被った帽子のせいで顔は見えない。
飛び退くもう一人、ひるがえるスカート。
「憲!」
「智真理、どいてろ!」
憲は暴漢に蹴りを入れようとした。
だが暴漢は横にころがり、憲の攻撃は外れた。
「うぬ?」
靴がないので、跳び蹴りは思ったほどのダメージを与えなかったようだ。
男は立ちあがり、そのまま部屋の外へと逃げる。
「待て!」
憲は男の後を追った。
追いながら暴漢の服装をチェックした。
夏なのにジャンパー。下はジーパン。帽子は野球帽の類か。背は――オレより高い。
顔は、いまだ見ておらず。
ぜったいに拝んで殴ってやる!
きっとこいつが盗撮犯にちがいない!
――と、暴漢の前に、ライトの光。
「だ、誰だおまえは!」
「くっ」
「平良さん! 痴漢です!」
「な……なにぃ?」
動揺する平良。あたりまえだ。これが普通だろう。
憲は高校に上がってからはさすがにまだないが、中学以前の喧嘩の場数は多い。
有事に素早く反応できる者のほうがすくないはずだ。
平良はしかしやるもので、動きが堅いながらも不届き者を止めようと試みた。
ライトをふりかざし、駆け抜けようとする痴漢野郎に殴りかかった。
だが、動きは相手のほうが若干よいようだ。
その肩にライトが当たったが、構わず押し通した。
平良は自衛隊にいたくせに暴力に慣れていないのか、それだけで勝手に体勢が崩れた。
その隙に、男はさっと先に走っていく。
「待て!」
前のめりに歩いて転ぶのを抑えている平良の脇を、憲はすり抜けた。
男は階段を駆け下りた。
その先は事務室だ。まえもって逃走経路を知っていたのだろうか。
憲も後を追った。
男は教務棟の外に飛び出した。
ロータリーのなかを、闇に駆け下りる。
憲も靴下のままで後を追う。
見れば、男は足袋のようなものを履いている。そういえばあまり音を立てていなかった。
憲の怒りは増幅された。
音を消し、息を潜め、なにをしていたのだこの男は。
そしてなんの目的で、智真理を――
とにかく、ぶち倒す!
男はロータリーを抜け、運動場脇通路を抜け、バス停留所を通過した。
その先には、山頂部から下へと降りる私道がある。農道までの距離、一・四五キロ。
長距離となると、憲の得意分野だ。
中学時代では県の駅伝大会で区間賞に輝き、いまはトラック競技で、二年でのインターハイ出場を目指している。種目距離をまだ絞っていないが、二キロメートル以内ならハイペースで走りきる自信があった。
だが――男は三〇〇メートルほど降りたところで、とつぜん舗装路から脇の林に入っていったのだ。
「げ!」
憲もあわてて男の後を追った。
そこは軽自動車も走れない、細い未舗装路だった。
暗くてよく見えないが、かろうじて草ぼうぼうの道が見える。
かつての遊歩道だ。学校が完成すると立入禁止も解かれて道は復活したが、もはや利用者はおらず、事実上の廃道だ。
「くそっ!」
憲は走ろうとするが、足裏に小石が当たり、痛くて走れない。仕方なく草の生えているところを選び、歩いて追うしかなかった。
「室っち、痴漢はどうした!」
一分ほどして、平良がライトを持って追いついてきた。
「平良さん、智真理は?」
「智真理? ああ、あの女の子か。警察に連絡を入れている。それよりも、当の痴漢はどうした?」
「この下です」
憲が指さしたのは、未舗装路からさらに脇に逸れ、下に降りる道だった。まさに獣道みたいな感じなので、さすがにここからは靴下だけで追うのをためらっていた。
「これは……なんだ?」
「裏道です」
「ほお……噂には聞いていたが。直に見るのは、はじめてだ」
くねくねと一・四五キロ続く坂道。
自転車通学組は下からバスに乗ることもできるが、金を惜しんで坂道を歩く者も多い。だが世の中正直に舗装路を歩く者ばかりでもなく、こうしてバイパスする裏道が各所に出現したわけである。
「ここは二番目に長いところです。一気にだるまカーブまで降りるんですよ」
「……オレはここを降りよう。室っちは靴下だから、出口で挟み撃ちにできないか?」
「いいえ、裏道は途中で他の方向にも枝分かれしています。追うほうが確実です! ライトを貸してください」
「あ――」
憲は平良のライトを奪うと、そのまま獣道に入っていった。
ライトで足下を照らしつつ、憲は小走りで駆け下る。幾度か利用したことはあるが、こんな速度で抜けるのははじめてだった。
裏道は表の舗装路より短時間で上下山するのが前提なので、自然急斜面になっている。足の裏にかかる負担はおおきい。
つぎつぎと小石が足裏に刺さる。確実に出血しているはずだが、痛みを感じるたび智真理のことが頭によぎる。憲は構わず降りた。
光さえあれば、何度も通っている道なので、多少バランスを崩しても立て直せる。
「ひえー、待ってくれよ」
すぐ後方を平良が追いすがる。靴を履いているとはいえ、夜中ではじめての道だ。なかなかの運動神経だった。
「――なあ、室っち」
「はい?」
「おまえ、痴漢の姿を見たのか?」
「ええ、見ました。とっつかまえて、警察に突きだします」
「オレも見た。なら大丈夫だな」
「え?」
「逃げられても、だよ」
「ええ――でも、逃がさない。オレが捕まえます。智真理をあいつは!」
「……あまり無理はするなよ」
「ええ。ありがとうございます――あ!」
ライトの中にいきなり、顔を隠す男が。
裏道で迷ったか?
だが確認以前に、憲と平良は勢いあまって、男にぶつかった。
三人はそのまま、数メートルを転げた。
憲は木の幹に胸をぶつけ、口から唾液混じりの息を吐いた。
「うくう……」
それでなんとか止まったのだが、平良と男はさらに下に転がっていった。
憲はライトを求めたが、光は完全に消えていてどこに落ちているかわからない。衝撃で壊れたか、スイッチが切れたか。
憲は起きあがると、歩みだした。
とたん、足裏に激痛が走る。いままで麻痺していた痛みが、急に襲ってきたのだ。
しかし憲はひたすらそれに耐え、下へ下へと降りてゆく。
下では音がしている。おそらく平良と暴漢野郎が争っているのだろうか。
憲は急いだ――が、ふいに音が消えた。
「え?」
憲はあわてて、痛みも忘れて走った。
憲はかろうじて地勢を把握しており、暗がりでもなんとか降りてこられたのだ。
もっとも道がちかくになるに従い、道のところどころに備え付けられている灯りが裏道にもかすかに届いて来た。
まもなくだるまカーブが見えてくる場所だ。
ここは切り通しになっており、その上を裏道が進んでいる。落差は最大九メートルあるので、落ちたらもちろんただでは済まない。
「うーむ……」
憲は段差の上に立ち、あたりを見回した。
誰もいないのか?
憲は嘆息する。
はあ……
そのとき、車のエンジン音が耳に届いた。
切り通しの下――私道を、下から上にあがってくる車だ。そのライトが、憲を照らす。
だが車の運転手には憲は林に紛れて見えないだろう。それよりもカーブの路面に気を取られているはずだ。
憲はカーブを曲がる車の側面を何気なく見た。
「桂川警備保障……あ!」
図書室だ。智真理を救うために近道をしたのだが、扉を開けたので自動で連絡が行き、警備会社が来たのだ。
大事になったな……
まあすでに警察沙汰だから、いまさら取るに足らないことだが。
あ、平良さんを探さないと。
憲が向きを変え、ふたたび降りようとした、そのときであった。
どん。
憲は肩を激しく突かれた。
憲は体の向きを変えている最中だった。
よって横に回りながらバランスを崩した。
背中を下にして、憲は重力に引かれた。
足が、離れる。
土を掴んでいた足が。
憲は見た。
開いた口を。
闇に光る目を。
目は――やった、という達成感の目。
口は、なにか間抜けな感じで半端に開いている。
目とちがい、迷った、ついに取り返しがつかない、あるいは――なんだろう。
わからない。
あ、落ちている。
だるまカーブに向かって。
あの目と口が視界から消えた。
憲の目には星が映った。
一筋の雲があった。
それだけ。
自分の頭から響く音。
智真理!
なにもかもが、消える……
すべて――