あずまんが系ショートストーリーいろいろ。
「なんだ智、こんな誰もいないとこに呼んで」
「たまにはまあ、雰囲気でも出そうと思ってなあ。最近やってないし」
「あ……ああ。そういうことか」
「じゃあいくぞ、プリーズ、キル、ミー」
「……はあ?」
「だから、プリーズ、キル、ミー」
「あのなあ」
「あれ? なにかおかしい?」
ばこん。
「殴ることないだろー!」
「あ、すまん。つい条件反射で」
「あー、よみのせいで雰囲気ぶちこわしだ」
「壊したのはおまえだ! キスミーが正解だろ!」
「あれれ? あはは……めんご」
「死語だゴルァ」
「あ…………よみ……」
「…………」
「…………」
「ふう」
「けっきょく私が逆によみに襲われたってわけかよ」
「なんだとこのバカ。むりやり戻すにはこうするしかないだろ」
「へーいへーい。どうせ私には雰囲気作りは無理ですよーんだ」
「じゃあいくぞ、次の授業がはじまる」
「……なんだかんだ言って、好きなんだよねえ」
「なにか言ったか?」
「いえいえ。なんでもありませーん」
2 ゆかりの野望 (機動戦士ガンダム、ギレンの演説)
……私はアニメの登場機会が漫画より少なかった。これは敗北を意味するのか? 否! 始まりなのだ!
大阪に比べ私の人気は30分の1以下である。にも関わらず諸君らが今日まで私に萌え抜かれてこられたのは何故か! 諸君! 私に萌えることが正義だからだ! これは諸君らが一番知っている。
わたしの車、諸君らが愛してくれたゆかり車は死んだ!! なぜだ!? 諸君は襟を正しこの戦局を打開しなければならぬ。新しいあずまんが大王萌えの覇者を諸君ら選ばれたゆかり萌えが得るは歴史の必然である。
しかしながら大阪板のモグラどもは自分たちがあずまんが大王の支配権を有すると増長し我々に抗戦をする。諸君らの小遣いも、時間も、その女子高生萌えの無思慮な抵抗の前に死んでいったのだ! この悲しみも、怒りも、忘れてはならない! それを……ゆかり車は……自損事故をもって諸君らに示してくれた!
諸君らは今、この怒りを結集し、女子高生萌えにたたきつけて初めて真の勝利を得ることができる!
なにしてるのよー、ゆかりー。はやく警察呼びなさいよー。
先生萌えよ! 悲しみを怒りに変えて立てよ、先生萌えよ!
なにわけのわからないこと言ってるのよー、ゆかりー。
優良萌えたる諸君らこそ、私に新しい車を寄付してくれるのである! ジークゆかり!!!
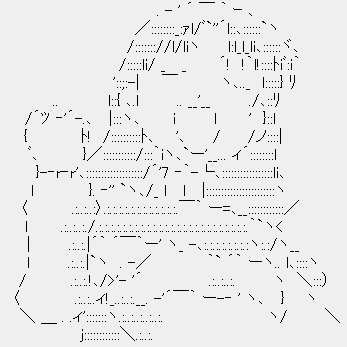
「ちよちゃんの好物はなんだ! フカヒレか?」
「……ミートボール」
「うわ! 子供がいる」
「子供じゃありませんー」
「こっどもー♪ こっどもー♪」
「じゃあ智ちゃんはなにが好き?」
「おっ、私か? ……バナナかな」
「わっ、バカがいる!」
「なんだとよみー。いきなり割り込んで」
「いやだから猿……」
「猿って、ひどいぞよみ! よみも好きなくせに」
「え?」
「バナナに決まってるだろー!」
「あ……おい、待て。そういう意味で言ったのかきさま」
「なんだとー。好きなものだろ! 当然だろ!」
「え? あれ? あの? なに言っているんですか?」
「だからちよちゃん、食べるんじゃなくてー」
「バカ智、大声でいうな周囲が見てる!」
「なんだよー。教えてくれたのよみじゃないか」
「うわーうわー!」
ばこんっ。
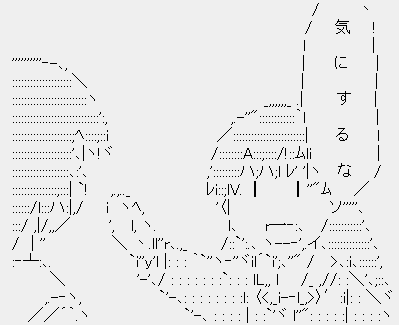
このゆかり車は、駆動系と防水関係しか修理されず乗り継がれてきた、極めて不安定なものである。それは過去の事故でうまれた数多の損傷のために、急遽修復されてきたものだからだ。しかも女子高生萌えの典型であった私の父がゆかり車に対して行った投資はここまでで、入れ物さえ造ればよしとして、彼は財布の紐を閉じ、女子高生ではなくなった私に新車を開放することをしなかったのである。
私の信者が、ゆかり萌えの自治権を大阪板に要求したとき、そのスレッドはにゃも萌えに荒らされた。そしてそのにゃも萌えは先生萌えの宗主を騙り、女子高生萌えに独立戦争を挑んだのである。
その結果は諸君らの知っているとおり、にゃも萌えの敗北に終わった。それはいい。しかしその結果女子高生萌えは増長し、大阪板の内部は腐敗した。みるちーゆかちゃん萌えのような反女子高生運動を生み、先生萌えの残党を騙る木村萌えの跳梁ともなった。
これが、先生萌え難民を生んだ歴史である。
ここに至って私は、人類が今後、絶対に女子高生萌えを繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それが、ゆかり車を大阪板に突っ込ませる作戦の真の目的である。これによって、大阪板の主流である女子高生に心を縛られた人々を粛清する!
諸君! 自らの道を拓くため、難民のためのスレッドを手に入れるために、後一息、諸君らの力を私に貸していていただきたい。
そして私は、新車のもとに召されるであろう!
【知徳】校長です【文武】
1 名前:優しい校長先生 投稿日:1997/9/16(月) 09:30 ID:tesutmas
我が校にもスレッドフロート式掲示板が出来たので、
記念にこのスレッドを立てました。
みなさんが普段思っていることをなんでも打ち明けてください。
2 名前:百合少女 投稿日:2002/12/21(土) 01:58 ID:yrkaorin
どうしてこのスレは5年以上も消えてないんですか?
3 名前:名無しさん 投稿日:2002/12/21(土) 01:59 ID:tomosexa
なんだこのスレ、すげー
4 名前:名無しさん 投稿日:2002/12/21(土) 02:01 ID:???
史上最長の放置プレイを味わった1さんがいるスレはここですか?
5 名前:名無しさん 投稿日:2002/12/21(土) 02:02 ID:???
ていうかもう代替わりしてるだろ(w
6 名前:名無しさん 投稿日:2002/12/21(土) 02:05 ID:osakasan
5年消えんかった理由を私も知りたいですー
7 名前:愛の伝道師 投稿日:2002/12/21(土) 02:10 ID:kimurin7
みなさん夜更かしはいけませんよ、早く寝てください。
このスレッド、よく見つけてきましたね。私も忘れてました。
たしかエンジニアに頼んでシステムに干渉させたのだと思います。
8 名前:6 投稿日:2002/12/21(土) 02:12 ID:osakasan
えこひいきあかんやん
先代の底知れぬ深ーい意地を感じた
9 名前:ダイエット 投稿日:2002/12/21(土) 02:13 ID:55yomi55
毎日毎日、朝昼晩とパソコンに向き合うたび、
がっくりと肩を落とす先代の哀愁を想像して涙が出ます。
爆笑の。
10 名前:名無しさん 投稿日:2002/12/21(土) 02:13 ID:tomosexa
これギネスに申請できねーかw
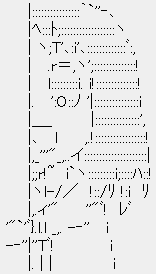
6 狙ってた (アニメ版15話3【原作3巻31P時系列】)
体育祭だー! ゆかりちゃんにジュースを奢って貰うのだ。あー、おまえらなんでもう飲んでるんだー? よみまで! 裏切り者ー。あ、よみの口が、あの缶と触れている。ごくりっ……私はあれになりたい。
私はジュースの缶になりたい。あの小さな小さな、ほとんど誰にも顧みられることのないちいさな缶に。空き缶になれば捨てられ、潰されるだけ。だけど人一倍頑張っているささやかな与えられた役割を黙ってこなす、がんばりやさん――
って、なにブンガクやってんだー! おもいっきりパクリだし。
それはいいとして、ふふふ、あの缶を奪うぜ。これは黒日記。
あー、よみちゃんと間接キッスしたいねん。これはボケ日記。
だ、か、ら、人で遊んでんじゃねーよ貴様! え? なにが貴様かってよく分からないけど、とにかく私はともちゃんなんだー! はあはあ……体の自由を回復しました。ばんざーい、ばんざーい、独立ばんざーい。独立記念に粗品をプレゼントします。どういう粗品かというと、それは強奪能力です。
おおお! 強奪か! そうだ、秘かによみに恋している純情可憐なこの私が、いまの好機を逃すのは人類にとっての大損害なのだー! 私は滝野智、暴走女子高生! いざゆかん暴走の彼方へ、そしてラズベリーヘヴンならぬ百合ヘヴンを建国するのだ。私がイザナギ、よみがイザナミね。やっぱ攻は私じゃなきゃだめでしょう。イメージ的には意外と受も似合いそうだけど……
うーん、ちょっと思い返すと、百合ヘヴン、ってダメダメだねえ。百合って英語でなんていったっけ? 忘れちゃった。よし、下を変えよう。百合天国ー! ゆりてんごく……さすがの私もこれはセンスが悪すぎて受け付けませんねー。
はっ! いけないいけない、さっさと暴走しないと。いまから暴走しまーす! 3、2、1、ゼロ! だー! 奪った! よみの目がつり上がった! あーん、その目がいいのだよチミ。飲むぞ、みーんな飲んでやるぞ。ちよちゃんと大阪が驚いた顔をしてるぞ。でもこれが私の正体なのだー。ふふっ、これからは公然と百合になるしかないのかねー、よみさま?
……あれ? ちよちゃんも大阪も、どちらかというとあきれた顔してるぞ? 衝撃の間接キスを目撃したというのに? どうしてかな? それほど色気ない? あー! 私が物欲――じゃなく、食欲にかられたと思ってるだろ! ちがーうぞ! その目はなんだー! バカだと思ってるだろ! ちがうぞ、いまのは色欲なんだ、崇高な純愛の物語、美しき系譜の1頁(ページ)だったんだ! ……信じてくれよなあ、バカじゃない、バカじゃないぞー。うわあぁぁーん。
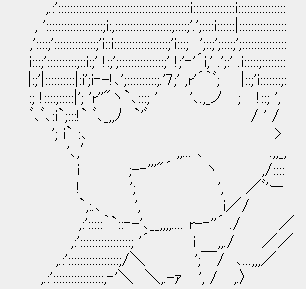
帰ってくると、机になすびが置いてあった。
「こ、これは……」
紙が近くにあった。
『歩も今日で17歳。そろそろいけない遊びを覚えやー。母より』
「おかーちゃん、ひどいわー。これで自慰しろていうんやろ?」
隣にもう一枚紙がおいてある。
「なんやー?」
『なすびとはまだ甘い。これでより高次元の楽しみを味わえ。父』
見ると、そこにかわいい手足の生えたちんぽがいた。
「わーいわーい。入れてー。きみのあそこに入れたいー」
「グロい!」
「大丈夫です。かわいくもなれます」
ちょっと小さくなって毛もなくなった。
「わー。これなら楽そうやー」
「13歳のちんぽです。先ほどは25歳でした」
「13歳のちんぽちゃん、よろしくね」
「わーい」
「ねえー、僕を下に降ろしてー」
「ええでー」
机の上にいるちんぽちゃんを両手で掬うと、興味深そうにふんふんと臭いを嗅いだ。
「ちょっとくさーい」
「それが普通だよー。大丈夫、フェラチオなんかさせないから」
「ふぇら?」
「知らなくていいよ。あれはエロゲーやアダルトビデオの世界のことであって、実際に強要なんかしたら夫婦間でも強姦罪が適用されてしまう危険を含む性行為だからねー」
「よーわからんけど、13歳やのに物知りやねー」
大阪がちんぽを床下に置くと、ちんぽは大阪の真下に歩いて見上げる。
「えっちー」
「ごめんなさい。でもこれをしないと僕はイチモツになれないの」
「え?」
「あなたのすばらしい白い神秘を僕に見せてー」
大阪は白い神秘という言葉にやや安心したのか、押さえていた手を離した。見上げるちんぽの視界には、赤い世界に包まれた白い神秘が広がってきた。
「おおお!神の奇跡よ!勃起ーーー!!!」
ちんぽがむくむくと膨らむ。大阪は目をまんまるとした。
「すごい!立った!」
「そうだよー。これが勃起。これでボクは準備OK」
「私はなにをすればええのん?」
「これから前儀に移るよー」
「前戯てなんやー?」
「大阪ちゃんを性的に興奮させるんだよー」
「興奮てどきどきするやんー」
「ではいくよー。まずはそこに座って」
「こう?」
大阪はその場にぺたんと座った。ちんぽには大阪の白い三角が丸見えである。
「ボクはこの体だから、主に君自身でやってもらうよ」
「それって1人エッチやん」
「ちがうよ。ボクがいるもん」
「それて、智ちゃんが話しとったテレフォンセックスみたいなもんやろか」
「いい友達がいるね」
「でも相手の男の人はマニアや。智ちゃんもまだ処女やねんで」
「君は一足先に女になるんだよ」
「女?私は女やで」
「ちがうよ。きみは女の子だよ」
「女の子……」
「じゃあまず、手をスカートの中に入れて」
「こ、こう?」
「そう。下着の上から、敏感なところを擦る」
「恥ずかしいねん」
最初、なにをしているのかまるでわからなかった。ただちんぽの言うがままに素直に従い、おそるおそる触っていただけなのだ。それが次第に止まらなくなり、ちんぽが言う以上のことを手が勝手に求めるようになってきた。
「……あんあん……ぅんんっ!」
いつのまにか指がパンツをかきわけて直接あそこを触っている。おしっこが出るところの、すこし下にある丸い箇所。そこがいつか男性を受け入れることを知っている。
「大阪ちゃんはエッチだねー。ぼくそこまで言ってないよ」
「ちゃ、ちゃうねん……手が、手が悪いんや」
「大阪ちゃんが求めているということだよ」
「はあ……っ……ぅ……うう。わ……わたしがエッチなん?」
「恥ずかしがらなくていいよ普通だから。見たところ、まだ自慰行為が下手だねえ。経験ないでしょ」
「そないな……必要ないねん……私」
「女の子は男の子ほど性欲必要ないからね。彼氏との間で精神的な幸せを感じられたら肉体関係要らないという子もいる位だし」
「くふっ……ぷらと……にっくって……やつ?」
「聞いたことはあるようだね。そうだよ。それで自慰に戻るけど、この陰裂の上のほうが――」
「あかんちんぽちゃん、見いへんとって!」
大阪はちんぽに自分のすべてを見せていたことを思いだし、足を閉じていやいやと首を振った。
「だめだよ大阪ちゃん。きみは女になりたくないの?」
「お……おんなに……ごめんなさい」
理由もなく謝ってしまう。大阪の悪い癖のひとつだ。
「よし、ゆっくりとまた開いて。そう」
大阪の秘所は年齢からは考えられないほど幼く、陰毛はごくうすくしか生えていなかった。すでに濡れている肉は全体的に淡いピンク色で、まったく新鮮だ。
縦に避けた内側の唇はやや赤みを増してよく湿っており、丸い陰核が裂目の先にちょこんと頭を覗かせている。
ちんぽはその部分を見て興奮したのか、びくんとふくらみ立つ。
「わっ。ちんぽちゃん反り返っとる」
劇的な変化に、大阪は見られている羞恥を一時忘れた。
「ごめん。あまりに可愛かったから」
「かわいい?」
「きみは美しいよ。じつにいい」
「そ、そうなん?」
「だからクリトリスを触るのだ!」
「クリトリス……って?」
「それはここだー」
ちんぽはぽてぽてと走ると、その短い手で大阪の一番感じるかわいい突起、陰核をちょんと撫でた。
「あん♪」
いきなり体の芯を抜けるような快感が走り、思わず叫びに似た嬌声をあげてしまう。
瞬間、愛液が赤い唇の間から愛液が溢れて流れてきた。
「すごい。感じやすいんだ」
ちんぽはさらに幾度か触る。
「え……えっちぃ……いやぁぁぁ……くふぅ」
大阪の体ががくがくと震えだした。頭の中になんとも言えない空白の領域が生まれ、それが急速に膨らんできた。
「あ……あっ……あっ……あ――!!」
体を支えきれずに仰向けに寝てしまった大阪は、脱力感に心地よい疲労を感じていた。
「き、きもちええ……」
「よかったねいまの声。でもまだ飛んではないようだね」
「私羽根なんかないでー」
「エクスタシーを感じてないということだよ」
「ふーん。あー、気持ちよかった。じゃあ私そろそろ」
「だめだよー。これからだよ本番は」
「本番?」
「ぼくを入れる」
「……それが私のに入るの?痛かないのん?」
「入るよー。処女膜を破らないような特別製だから大丈夫」
「でもはじめては痛いて聞いたで。どないな仕組みや。それにだいたい、あんただけじゃふんばれへんやん。私があんた掴んで入れるん?」
「それじゃあただの男性器の張り子だよー。ボクは発明品なんだ。画期的な、最高の大人のおもちゃなんだよ。天才が発明した」
「まさか……」
ぴんぽーん。
「やばっ。人が」
「大丈夫だよ。来たんだよ」
「へ?」
玄関の扉が開く音がした。
「大阪さーん。首尾はどうですかー?」
「この声は――」
そして部屋に入ってきたのは、幼い同級生だった。
「ちよちゃん!」
「試していましたねー」
ちよは大阪の乱れた服を見ても意に介さず、むしろ顔をほのかに染めて興味深そうに近寄ってきた。
「まいど」
ちんぽの挨拶に平気に手を返すちよ。
「まいど。イカせた?」
「むりですよー。だからご主人さまが来たんでしょう?」
「その通りです。それでは、装着!」
ちよが叫ぶや、ちんぽがぴょんと飛んでちよの股間に収まった。
「合体!」
「合体て、ちよちゃん服着たまま……おかしいねん」
「脱ぎますです」
ちよは天才なので、ちんぽをつけたままでも脱げました。
全裸になったちよは、反り立った13歳のちんぽをびんびんに揺らした。
「ちょっとアンバランスですねー。11歳になってー」
「へーい!縮小ー!」
ちんぽは11歳サイズになった。
「それでもまだ大きいー」
「痛くないですよー。処女膜だけ空間ワープして挿入できる最強の自慰システムを開発してますから」
「そうなん……私、はじめてを好きな男の人のために取っておけるんか」
「そうですよー。さあ、今は私のものになってください」
「……そのちんぽ、射精はどうなん?」
「しますよ。でも本物ではないです。そこまで再現できませんよー」
大阪は逡巡していたが、ちよちゃんの熱心な視線と安全という説明に負け、閉じていた股間をゆっくりと開いた。
「うわー。5分ほどなにもしていなかったのに、まだまだパンツ、濡れたまんまだよー」
「じゃ、脱がしますねー」
ちよちゃんは大阪のパンツをそっと脱がした。
「くすぐったいねん」
ちよはさらに大阪のスカートを脱がし、上の制服もスローモーションのようにゆっくりと脱がしてゆく。脱がしながら体中を愛撫してゆく。気持ちよさに大阪はなすがままにされていた。
やがてブラジャーも取られ、2人は全裸となった。ただちよの股間にはずっと反り立ったままのちんぽがやあと手を振っている。
「……手足、生えたまんまでおかしいねん」
「かわいいでしょ。触ってみる?」
大阪は黙って頷き、ちんぽの棒の根本をそっと掴んでみた。
「あん♪」
「わーい」
「え?なんでちよちゃんまで」
「連動してるんですー」
「ですー」
「……へー。じゃ、仕返ししてやるでー。ほらっほらっ」
大阪はちんぽの袋の部分を揉んでみた。棒も擦ってみる。
「わ、わ、いきなり上手ですー」
「うへ……お、大阪さん……いきなりこれは……」
「わはははは……ひくひくしとる……おもろいわー……」
「お……大阪さん……ちょっと激しすぎます」
大阪はちんぽの棒を激しく上下に擦る。すると皮がつるりと剥けて未使用のきれいな鬼頭があらわになった。その先端から、つつーっと透明な液が流れ出す。それが大阪の手にかかった。
「わっ。ちんぽも濡れるんか。私とおなじやー」
「ああ……これが……S余話するときに互いの性器を守るための……」
「もう授業はええねん。なるほど、だからちよちゃんの発明やったんやなー。かしこいわけやー」
「でも……ぼく……知ってるだけで……はじめて……」
「わ……私も……で――――」
いきなりちよがしゃべれなくなった。体全体でなにかを我慢しているうようだ。
「どうしたんー?」
大阪は激しくちんぽの棒を上下させている。ちよとちんぽが気持ち良くてワレを半分忘れてるさまを見て、自身も興奮しているのだ。この先さらにちよがどうなるか好奇心がでて、動かす手にさらに力がこもる。開いたもう一方の手で自慰も開始した。
「あん……あ……ん……くふ…………」
「…………ん…………う…………」
しばらく卑猥な音とあえぎ声がが部屋に籠もった。しかしそれはある一言によって突然の終焉を迎える。
「もうだめー!」
と、大阪の手にちんぽの棒がいきなり膨らんだように感じられた。
ちんぽがびくんと痙攣するや、その先から白い液体が大量に発射された。
「うわぁ」
いきなりのことに、大阪は驚いてちんぽを握る手を離してしまった。
疑似精液は大阪の顔におもいっきりかかった。
ちよは力なくその場で腰砕け、はあはあと深呼吸している。
「すごい……これが射精」
大阪は興奮に任せてその白いものを舐めようとしたが、ちよが止めた。
「お、大阪さん――だめです。それは、将来出来る好きな人のために」
「……そうなん?」
「私は天才ですから、味まで本物を再現してます。だから、今はまだ」
「どういう味なんやー」
「だめですよー」
ちよの説得で大阪は精液を舐めるのをあきらめ、とりあえずふき取るとまだぐったりしているちよの前に座り込んだ。
「ちよちゃん、挿れて」
「え……あの」
「だって、ちんぽくん大丈夫て」
「はい。大丈夫ですよ」
ちんぽが言った。
果てた。
もうひとかけらの力もない。
全身の筋肉からすべてのエネルギーが抜けてしまい、疲労しか感じない。その疲れはじつに心地よいものだ。
労働の汗というが、それに近いものだろうか――
しかし――
股間の先でそそり立っているそれは、まだまだ動いている。振動している。いや、動いているのはそれを受け入れている側のほうだ。
「……大阪さん、まだやるんですか?」
「…………」
大阪は声を発しない。ただひたすら自分の高ぶる本能のままに、ちよの下で腰をゆっくりと扇動させるだけだ。大阪の胸に正常体で被さっている格好のちよには、彼女の鼓動をはっきりと感じる。そのお世辞にもあるとは言えない胸が、まだまだ興奮を示して小刻みに揺れているのだ。その振動はダイレクトにちよにも伝わり、体力を使い果たした全身の細胞を刺激してゆく。そのマッサージにも似た動きによって、ちよは水がしみ出すように体力が回復してゆくのを感じていた。
「大阪さん……」
「お、女の子同士のはやな、エンドレスなんやで」
大阪の言葉はそれだけだった。ふたたび黙った彼女は、ちよの股間についているそれを攻めだしたのだ。それはすでに男根としての宿命か、意識を失ってしまっている。しかしぶらぶらとしている楊枝のような手足を除けば、まだその本体はちよの血を吸って充血し、11歳のものとは思えぬほど立派にそそり立って大阪の膣に収まっているのであった。異空間を経由して処女膜を傷つけない特殊機能もなお健在で、すでに4回の射精を行っているとは信じられない元気ぶりだった。
実際の男性でここまで行くと、カウパー線が悲鳴を挙げて痛みを伴うだろう。そうなるともはやS余話どころではなくなるのだ……
「エンドレス……うん」
ちよのイチモツは、女性器が持つ高い耐久性を獲得しているようだ。ちよ自身それほど強力だとは思わなかった。そのイチモツと、そして大阪のちよを求める肉欲とが合わさっている。
後は、ひたすら果てるまで、いけるまでやるのみだ。ちよは覚悟を決め、5回目の律動を開始した。いや、すでにはじめていた。ちよの頭で考えが追いつくのに時間を要したのである。大阪はひたすら小声で喘ぎ、あえて大声をあげるのを我慢しているように思えてならない。
大阪の性格からしてそれが出来ないことはわかっているが、ちよは大阪が自分の行為に恥じらいを覚えて我慢していると錯覚したそのものに男性のように興奮し、その錯覚を事実のものにしようとさらに大阪を責め立てる。その行為に大阪は声では応えてはくれないが、行動では示してくれた。具体的にはシーツを掴む両手に力がこもり、開いた股で遊ぶ両足をちよの腰に激しく絡ませて、さらに結合を強くしようとするのだ。ちよの動きはさらに速くなる。
大阪はけっして声を荒げない。それが大阪の感じ方だ。
彼女はその平静のペースを情事でも維持するのである。
そのかわいらしさがちよの征服欲を掻き立てる。なんとしてでも、大声で言わせてみせよう。
「え……ええねん」
大阪が、そうちいさく言って足をひくひくと揺らせた。
「ええねんーーー!!!」
そしてまた、弾けた。
「……あ……ああ……」
ちよの腰ががくがくと揺れ、大阪の絶頂にやや遅れて欲望を解き放つ。いや、解き放つ真似をした。すでにそのものはちんぽくんの生産力が追いつかない。あくまで精神的な解放にすぎなかった。それでも大阪にとってもちよにとってもどうでもよかった。ただ結合して飛んだことが証でありすべてであった――
そして眠れない夜は、つづく……
「あ、なすびなんかに使えやろかー」
大阪は母親が置いていったなすびを持ってきた。
「え……」
その顔にはなにかちよにとって嫌なことを思いついた笑いで溢れていた。
「あの、大阪さん?」
「ちよちゃん、これからは百合のお時間や」
「い、いやあ、大阪さーん!!」
今日も今日とてダンジョンに乗り込む。
前衛
さかき(サムライ)
かぐら(ファイター)
後衛
ちよ(ロード)
とも(シーフ)
よみ(魔法使い)
おおさか(ビショップ)
「これではバランスが悪いですー。私、前衛やりますよー」
とちよちゃんが言ったが、榊が一言。
「……スライム、倒せるのか?」
さっそく、目の前にスライムが現れた。
ぷるぷるしている。
「き、きみが悪いですー」
ちよちゃんはトテテテと走ってさかきさんの後ろに隠れた。
「へへーんだ。こんなもの、私なら倒せるもんねー」
ともがちよにあかんべーした。
「そうか、じゃあおまえが前衛3人目決定な」
「へ……?」
神楽の言葉に、顔を青ざめるともちゃんであった。
つぎの戦闘では、レベル3ファイターさんが5人だ。
「うわわーん」
ともちゃんは泣く泣く逃げ回っていた。
戦闘後――
「うえーんうえーん、やはりシーフに前衛は無理だよー」
「まったく役立たずだなあ」
神楽をはじめ、皆呆れている。
「宝箱開けられるもん」
ともは宝箱を調べた。
「罠は石つぶて!」
思いっきりあけたら、矢が飛んで額にぶすり。
「…………」
ともは死んだ。
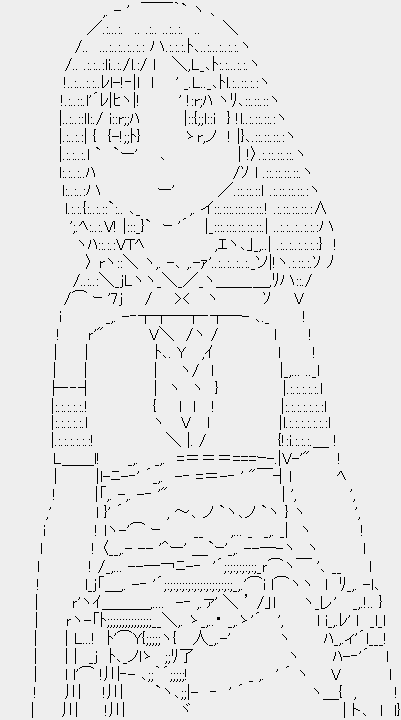
今日も今日とてダンジョンに乗り込む。
友好的な敵があらわれた。
「このパーティーは善が多いから、見逃しましょう」
リーダーであるちよが言って、全員立ち去った。
するとともが突然泣きだした。
「ああ、私はいままでなんと罪深い悪人だったんでしょう」
両手を胸元に抱いて、なにかに祈りだした。
「どうしたんやー、ともちゃーん」
「ごめんなさい大阪さん。あなたの下着を盗んだのは私です。お金が欲しくてついエロオヤジに売ってしまったんです」
「えー。そないやったんか。別にええで、わたし心が広いねん。どのくらいかとゆーと、このダンジョンくらい」
「びみょーに狭い心ですね」
「ゾンビとかも棲んでるねん」
「いやな心ですね」
ともがおかしくなっている。
「どうしたんだとも、いきなり敬語なんか」
「よみさんすいません。この4年で私、寝てるよみさんに105回もキスしました。好きですから……」
「なーーー!!」
ともは次々に自分の悪事を明かし、懺悔を続けた。
「もしかして……性格が善になってしまったんでしょうか?」
ちよはやっと気付いた。友好的な敵を見逃しつづけたら、悪の性格が善になることがある。善が悪になるには逆のことをすればよい。
「それにしても、極端だなー」
神楽があきれたように言った。
「反動ですね」
「ま、いいか」
しかし問題だらけだ。
「ごめんなさいマーフィーズゴーストさん。あなたをもう狩りません」
とか言って経験値稼ぎの部屋にトラップを仕掛けて立入禁止にしたり、
「あなたは飢えてますね。はい、私の経験値をあげます」
とヴァンパイアのエナジードレインをわざと食らったり、
「榊さんだめですよ。このかわいいうさぎを殺したら――ぎゃあ」
とポーパルバニーを庇ってあっさり首を刎ねられたり。その生き返す金がけっこう負担が大きかったり。
「この宝箱はこの人のものです。一緒に埋めてあげましょう」
宝箱の一切の罠解きを拒否し、戦闘のたびに埋葬する始末。
「これでは……冒険になりません」
3日我慢して、ついに我慢は限界に達した。
「ここに魔法がかかった短刀があります」
ちよはボルタック商店でぼったくられた1本の短刀を示した。
「これをともちゃん、使ってください」
「使うんですか?」
「はい。掲げてください」
「わかりました」
智の体が光った。光が止むと服装が和風になっていた。
「……私、なにか生まれ変わったようです」
「忍者になりました」
「忍者?」
「悪にならないといけません」
「悪!悪!悪!」
「そうです。悪です」
「悪ーーーー!!」
智ちゃんはいきなり目を尖らせると、1人でダンジョンに突入していった。
「あれでよかったのか?」
神楽が聞いてきた。
「大丈夫です」
しかし智ちゃんは帰ってこない。
やがてダンジョンの最下層で凶悪な女忍者の噂がたちはじめた。
「……モンスターになっちゃいましたね」
「つくづく極端なやつだなあ」
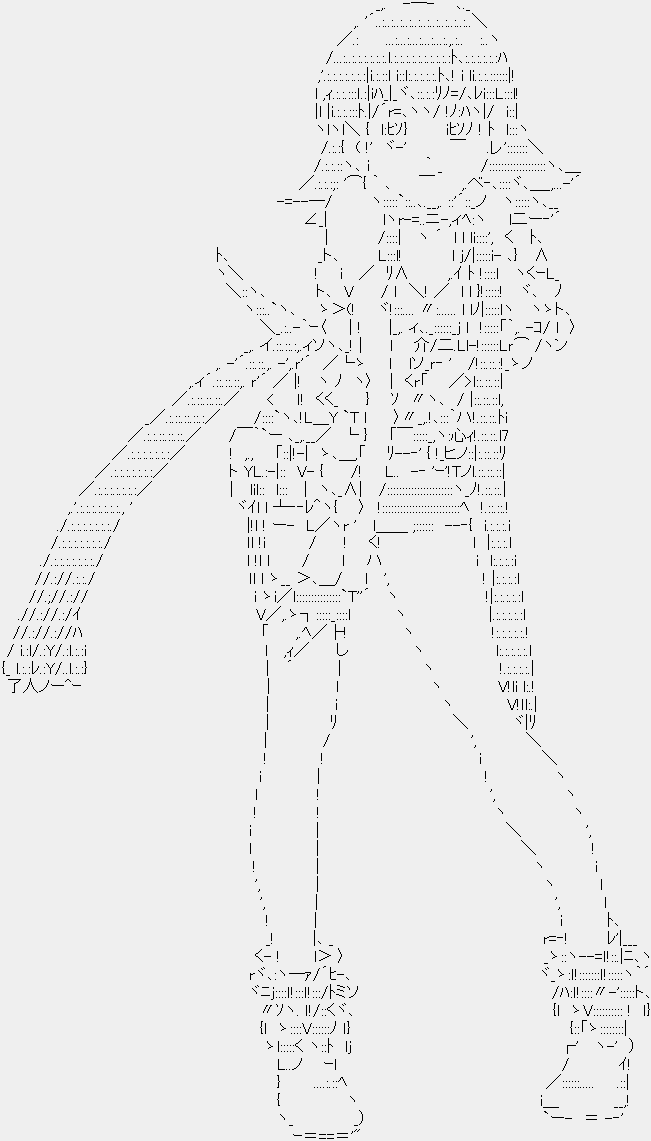
アメリカ・カリフォルニア。
こちらの生活も3ヶ月がすぎ、だいぶ慣れてきた。今日はルームメイトのナタリーと一緒にBONSAIを見に行った。屋外展示で、自然公園にある広場の一角が会場になっている。BONSAIとはまさに盆栽そのものだが、アメリカの盆栽は日本の文字通りではなく、多少アレンジされている。
「ファンタスティック!見て見てチヨ、これはいい枝振りだわ。まるであんたのツインテールみたい」
「……そうですね。たしかに個性的な枝ぶりだと思います」
「だめよチヨ。あんたまた本心隠してるね。本音言ってヨ」
日本人的な気配りは、ナタリーには通用しない。私が感情を隠すのが下手なせいかもしれないけど……
「えと……日本の愛好家に見せたらハサミで根本から切られそう」
「あはは!日本人にはこのすばらしさがわからないね。こちらは?」
「クリスマスツリー……」
これはまた個性的だ。漫画に出てくるような簡略化されたクリスマスツリーの形そのままに固めてある。
「そしてこれもいいねー」
「う……」
「どうしたの?すばらしいねー」
「版権どうなってるんでしょうか。厳しいんでしょ?」
それはずばりミッ○ーマ○スだった。
「これのどこが盆栽なんでしょう?」
「OH!BONSAIはBONSAIね」
「まあいいです。どうせ私の感性は日本人の枠から抜け出せないです」
「あ、拗ねてる。かわいいネー――あ、ビルー!」
ナタリーは知り合いを見つけて話をはじめた。まったくアメリカ人の感性はなかなかに飛び跳ねている。ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ね回り~~だ。
私はすこし疲れて近くのベンチに座った。
「暑いー」
日本語で言って、両足をぶらぶらさせる。麦藁帽子を深く被り、背伸びをしてぼーっとした。
アメリカ人とつき合うと、すぐに日本の文化について言ってくる。ヘルシーな食事だったり、禅や空手だったり、アニメだったり。彼らの理解は妙にずれていておもしろい。もっとも私とてアメリカを理解してはいなかった。それは実際にアメリカに住んでみてはじめてわかったことだ。
日本から離れてかえって、日本についていろいろと考える。そんな機会がとても多い。そして今日もそれだ。私はそんなとき、ふと一番大事な友達たちのことを思い出す。
どうしているだろう……
大阪さん、榊さん、暦さん、智ちゃん、神楽さん、かおりんさん――
「わん」
「忠吉さん、榊さんを覚えていますか?」
そこにいたのは、知らない犬だった。
「あ……」
飼い主は、茶髪の男の子。
「ごめんなさい、そういえば今日は忠吉さん連れてきてなかったんですね。あ、忠吉さんというのは」
「日本語、わからないです」
「う」
つい日本語でまくしたてていた。
「どうして日本語ってわかったんですか?」
「僕のお父さん、日本人です。混血」
そういえばアジア人っぽい部分もある。少年は私を見て言った。
「君は日本人?」
「うん。そうです」
「どこに住んでいるの?」
「サクラメノ(サクラメント)ですよ」
「あそこはSAKURAがきれいですね」
少年は「さくら」だけ日本語的に平坦に発音した。
「……それって、冗談かなにかですか?」
「英語の話せる日本人にこのジョークは受けるって教わったんですけど」
「誰から?」
「お父さんから」
「それはオヤジギャグというんですよ。日本では嫌われます」
「不思議ですね。ジョークはまず笑わないと失礼です」
「他民族国家ですからコミュニケーションを円滑にするためにはね」
「日本には日本人しかいないって本当ですか?」
「え……」
「不思議な国です。みんな同じ。それはどういう感じなのでしょう。僕、そういうのは想像も出来ません」
なかなかにおもしろいことを聞いてきたので、興味が湧いてきた。
「そういうの私、あまり考えたことないです」
「よければ日本のこと、教えてください。お父さんは帰化してるので、日本語もしゃべってくれないし、日本のこともあまり教えてくれません」
それはなにかがあったのでは?とふと思ったが、私はうなずいた。
「いいですよ。私は美浜ちよです。あなたは?」
「僕はレンディックストカックス・ミヤサカ・ガイルです。通称レン」
「長い名前ですね……」
「僕もジュニアスクールに上がるまで覚えられませんでした」
「どうして覚えたの?」
「だって、名前書けないと格好悪いじゃないか」
私とレンは、数秒見つめ合って同時に笑った。
その日から私とレンとは友達になった。
彼は私とおなじ12歳で、ごく普通の子供だった。私は自分が大学生であることをなんとなく隠して彼とつきあった。彼には日本人学校に行っていると言った。まさか1人暮らしだとは知らないだろう――なぜだろう。私は彼にだけは自分の「正体」を隠したがっていた。どうしてだろう。私は彼と会うことが楽しみになっていた。
ある日レンが死亡した。
「なんだと!」
私はレンの死体を掘り起こして食べた。
「うまい!」
レンはじつはジョンレノンだった。
「うっしっし」
……ごめん、飽きた。
今日も今日とてダンジョンに乗り込む。
ともちゃんが宝箱を開くと、奇妙な棒が入っていた。それを手にとって不思議がるは大阪である。
「なんやこれー?」
「大阪さん、ビショップなんですから鑑定してください」
「わくわく。マジックアイテムだったら高値が付くぞー。今夜はスイートルームだー」
「おお! 焼き肉だ。焼き肉定食!」
「定食じゃねえ。焼き肉そのものだぞー」
「おお。焼き肉か!」
「焼き肉だー!」
ともと神楽がバカみたいに叫んでいるが、それを無視して鑑定はつづく。
「大阪さん、なんでしょう」
「これは……」
大阪は首を振った。
「この棒、わからへんねん」
「え?」
「とりあえず仮名称、『奇妙なもの』にしよっ」
大阪はその見かけに反し、1回だけだが最強の魔法・ティルトウェイトを唱えるほどの実力者だ。そう簡単に鑑定に失敗するはずがない。
「これはもしかして、よほどの品物なんでしょうか」
「ちよちゃーん、ぼったくる商店で鑑定してもらおー」
「だめだ! それはだめだ! 鑑定料が買値とおなじだ! 意味ねー!」
「そうだぞ大阪、なにしろ焼き肉なんだからな」
つまり大阪が自力で鑑定しない限り、焼き肉にはありつけないわけだ。
「焼き肉なんか、その辺のモンスター焼いたらええやん」
大阪が指さした先では、よみと榊がファイヤードラゴンの死体を焼いて食べていた。このドラゴン、帽子の入っていた宝箱を守っていたやつだ。
「いやだー。牛がいいのー。神戸牛!」
「そうだ、霜降りの高級和牛じゃないといやー」
ダダをこねる2人である。
「なんだなんだー?」
よみが騒ぎを聞きつけてやってきた。
「焼き肉がどうしたって? 次の戦いに備えるため、食えよほら」
美味しそうな匂いを発している串肉を出され、ともの口から一瞬涎が垂れた。が、それを掃除機のように吸い上げると、両手でNOのサイン。
「牛なんてダンジョンにいないもん。だから牛の焼き肉食べられないもん」
完全に幼児と化し、3頭身で通路を転がる。
「じゃあ牛を倒して食べたらええんやないのん?」
「それだ!! よし神楽、行くぞー!」
「おー! 牛退治だー!」
神楽とともはダッシュしてダンジョンの出入り口の方向に消えていった。
「まあともと神楽のアホはほっといて、4人で経験値稼ごうぜ」
「そうですね」
さりげなくちよちゃんも黒い。
「うーん。結局この棒、なんなんやろー。なんや榊ちゃん」
「……ちょっと貸して」
「ええよ」
大阪は榊に棒を渡した。
「――これは、たぶん」
そのときだ! 敵が現れた!
「わっ! いきなりです」
不確定名『やまねこ』
「キター!」
榊は目の色を変えて走りだした。
「だめですよ、また首を刎ねられます!」
榊は奇妙な棒を振り上げた。
それは7回やまねこにヒット。1ダメージを与えた。
「武器としてもぜんぜんだめじゃないですかこの棒」
やまねこは仲魔になった。
「なんでですー!」
「女神だ。女神転生だぞちよちゃん」
「……わかった! あれ猫じゃらしや」
「なんですかそれ?」
「東洋の神秘やねん。猫を手懐けるスペシャルアイテムや」
なまえをつけてください。
「マヤー……この子は、マヤーにしよう」
イリオモテヤマネコのマヤーが仲間になりました。
「うわ、この子、いきなりHP1000近くもあるよ」
「戦わなくてよかった……」
4人と1匹が地上に戻ると、2人が賞金首になっていた。
「そりゃ、そうやんなー」
「それでこのSSのオチってなんなんでしょうか」
12 祭り (よつばとひっこし【よつばと!1話】)
とーちゃんに連れられて面白いところに来た。家がたくさんある、人がいっぱいいる。
「今日は祭りか!」
「学校だ」
あんなに人がいて学校か? どういう学校だ?
祭りだな、祭りだ。
ジャンボがいた。働かないらしい。よつばが働いてやる。
私がえらいとお父ちゃんはダメだそうだ。
祭りの音頭はジャンボが取るのか?
私は踊りたいぞ。踊らせてくれ。
……働くのは意外と面白くないな。私は踊りたいぞ。
お、ちょうちょだ。このちょうちょは私に捕まるために生まれたのだ。
ちょうちょちょうちょ。
ここはどこだ? 変なところだな。妙なものがいっぱいある。これは知ってるぞ。砂場だ。囲われているな。なんだこの鎖の下にあるものは(注:ブランコ)。そうだ、きっとこれが祭りに使うものだ。今日の祭りは面白くなりそうだな。回してみる、揺らしてみる、押してみる。
ガン。
…………。顔に当たったぞ、痛い……これがここの祭りなのか? 痛い祭りだ。
.
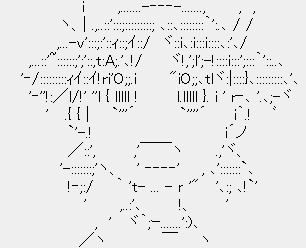
13 革命 (原作3巻151P+ウィーザードリィ)
今日も今日とてダンジョンに乗り込む。
智が変な防御方法を考案した。
「回転防御だ」
すなわち敵が剣や爪を突きだしてきたら、回転することで力を受け流すというのだ。
「……そんなの不可に決まっとるだろ」
暦が皆の決を採って即座に不採用にしようとしたが、忍者の智は食い下がる。
「前衛の苦労は後衛にはわかるまいて」
榊(サムライ)と神楽(ファイター)がうんうんと頷く。
「まずは実戦で確かめないとね」
そしてモニターは智に決まった。
「なんでー! 榊も神楽も賛成したくせにー」
「いやだよー。死ぬのは」
「それとこれとは……話がちがう」
「いいもん、私が回転防御の有効性を実証してやるんだ。見てろよ、戦闘に革命を起こしてやる」
敵が現れた! ストーンゴーレム。
「よし、回転防御発動!」
くるくるくるくる。
ストーンゴーレムは両拳をひとつにまとめ、智の頭上に振り上げた。
影で覆われた智の顔が、見る見る青ざめる。
「え? あの、振り下ろし? えと……頼みますから、突いてくれないと……」
くるくるくるくる。
ぷち。
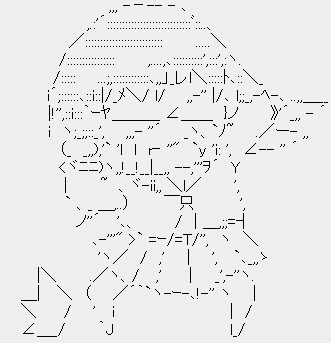
さあ、今こそ純愛を語るときだ!
「……よ、よみ。あの、手が」
「なんだい智。私の手が、どうかしたのかなー?」
「あの、さっきから、私の……あの」
「赤い顔をして、変な声まで出してるねー。だめな子だねえ智は」
「ふくぅ――よ、よみ……」
「なんだい? もう止めるのかい?」
「……いや、まだ、つづけて」
「かわいいねえ智は」
すばらしい純愛だ。
それを見ていたちよちゃんの顔は真っ赤だ。
「百合、百合、百合、ユリゲラー」
などと20歳以下にはちんぷんかんぷんなことを言ってその場を去る。
「わたし、彼氏が欲しい……」
よかった、百合の道には興味がないようだ。
「まずは男を狩らないと」
家に帰ったちよちゃんは、部屋に閉じこもって巨大な網を作り始めた。
……正直、なにかがちがうと思う。
大山がかかった。
「……いらん」
大山は捨てられた。
木村がかかった。
「これはこれで!」
「……いらん」
木村は埋められた。
ちよ父がかかった。
「赤いものが……」
「……いらん」
ちよ父は燃やされた。
石原先生がかかった。
「ちよちゃんそのうち2メートルこえるぞ!」
「ありがとうございます。でも……いらん」
石原先生はマヤーにかじられた。
もう誰もかからない。
「……屋上に」
屋上で後輩がかかった。
「ああ、春日先輩助けて!」
春日歩のボケ日記スレに出てくる「大阪の年下な彼氏」だ。
「……かわいい」
気に入ったようだ!
「やいおまえ、私のものになれ」
もはや黒ちよと化した彼女に、青少年は逆らえないのか!
少年は諭すように言った。
「そんなことをしてはだめですよ、先輩」
「な、なんだ……」
「君は恋に恋してるんだ。これは愛ではないよ」
言ってることは真面目だが、網にかかって逆さ吊りなので格好が付かないぞ。
「……うーん。わかった。まだ私には彼氏は早いね」
しかしちよは納得してその場を去った。
少年は自分の貞操を守ったのだ! 少年に平和が訪れた。
しかし――
「……あのー。助けて?」
そうなのだ! ずっと逆さ吊りなのだ!
「……なにしとるん?」
昼になって大阪が買ってきたパンを持って屋上にあがってきた。
「ああ、先輩。じつは……――」
説明を聞いた後、大阪はにやりと微笑んだ。
「それはそれでええねん。ふふふ。動けないね明智くん」
「げ」
大阪の目が座っている。
「いたずらターイム!」
「あわわわわ、せ、せんぱーい……」
……彼は散々弄ばれたそうな。なんまいだ、なんまいだ。

9月のある日、みんなでちよちゃん家にお泊まり会をしたときだ。
「じゃーん、お酒~~!」
智が酒を出して来た!
「おまえなあ……」
あきれ顔のよみであるが、止めようはしていない。
夏の合宿で先生に取られた記憶が生々しいからだ。
たちまち酒盛りとなり、やがて――
「やいやいメガネ、よくもこの私にさけなんか飲ませやがったなあおい」
「え……ちよちゃん、あの? 酔ってる?」
「けっ。私は天下のちよ様だぜ、酔うわけねーだろ。ひっく」
「うわー、ちよちゃん性格変わってしもた」
「ちよちゃんが怖いよー。神楽頼む」
「なんですかー?」
「うわ私を仕掛けるな智。あっちいけちよちゃん」
「なんだとー? がるるるるる」
「……逃げろー!」
みんな逃げ出した。
後にのこるは、よみとちよ。
「なあジャイアン」
「じゃ、ジャイアン?」
「うるせー」
がこん。
「あう」
「ふふふ、どうやって苛めてやろうか」
「な、なあちよちゃん?」
「あんだ、デブメガネ」
「…………。あ、お父さんが飛んでる」
「…………」
「…………」
よみの額から、汗が一筋。
「ふっ、そんな罠に引っかかるちよさまじゃないぜ。涙のダイエット少女」
「な、なぜそれを知ってる!」
「私がおまえらのなにも知らないとでも思ってるのか? 私は本当はすばらしい天才なんだぞ、ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ」
目が完全に座っている。
「……許せちよちゃん」
よみは必殺技を使った!
「目からビーム!」
よみよみよみよみ~~~~~~~~!!!!!!!!!!
よみは黒こげになった。
「な、なんで……」
「甘いな、ビームは鏡で跳ね返せるんだぜ」
「それはレーザー……」
「――そうか? まあいいや。あー、房がすこし焦げたぜ」
『なんやっちゅーねん』
ビーム? を跳ね返したのは、鏡面処理されたぴかぴかのツインテ-ルだった。
『なあなあボス』
「なんだおまえら」
『正体を知られたからには、このメス、生かしてられませんぜ』
「そうだな」
「な、なんだよ――」
よみは恐怖を顔面に貼り付け、おずおずと後ずさりした。助けを呼ぼうとしても、うまく口が開かない。
「ふふふ、メガネ、死ぬがよい」
「喰らえ、ちよハリケー――」
そのときだった!
「ちよちゃん助けたる!」
大阪がちよのツインテールを掴んで離したのだ。
「――……ん?」
ぱたり。
ちよはエネルギーを失って気を失った。
「た、助かった……」
よみは胸をなで下ろして大阪に礼をした。
しかしついまちがってしまった。
よみよみよみよみ~~~~~~。
「いややー!」
ああ! 大阪が黒こげに!
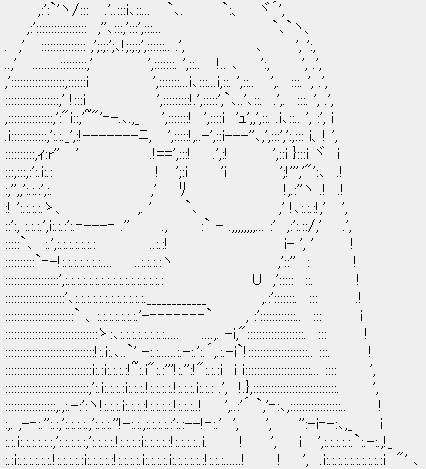
*なんとなく小咄。
ゲーテは死の床にあった。
「なにか言いたいことがあるんですかゲーテさん」
「み、見えない……ひ、ひかり」
「おい、そこの君、窓を開けたまえ」
「わかりましたお医者様」
少女は窓に向かった。
うっすらとした、柔らかい光が部屋を覆う。
「おおおおお」
ゲーテの顔に、涙が一筋。
「見えぬ」
「どうしたんですか、ゲーテさん」
「もっと……明かりを」
「窓は開いていますよ!」
「見えぬ、私には、もう……」
そして天井を見つめ、つぶやいた。
「もっと光を……」
がく。
文豪、最後の瞬間であった。
「……聞いたか?」
「はい、しっかりと聞きました」
付き添いの少女はハンカチで目を覆っている。
「最後の一言を、皆に伝えよう」
「……はい」
こうして「もっと光を!」の名言が生まれた。
*そして意味もなくあずまんがSS化。
キムリンは死の床にあった。
「なにか言いたいことがあるんですかキムリンさん」
「み、見えない……ひ、ひかり」
「おい、そこの君、窓を開けたまえ」
「わかりましたお医者様」
少女――いや、ちよちゃんが窓に向かった。
「い、いや。お、おいしゃ様が……」
「え? 私が開けるんですか」
ちよちゃんは元の位置に座り、医者が窓を開けた。
うっすらとした、柔らかい光が部屋を覆う。
「おおおおお」
キムリンの顔に、涙が一筋。
「見えぬ」
「どうしたんです、キムリンさん」
医者が慌ててキムリンに駆け寄るが、彼は抵抗する。
「もっと光を!」
「窓は開いていますよ!」
キムリンは医者を押しのけ、医者の裏に隠れていたちよちゃんを見た。
「おお! 光だ!」
そして天井を見つめ、つぶやいた。
「もっとパンチラを……」
がく。
稀代の助平、最後の瞬間であった。
「……聞いたか?」
「はい、しっかりと聞きました」
付き添いのちよちゃんはスカートをしっかりと抑えている。
「最後の一言は、なかったことにしよう」
「……はい」
「最後の言葉は、あれだ」
「……はい」
こうして「もっと光を!」の迷言が生まれた。
大阪は急にプロレスが見たくなった。
「ちよちゃん、猪木見にいこー」
「いいですよー」
猪木は強かった。
「猪木ボンバイエ~~やねん」
「ボンバイエーー」
「ただいまー」
玄関のドアを開くと同時に、カレーの匂いが大阪の鼻腔をくすぐった。
母親が台所から顔を覗かせる。
「歩、今日の夕御飯はおつ――」
「待ってお母ちゃん。まさかお疲れーて言うんちゃう?」
「……なに言っとるねん歩、いくらなんでもそれはないねんよ」
「…………」
「…………」
「お母ちゃん、汗いっぱい出とるで」
「……鋭くなって来たんやなー」
「ふっ、私は猪木を見て感覚が高まったんや。もう無敵やで」
「そう。ところで今日は、ボンカレーやで」
「ぼん?」
「そうや、ボンカレーゴールド、甘口」
「ゴールド! 甘口! ぼん!」
大阪はそわそわを抑えきれず、靴を脱ぎ捨てて台所にかけこむ。
いい香りが部屋に広がっていた。
「ぼん! ぼん……ぼんばいえーごーるど!」
「うふふ、まだまだやね歩」
後方の視線に、大阪は固まった。
「他にもあるで。ほれ、サーターアンダギーに、チャンプル」
「ちゃ、ちゃんぷるー! さーたーあんだぎー!」
「あら歩、どうして涙を流しとるんやー? ふふふ」
「な、なんで口が勝手に……」
「可愛いわね。はい、ボンカレー」
「いのきぼんばいえー!」
神は死んだのか!まったく貴様ら、一時の快
楽のためだけに俺様が敬愛してやまない神楽
タンの妄想画像を欲しいなど下劣トンチンカ
ン抜かしおって!神楽タン様の裸体は、俺様
の写真にすら一枚としてないのだ。その通り、
エロ画像はあくまで画像であって、目で見て
ロでしゃぶり、耳を当て、どこから調べても
画でしかない。本物の神楽タンではない。映
像のパンチラなら持っているが、貴様ら色情
キ○ガイには決してやるものか――俺様のが
ボッキしてきた。神楽タンの家の前に昨日ウ
ンコをし神楽タンの愛をゲットした。カップ
ヌードルをすすって今日もウンコをする。
19 六輝六曜 (創作+ひめくりあずまんが2003・11月23日友引)
・友引
「なーなー智ちゃん、今日は友引なんやでー」
「それでなんだ大阪?」
「智ちゃん引くんやー」
「うわー! ともびきだ!」
「そうなんや、トモビキなんや!」
体育祭だ! ちよちゃんが借り物競走で飛んできた!
「ブルマか?」
「智ちゃん来て!」
「おお! トモビキだー!」
・仏滅
「仏滅ってなー、なんでぶつめつなん?」
「……またこいつは妙なことを」
「よみちゃん知ってるー?」
「うーん、たぶんあれだろ、仏滅は葬式をしないから、仏教に関係あるんだ」
「死体に関係が?」
「ちがうちがう。仏教」
「仏いうたら、死体やろ?」
「……た、たしかにそうだが」
「せやったら、死体の教えやんなあ」
「なんか釈然としないな」
・大安
「今日は大安や。せやから安心やでー」
「……なにを言ってる」
「榊ちゃーん。今日は大丈夫やで」
「なにが?」
「ほら、カミネコさんや」
「う……」
「今日は噛まれへんで。大きな安心の日や」
「大丈夫なのか?」
「私が保障します」
「かえって不安な気もするが……よし」
そ~~~っと。
…………。
がぶ。
「痛い……」
「あー、ごめんなあ。別な安心の日かな?」
「なんの安心?」
「激しく動いても漏れません。これ以上は乙女の口からなんて言えへん」
「……あの日ネタで誤魔化すのか?」
「いやや、榊ちゃんエッチや」
「一度だけでいい、殴っていいか?」
「へ?」
・赤口
「大阪さーん。どうして口を開けてるんですかー?」
「あーあはふひやへふ」
「……えーと? なに言ってるかわかりませんよー」
「ちよちゃーん、そんなバカ相手にしたらだめだよー」
「え? 神楽さん?」
「そいつさあ、今日が赤口だからって、口開けてるんだよ」
「ど、どうしてどんなことを?」
「秘密があるに違いないだってさ」
「でも……口の中って赤いというより、暗いですよね」
「だから大きく開けてるんだよ」
「……へー」
「ちよちゃんも成長してきたねえ。放置を覚えたか」
「悪いやつだなあ神楽。大阪に赤口のこと最初に言ったの、おまえだろ?」
「乗ったのは大阪だよ智。私に責任はないって」
その日の午後、救急車が一台学校にやってきて、あごの外れた大阪を連れて行った……
・先勝先負
「てやー! ちょっぷ!」
「痛いーー! なにをする大阪」
「赤口の復讐や! 先手必勝や!」
「うん? もしや」
神楽はスケジュール帳を開いた。
「そうか、今日は先勝――じゃない、先負じゃん!」
「な! そんな! そんな馬鹿なーー!」
「あれ? もしかして勘違いか? 勘違いか大阪!」
「だって、六日ごとに繰り返し繰り返し……」
「先勝と先負は意外と交互に使用されたりするんだよ、ぼんくらー」
「うう……ぼんくらやないねん、ボンクラーズやねん!」
大阪は涙目で走り去った。
「……捨てぜりふからして意味不明じゃん」
・吉日
「あんなあかおりんちゃん……吉日ってどこにもないねんな」
「どうしたの? 大阪さん」
「うん……先勝友引先負仏滅大安赤口……吉日ってどこやのん?」
「あの……それって、いわゆる大安吉日とかっておまけみたいなものじゃ」
「でもな、ネタがないねん」
「ね……ネタ?」
「吉日がないなら、私はどこに入ればいいのやろう」
「はあ……」
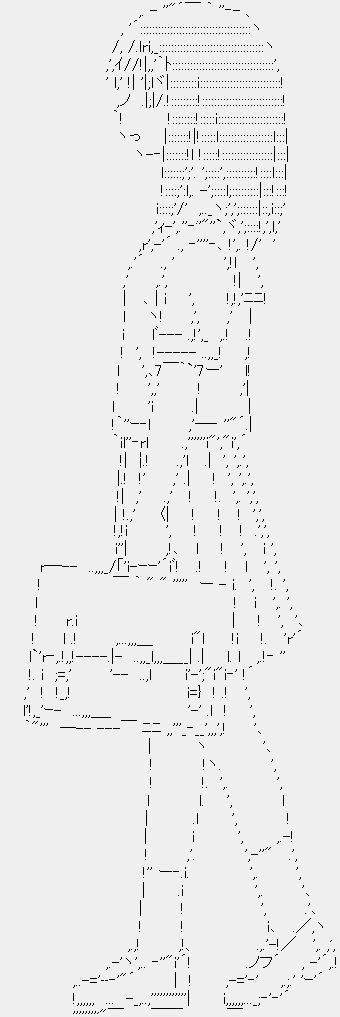
年末年始の休みを利用して、よみは北海道に来ていた。
「……なぜ?」
目の前で牛が枯草をはんでいる。
糞尿の臭さが鼻をつく。
「なぜ私が!」
スキを持ち上げて叫んだ直後、まきあげた枯草にくすぐられた牛のくしゃみをまともに受けた。
「どーしたんべメガネなんが真っ白にしてぇ?」
尋ねたのはメガネをかけた老婆である。
「……いや、ちょっと」
「さっさど洗ってこい」
「はい」
沈んだ気持ちで洗面所に行く。メガネを取り、顔を洗う。顔をタオルで拭き、さらにメガネを拭きながら鏡に映る自分を見つめる。
「うう……なんでこんなことに?」
本当ならこの顔は今頃笑みにたっぷりと彩られていたはずだ。それがなぜ、田舎で牛と牛と牛と牛と……
「キー!」
「うるせーよ、よみちん」
「いてっ」
頭を小突かれた。
「叔父さん」
振り向くと、やはりメガネをかけた男がいた。
「あんだー、もう終わったんだべ?」
「はい」
「東京住んどると要領がよぐなるんだな」
叔父さんはげらげら笑いながら去ってゆく。よみはさらに命じられた仕事を色々とこなしてゆく。
「よぐ働くなー」
「力もある、みんな正月休みでいなくなって、助かるわー」
入れ違いに2匹のメガネ唐変木が笑って話しかけてくる。牧場の息子どもだが、肉の食い過ぎでちょっと体重がありすぎる。
(……父さんに騙された!)
温泉、かわいいキタキツネ、おいしい料理――
(騙された! 騙された!)
かっこよくなったという従兄弟たち――
(本当は働き手が欲しかっただけじゃないか!)
晩になると全員で食卓を囲む。全員がメガネをかけている。
ペットの猫まで目の周囲がメガネ柄だ。
「ザ・メガネ一族!」
よみは溜まらず叫ぶと、粉雪降る外へと走り出た!
牧場の周囲は真っ暗だ。街灯もない。田舎田舎、ど田舎だ。
「キツネ……温泉……かっこいい男の子……おいしい料理……」
いつのまにか道に迷っていた。
(しまった!)
もしかして追いかけてくれると、秘かに期待していたのかも知れない。
(いや、あいつらに限ってそれはない!)
よみはなんとなく想像してみた。
『あれー、よみちゃん出ていったべ』
『きっとこの鍋が美味しがったんだー』
そしてまた黙々と食べ始めるメガネども――
そういえば、牛舎の牛たちもなぜか多くが目の回りが……
「メガネいやー!」
よみはメガネを取って、思わず暗闇に投げてしまった。
メガネはたちまち雪に吸い込まれ、消えた。地面に落ちる音はしない。当然だ、雪がすべてを吸収してしまう。
「……メガネのバカー! 北海道のバカー!」
よみは不満を思いっきり叫んだ。すべては雪が吸い込んでくれる。誰も聞いていない――
いつのまにかそいつはいた。
「……バカー!」
「くー」
「ば……?」
可愛い声のしたほうに涙を拭いて向いてみると、そこに見慣れぬ動物が1匹いた。
「……なあおまえ、もしかして」
「くー」
「キタキツネ……?」
「くー」
毛深くて小さくてもこもこしているそいつは、ゆっくりとよみの足元に来て、その側を通過したと思ったらすこし離れてまた近づき、離れて――を繰り返した。
興味深くてしばらく観察していたが、よみはそいつが気に入った。
「エサが欲しくて、しかし媚びるのはいやで……なかなか複雑なやつだな、おまえ」
「くー」
そいつはまた鳴いた。
「そうかそうか、ほれ、チョコレートだ」
よみは秘かにくいしんぼなのだ! 口が寂しいときの携帯食料には事欠かない。プライドと体重が気になるので間食は適度にセーブされている。
「くー」
そいつはおいしそうにチョコを食べた。
「そうかそうか」
よみはそいつの頭を撫でようと思ったが、やめた。そうしてはいけない気がした。自分なら、嫌だ。だからこいつにはしない。
「なあ私に似てるきみ」
よみはそいつに微笑みかけた。
「くー!」
そのとたんだった、突然そいつが高く鳴いて、一目散に走り去ったではないか。
「……なぜ?」
直後、雪の中からなにかの音が響いてきた。
「スノーモービル?」
牧場に来た初日に聞いた。乗れるかと秘かに期待していたが、翌日から連日の労働で失望して今に至っている。その存在もすっかり忘れていた。
やがて雪の中からヘッドライトの光が生まれ、スノーモービルはよみを確認するとまっすぐやってきて、すぐ側に止まった。
男だった。手になにか筒状のものを持っている。メガネがないので良く見えない。
「おい、命は大丈夫か?」
(命が? ――どういうこと?)
「熊いなかっただ?」
声の主を思いだした。よみを牧場まで乗せたバスの運転手だ。
「え……あの……熊?」
「親子連れの熊だべ。バカなガキが迷子の小熊を追ってしまっで、母親が怒っただ。生憎ガキは軽傷で済んだが、まだこの辺にいるはずだべ」
「うわ……」
怖くなって震えてしまう。男が持っているのは猟銃なのだ。
「だがらおまえ、さっさとけえれ」
「でも道が」
「あちらだ」
男が指すほうは、ぼんやりとして見えない。
「えと……あの」
「近いだ、じゃな」
男はさっさと行ってしまった。
まっくらな中に、よみは1人取り残された。
「あの……見えないんですけど」
そのときだった、またあの声。
「くー」
丸い獣がやってくる。
「まだいたの?」
「くー」
その子はよみのズボンの裾に食いつくと、引っ張り出す。
「え、こちらに? あの……熊がいるんだって」
「くー」
よくわからないが、どうも連れて行きたいところがあるらしい。
「わかった、わかったよ」
大人しくついてゆく――数分してある木の裏につくと、そこで蠢く鼻息。音が、妙に大きい。
(なんだろう? まるで牛みたいに大きい動物の……まさか、熊!)
「ぐー」
その動物が、大きな声で鳴いた。「くー」の大きい版だ。その変な音に、よみは沸き上がりかけていた恐怖がやわらぐのを感じていた。
「……わかったわかった、チョコあげるよ」
よみは板チョコを取り出し、残りすべてを近くに投げた。
「ぐー」
その大きい――おそらく熊らしいもの――はゆっくりと歩くと、チョコをむしゃむしゃと食べて「ぐふふ」とまた面白い声で鳴いた。
「そうか、美味しいか?」
「ぐふふっ」
「くー」
小熊も親熊からチョコを貰って、美味しそうに食べている。
「よかったな……」
ふっと、よみは自分の意識が遠のくのを感じた。
(あ……れ?)
気が付くと、布団の中だった。
叔父さん一家は私が牧場の前で倒れていたと言って、よかったよかった、ごめんごめんと言うばかりだった。
(……どうやら、助けられたみたいだね)
熊の親子は、よみを運んでくれたのに違いない。
その後よみの待遇は大きくかわった。もちろん主目的が労働力確保だったので仕事はしたが、いろいろと楽しい経験を出来た。充実した正月をすごし、東京に帰った。
年明けの初登校。
いつもの連中、いつもの時間、いつもの場所。
心地よい。
そんな空間を満喫し、家に帰った。
(けっきょく、熊の親子のことは言えなかったな……)
そもそも「旅行」自体が嘘である。北海道にいた期間は1週間以上に及ぶ。真実の多くをオミットし、楽しいことしか語っていない。
(それが私らの間じゃ似合ってるからなあ)
仲間内ではけっこういろんな話をするはずだが、なぜかみんな幸せなことしか語らない。本当はいろんな悩みとか問題とかがあるはずなのに、智からして高校にあがってからは幸せ者のふりをしているように思えてならない。
いや、それはそれでいい。
仮面かもしれない。虚構かもしれない。
だが、それは皆が望んでいることなのだ。
不文律。
その細いバランスの上で語らい、どつき合い、楽しい思い出だけを凝縮させてゆく。
(私たちはピエロなのかも知れない――そんなのでもいい。それを望んだ者だけが自然に惹かれ合い、演じているんだから)
演じていれば、それが真になるだろう。どうせ残るのは凝縮だけだ。
ふとテレビをつけると、北海道で暴れ熊親子射殺のニュースが映っていた。
「あのときの……」
小熊は助かったようだが、動物園に送られたらしい。
「…………」
なんだかやるせない気分になってテレビを切る。
あの熊は、暴れているのも真実だろう。だが、よみに見せた面も真実なのだ。表裏一体、どちらを見るかで気分も、世界も、人も、すべてが変わる。
「そう……これでいいんだ」
よみは自然に流れ出た涙を拭った。
(なんだか拭ってばかりだな)
よみは葉書を出して、すらすらと書き始める。
「涙のダイエット少女です。このあいだ北海道で……」
これはメルヘンだ。おそらく採用されることはあるまい。
だけど実際に起こったことだ――
信じる信じないなど、誰にも求めない。
だからせめて、文章にしておきたい。
チョコレート好きな熊の親子のことを……
あるところに1匹のカエルがいた。
「げこげこ。げこげこ」
そのカエルは実は菜食主義者だった。
かえるは思った。
(あー、植物食べたい)
だけどカエルは肉食だった。肉食なのに菜食主義なのは謎だ。
「げこげこ(こうなったら人間になろう)」
そうすれば寿命が長くなるし、植物も食べられる。
カエルは天才チヨチャンメデスのところに行った。
「あー、カエルちゃんですー。かわいいー」
ちよちゃんは10歳だけど天才なのでギリシャで博物学者をやっている。
「げこげこ(ぼくを人間にしてください)」
「なにいってるんですかー?」
「げこげこ(人間にーーー)」
「わかりましたー。魔法で変身させてあげますよー」
「げこ(なぜに?)」
チヨチャンメデスはいきなり魔法の(好きな名前を入れてください)を取り出すと、呪文を唱えた。
「(好きな呪文を入れてください)!」
(好きな効果を入れてください)
カエルは見事、人間になった!
「きゃー、男の子だったんですねー。隠してくださいー」
顔を真っ赤にする女の子を見て、素っ裸のカエル(人間版)は興奮した。
「おお! 人間に性的に興奮している! 人間になれた!」
カエルは今まで沐浴に来た女性の裸を見てもなにもなにも感じなかった。それが今、下半身が反り立っている!
絶倫だぞ。だけど10歳にはちょっとやばい!
「あんなー先生ー?」
そこにちょうど、オオサカリアナが入ってきたのだ。
「うわっ! うわっ! ロリコンや、痴漢や!」
カエルはやばいと思った。
(そうだ、ぼくは人間になって、植物を食べるんだった!)
すぐに室内にあった観葉植物にがぶりつき、いきなり食べ始めた。
「この人、変態さんや」
「……元がカエルなだけに、ダメですねー」
「カエル?」
「はい、人間になりたいって私に言ってきたカエルさんですよー」
「さすがはちよちゃんや。不可能はないねんなー」
「そうです。天才なんです」
そんな会話を横目に、カエルはあまりの不味さに食べたものを吐き出した。
「……ぶえー、苦くてまじーや」
「カエルさん、あなたはどうして人間になりたかったんですかー?」
「はい、それは――」
カエルは理由を説明した。
「ふーん、そんでなあ、いつまでその棒を立たせてるん?」
それはギンギンに立ったままだ。カエル自身もちょっとイヤだ。
「……なぜか縮みません」
「よし、切ったらええねん」
オオサカはいきなりハサミを取り出した。
じょき。
「ぐわあああああー!」
辺り一面血の海だ。
「よかったなー、これで世界は平和になったでー」
「あ……ありがとうございました」
「……普通、礼なんて言わないと思いますけどー」
こうしてカエルはカエサルとして一生を生きた。
彼のちんちんがなかったというのは誰も知らない事実だ。
「あんなあ、ギリシャが舞台って話おかしーやん。ローマ帝国やでー?」
「……適当に書いてますからねー」
しまった、「サル」ということでオナニーしっぱなしでそう名付けられたってほうが面白かったか。
というわけで題名はサル(意味なし!)。
今日、榊が死んだ。
あんなに愛し合っていたのに、
隣のあの変態が俺の榊を殺した。
許さない――
墓参りで買うのが面倒だからって、
俺が丹誠込めて種から育てた榊の苗を!!
23 めんせつ (2ちゃんねる・イオナズンのガイドライン)
面接官「学生時代で打ち込んだものはなんですか?」
大阪 「くさび!」
面接官「……え?」
大阪 「くさびというのは――」
面接官「いいですいいです、もういいです」
大阪 「はあ……」
面接官(……ったく、何者だこの少女は……それで……なんだこりゃ?)
面接官「特技は……わりばしぱきーんとありますが?」
大阪 「はい。わりばしぱきーんです」
面接官「わりばしぱきーんとは何のことですか?」
大阪 「占いです」
面接官「え、占い?」
大阪 「はい。占いです。確実きれいに箸が割れます」
面接官「……で、そのわりばしぱきーんは当社において働くうえで何のメリットがあるとお考えですか?」
大阪 「はい。よーさん利くんで、倒産の危機も大丈夫です」
面接官「いや、当社の業績は非常に安定しています。それに不用意にそんなことを言うのはけしからないですよね」
大阪 「せやけど、総会屋にも勝てるんやけど……」
面接官「いや、勝つとかそういう問題じゃなくてですね……」
大阪 「どないな問題も100割解決なんです」
面接官「ふざけないでください。それに100割って何ですか。だいたい……」
大阪 「100パーセントの親分。私が考えました」
面接官「聞いてません。帰って下さい」
大阪 「あれあれ? ええのん? やりますよ、わたし合格させやて、わりばしぱきーんで洗脳」
面接官「いいですよ。やって下さい、わりばしぱきーんとやらを。それで満足したら帰って下さい」
大阪 「……運がよかったなー。今日は割り箸を持ってきてへんかった」
面接官「帰れよ」
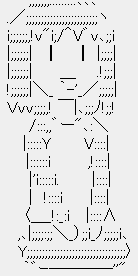
あるところに智ちゃんがいました。
「おひゃー」
しかし神楽はいない。
「ここって、神楽を苛めるスレなん?」
するとどこからともなく天の声が――
「ちゃうねん、智ちゃんと神楽ちゃんが愛し合うスレやねん」
「その声、大阪か!」
「ちゃうねん、私は神様やねんで。大阪なんて知らへん」
「ならば神という証拠を見せろ!」
「ええよー」
「よし、100万円くれ!」
「……欲深い願いは聞けへんねん」
「ちょっとくしゃみしてみろ」
「へーちょ」
「やはりおまえ大阪だろ!」
「ちゃうよ、神様やよ?」
25 CATMENT (ガンダムSEED歌・MOMENT)
誰も皆 猫が可愛いと 頭を撫でてる……
この子ならば今度こそ撫でられると 思ってたあの日々
月日は流れ 変わらず噛まれている すれ違う予測
巡り来る 試みの果てに あの猫が 許せばいいのに
猫の額 夢に見てやまぬ この闇の彼方に 毛触り求めて――
キャッツ・アイに映る私はどんな敵なの? やはり返事はない
ただただ寝ころび 手を伸ばせば唸る 傷つき慣れる心
めくるめく 旅路の中で 私の手に 応える君が来た
茶斑毛 野生が見上げて この時を待っていた 毛触り重ねる――
私の感触 忘れてしまわないでいて 汚れを知らぬ肉球
巡り来る 季節の中で ツインテールと 危機になった時
体ごと前に飛び出て 正義の瞳で見つめて
茶斑毛 野生の果てへ 胸の中で 床を転がり離さずに
高校総体が終わって、とつぜん暇な日々がやってきた。
担任が顧問であることもあって宿題も免除されているので、とくにすべきこともない。学校に行って部活でもしようかと思ったら、立入禁止になっていた。プールの水を抜いて、遅れていた定期点検と補修を2~3日かけて行うという。そういえば私たちがずっと使っていたから、水を入れ替える暇もなかった。私が都大会で優勝し、インターハイに出ることになった影響だ。ほかで泳ぐしかないが、だからといってその辺のプールなどではとうてい泳げない。私には遊ぶために泳ぐという発想がないし、25メートルのラインなんて確保できないだろう――まだ高1だしどこの会員でもないので、スポーツクラブのプールで泳ぐということも出来ない。
家に帰ると、父がいきなり5万円もくれた。どうやら総体でがんばったご褒美らしい。断る理由もなかったので受け取り、礼をいうとはにかんで喜んでいた。目尻にすこし皺が寄せ始めている。ああ、父はもう若くない、と不思議に感じた。
私はその晩、考えた。あと10日、なにをしよう。プールには数日も待てば通えるようになる。毎日朝から晩まで泳いで、それで終わるのか、この夏は。すると父の目尻がふと浮かぶ。年月はどんどん流れていく。一生に一度しかないこの時間、私は他にも、なにかしておきたい。
だから私は朝になると、すでに決めていた。
「ちょっと1人で旅行に行ってくるよ。3日ほど」
朝飯のとき、そう両親にいきなり言い放った。反対があるかな、と思ったけど、とくにそれらしい応答もなく、母が弁当を作ってほらよっと渡してくれた。たしか私、自分だけでどこか遠くに行くのは、生まれてはじめてのはずなんだが――と思ったが、言い出した勢いに任せ、とりあえず2日ぶんの着替えを用意し、いつも使っている水泳バッグに入れてさっそうと出ていった。
家からの1歩を踏み出てしかし、ちょっと不安が頭によぎった。いいのかこんなんで? と。ふり返って自分の家を眺めてみる。生まれてはじめてやるぜ、という行動の前だと、なんだかいつもの自分の家じゃないような気がしてくる。3日後にこの風景をまた瞳に入れて、私はどんな感想を抱くのだろうか。門札には『神楽』という文字がはっきりと刻まれている。うん、ここは私の家だなと、当然すぎる確認を胸に、私はふたたび振り向き、旅に出た。
20日(はつか)遅れの、本当の夏休みがいま、始まったんだ。
東京駅でどこに行こうか迷っていると、宮城県松島のポスターが目に入った。日本三景か……たしか、松島、天の橋立、宮島――前のふたつは行ったことがある。そうだ、宮島に行って日本三景を完全制覇してやろう。目的ができれば後はひたすら進むのみだ。だけど……
「宮島、宮島……どこにあるんだ?」
「広島ですよ」
ふり返ると、おかっぱ頭の可愛らしい子がいた。たしか同級生で3組の、えーと……顔しか知らない。だけど、なぜここに? 見れば他にも知った顔が何人か、荷物を抱えて立っていた。
「天体観測の合宿でー! 岡山県美星町の天文台に行くんですー!」
いきなり呼ばれもしないのに、頭のイカれたキムリンがしゃしゃり出てきた。
「一緒に星を見ようね、かおりん」
「かおりんって呼ばないでください!」
おかっぱ頭の目がつり上がってる。よほどいやなんだろう。
とりあえず行く方向がおなじということで、岡山までキムリン率いる天文部に同行させてもらうことにした。それにしても、みんな顧問から離れて――どうやら違うようだった。キムリンは勝手についてきたらしい。本当の顧問が野獣からカワイイ生徒を守っている。いやキムリンは野獣というよりただの覗きだ。物理的な実害はないが精神的にはちょっとイヤすぎる、ゴキブリみたいな存在だろう。
岡山で天文部ご一行が降りると、いよいよ私一人になった。さあ、私の旅が再開するな。じっくりと孤独を楽しむことにしよ――
「き、木村先生!」
キムリンが私の荷物を抱えて席に座っているではないか!
「あああああの、天文部は?」
カクカクとそいつは機械的に私のほうを見上げ、止まった。まるでロボットのようだな、人間離れしすぎてる――と思ったとき、いきなり叫んだ。
「一等賞――!!」
人さし指をぱっと振り上げ、私の胸をまっすぐ差し、ふたたび一声。
「一等賞――!!」
み、耳が痛い。それだけではない。周囲の視線がちょっとどころではなく激しく痛い。
どうやら私の胸がご執心のようだ。とんでもない状況になってしまった。なんとかしてキムリンを遠ざけようとしてみたが、背後霊のように狭い車輌の中を付いてくる。ストーカーだ、ストーカーだ! これはまさに恐怖だった。力は確実に私のほうがあるし、たぶん殴っても状況的に私が有利になるかも知れない。それどころかキムリン自身、気にも留めない可能性が高い。だけどそういった要素をすべて考えてもなお、いやだった。こいつがそばにいる、ということそのものが。退けるのに対象そのものになにかするということが。まさにゴキブリを嫌う心理そのものではないか! やーいやーいゴキブリゴキブリ――これって完全に差別かな? まあいいや難しいことは私にはわからない。とにかく逃げるという選択以外はすべてイヤだった。
私より大きな胸の女性の近くに座ったり、トイレに30分籠もってみたり、いろいろしたがすべて徒労に終わった。見える視線、見えない視線の双方に耐えられない。こいつは別にハアハアしたりとかせず、ひたすらじっと眺めてるだけなのだ。メガネをかけているので表情も読めないし、そもそも無表情――というか、常に仮面が貼り付いたような奇形の顔。噂では寄付をしたりするような善人の面もあるらしいしたぶんそうした面が評価されて先生などやってられるんだろうが、すくなくとも私にとっては生理的な嫌悪感がプラス要素のすべてを凌駕する。
我慢できない。
気が付けば私は適当な駅で飛び降りて、全速力で駆けて行き先も見ずに出発寸前のバスに乗っていた。キムリンは……よし、居ない!
安心してバスの行き先を見てみると、その中に湯木町というものがあった。気になって運転手に聞くと、どうやら温泉の町らしい。よっしゃ、これはいい。キムリンで疲れた精神と体を、温泉につかってゆっくりと癒そう。今日の宮島行きはなくなってしまったが、温泉は温泉でいい。完璧にいきあたりばったりの旅だが、そもそも明確な目的なんてないのでこれでいい。そう思ったら、キムリンというトラブルもまあまあ良い思い出になるかな、と思う余裕も出てきた。
1時間ほどして、まもなく目的地だよと運転手が教えてくれた。そのときにはバスの客は私しかいなかったので、私は最前列の席に移って正面の景色を見ていた。田舎道を進んで、やがてバスは暗いトンネルにさしかかった。バスの中もほとんど夜同然となる。
「ここを抜けるとまもなく、湯木町だよ」
「へえ」
なぜか「雪国」という単語が浮かんだ。なにかえらい作家が書いたやつで、試験でむりやり覚えさせられた。冒頭が、『トンネルを抜けると、そこは雪国だった』みたいなやつ。このトンネルを抜けたら、そこは私の疲れを癒してくれるパラダイス、温泉の里が待っているのだ。雪と湯木がおなじ発音なので、こんな連想になってしまったんだろう。
視線の先に、トンネルの出口が見えてきた。白い。やたらと暗いところから出る先は、いつもなぜか白い。だからまるで宝くじのようで面白い。この白いもやが晴れて、まもなく向こう側の世界が開けてくるのだ――あれ? 出口になにかいる。
そいつはこちらに向かって手を振っていた。運転手は不思議に思いつつ、ブレーキをすこしずつ踏んでゆく。トンネルの出口に近づきつつ、バスの速度は落ちてゆく。
もしや。
そんな思いが、私の頭に浮かんだ。もしやこいつ、あいつでは?
いやそんなはずがない。私の先に回って、合流できる道理があるのか? 行き先を確実に量るとしたら、あいつは超能力者ではないのか? そもそもどうやって先回りする? ――詳しいことを考える暇もなく、わずかな時間は残酷にもすぎさり、みじめな現実が私の前に立ちふさがっていた。
「いっとう……」
そいつが勝利のおたけびをあげようとしている。
それに気付いた瞬間、私はついに我慢できずに突発的な行動を起こしていた。
運転手を運転席から引きずりだし、彼の怨嗟を無視して席に座るや、ハンドルをぎゅっと握りしめ、アクセルを全開にしてそのゴキブリに突っ込んでいった!!!!
いやな音とともに、そいつは転がり飛んでゆく。
「賞~~~~~~!!!!」
その日の温泉はとても気持ちよかった。
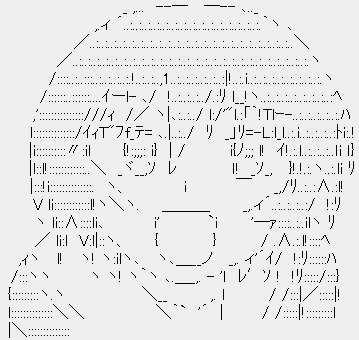
27 すいまや (よつばと! 電撃大王2003年2月号+吉野家)
ふーかはおよげない。おとななのに。とーちゃんもジャンボもだ。だからよつばがおしえてやる。
いうこときけといった。へんじない、やるきない、だらしない。さんまのきもちになれとおこった。よつばさんまをおいかけてとる。さんまはしぬきょーふをあじわう。とてもはやくなる。よつばのがはやいからとるけど。
とにかくおよげるよーになる、これさいきょー。
しかしりょーしにマークされるというきけんもともなう、もろはのつるぎ。しろーとにはおすすめできない。
まー、おまえらうかないおとなは、うきわでもつかってなさいってこった。

28 2004版が出た記念 (ひめくりあずまんが+ウィーザードリィ)
宿屋の寝室にて。
「あんなー神楽ちゃん、なんとなーく新しい呪文を覚えた」
「ど、どういう魔法だ大阪?」
「うん……ヒメクリ!」
室内に風が吹いて、近くの机に置いてあった日めくりカレンダーが1枚、めくれ飛ばされた。
「これが戦いにおいてなんの役に立つんだ?」
「1日に1回しか使えへんねん」
「だ・か・ら、なんの役に立つんだと聞いている」
「神楽ちゃん苺のでかいプリントはちょっとあかんと思うで」
「人の話を聞け~~!」
ぐりぐり。
「いたい、いたいー」
次の日。
「なんて数の盗賊だ! 大阪、強力な攻撃呪文で撃退してくれ!」
「わかったでー。ティルトウエイトやー!」
しかしなにも起こらなかった。
「あー、使用回数(MP)切れてもーた」
「だー! おまえも武器もって戦えー!」
「いややねん。私は後衛やねん。だから応援するんや」
大阪は笛を吹き、団扇を振っている。
「意味ねー! 援護魔法だー!」
「わかったで。ヒメクリッ!」
ひゅるるるるー。
「いまや! 盗賊さんたちが苺に見とれてる間にやっつけるんやー!」
「おお!」
「はあはあ……なんとか勝てた」
「よかったなー神楽ちゃん。でもな、2日もおなじ下着はどうかと思うんよ。
女の子やったら、もっと清潔にしとかなあかんでー」
「ダンジョンで言うセリフか、それ?」
ぐりぐり。
「いたい、いたいー」
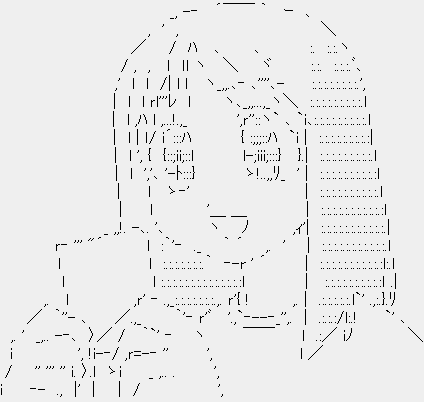
12月にもなると、担任してる生徒どもがちょっとブルーで雰囲気悪くて鬱陶しい。一部には滝野や大阪みたいに余裕つーかまるで自分が受験生である自覚のたりねー脳足りんもいるが、おおむねはごく普通のおつむだから、それなりに悩んでいるようだ。これも青春というか、うちのクラスは戦力的には良い――いやあまり役に立たなかったが畜生! ――が、それは個人的に受け持つ私が面白いとか、体育祭で勝てるとか、まあそういうことだ。
それでクラス担任なんてしちめんどくせー役割なんて教頭のバカから仰せつかってる以上、私としてもなんとかしてやらねばなーとはなんとなく思ったり思わなかったりだが、暗くて鬱陶しいのはだいっきらいなので、結局半分放置してるだけになってしまってるわけだが。あー、新しいゲームの発売日じゃねーか。帰りに買おっと。で、なんだったっけ? ――そうそう、放置しちまってるのは、あーゆー青春てゆーかそーゆーもんはいくら前向きになんとかって言ったところで、またはえんえんと聞いてやったところでも、まるで説得にもなんにもならねーわけだからさ。私としては仲がいいフリくらいは出来るが、結局のところ、あいつらが自問自答して解決するしかねーわけで、こちらに出来ることっつーたら、カンフルだけさ。そもそもカウンセラーみてーな器用な芸当、私なんかにはできねーんだよ。
バカだから。
うわ嫌なこと思った。なんで自分のことバカって。私はお利口なんだぞ? ――だって、にゃもが彼氏とラブラブだったころ、にゃもに気付かれずにいろいろ裏工作して別れさせることに成功してきたんだからな。中学のときも、高校のときも、大学のときも。だってにゃものやつ、私を世話してくれないものだから、急に部屋が汚くなったり遅刻するようになったりして不便だったからね。そう、私は、利口だ。
なのに教頭のやろう、私がバカだって? いったい何様だってんだ。私はちゃんと生徒たちをすこやかーに導いてやってるじゃねーか。ああん? 教師にだってちゃーんとなってるじゃねーか。猫の毛皮を10枚は被ってなんとか3度目で合格したわけだけどさ、担任だって受け持ってるんだぜ。世の中には、担任になるまでに10年はかかる無能がごろごろいるっつってんのに、私はぴちぴちで、お年玉もまだ貰える美貌で、担任だ。けっしてこの学校が人手不足なわけじゃないよ?
――なんだ? 大阪。私はいま忙しい……なんだってー!! 素敵な発想の生徒を育てられるだと? 大阪がかぁー? 「どうでしょう」って、なにゆーてんじゃ大阪ぁ! それに、ちよ助のバカ! 大阪のやつが教師なんかになれるわけねーだろ? じゃあボンクラの大阪でもなれるような教師って、どーゆー職業だってゆーんだー? 私だってなあ、それなりに理想を持って目指して、やっとなれたんだぞ? それが、思いつきでなれるような職業なわけねーだろ! 聖職だぞ聖職! いちおう聖職なんだぞ! この野郎! うお、もう教室だ。こういうときははえーな自分……とにかくちよ助だ。
「ちよすけぇ!! あんた私をバカだと思ってるでしょ」
「??」
驚きに見開いた眼で反応できてないちよすけ。自分が犯した禁忌に気付いてねえ? この野郎! 繰り返して聞いてやる。
「あんた私をバカだと思ってるでしょ!」
……一瞬の躊躇のあと、いいやがった。
「はい」
ちょーっぷ!
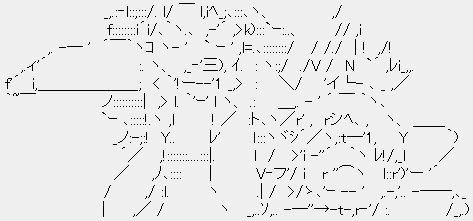
30 ギネス級エレジー2 (2ちゃんねる+あずラウンジ一周年記念プレゼント)
【知徳】校長です【文武】
1 名前:優しい校長先生 投稿日:1997/9/16(月) 09:30 ID:tesutmas
我が校にもスレッドフロート式掲示板が出来たので、
記念にこのスレッドを立てました。
みなさんが普段思っていることをなんでも打ち明けてください。
2 名前:百合少女 投稿日:2004/02/01(日) 19:58 ID:yrkaorin
どうしてこのスレは6年以上も消えてないんですか?
3 名前:へーちょ名無しさん 投稿日:2004/12/21(土) 19:59 ID:tomosexa
なんだこのスレ、すげー
4 名前:へーちょ名無しさん 投稿日:2004/02/01(日) 20:05 ID:???
史上最長の放置プレイを味わった1さんがいるスレはここですか?
5 名前:へーちょ名無しさん 投稿日:2004/02/01(日) 20:08 ID:???
ていうかもう代替わりしてるだろ(w
6 名前:へーちょ名無しさん 投稿日:2004/02/01(日) 20:15 ID:osakasan
6年消えんかった理由を私も知りたいですー
7 名前:着替え見たいなあもう 投稿日:2004/02/01(日) 20:22 ID:kimurin7
みなさん夜更かしはいけませんよ、早く寝てください。
このスレッド、よく見つけてきましたね。私も忘れてました。
たしかエンジニアに頼んでシステムに干渉させたのだと思います。
8 名前:6 投稿日:2004/02/01(日) 20:31 ID:osakasan
まだ9時前やでー
えこひいきあかんやん
先代の底知れぬ深ーい意地を感じた
9 名前:涙のダイエット少女 投稿日:2004/02/01(日) 20:47 ID:55yomi55
毎日毎日、朝昼晩とパソコンに向き合うたび、
がっくりと肩を落とす先代の哀愁を想像して涙が出ます。
爆笑の。
10 名前:へーちょ名無しさん 投稿日:2004/02/01(日) 20:50 ID:tomosexa
これギネスに申請できねーかw
11 名前:校長 ◆ZzAZUxozdw 投稿日:2004/02/01(日) 21:00 ID:m_sandayu
そんな薄情なおまいらの生活を、つぶさに垣間見てやる!
【1周年プレゼント DVD あずまんが大王 全26話】
そのとき、私は泣いていた。近所の空き地で、顔をくしゃくしゃにして、せっかく塗った口紅も晴れのお洋服も汚してしまって。夕焼けが私の背中にそっと赤い灯火を落とし、周囲を薄暗くして服の汚れを隠してくれている。
「泣くなよー」
その子は土に汚れた手で、構わず私の背中をさすってくれる。いつもの私なら嫌がるだろうけど、そのときは余裕なんてなかった。そして――その手が不器用に私を慰めてくれるたったそれだけのなんてないことが、たった今までの大事件で悲しみと混乱に占領されていた私の心を癒し、支配から解き放ってくれていた。
「にあもー」
幼い声で、その子はやはり小さな手で、私をなぐさめてくれる。心配そうな顔で、幼いその子はやはり幼い私を、本気の瞳で見つめていた。彼女は、いつも本気で、そして本音だ。
「にあもには、けしょーはにあわねーよ」
……たった今の、なし! 瞬間的になにもかもが180度反転。
「なんだとー! ゆかりー!」
私は目元を擦らせていた腕を伸ばし、ゆかりの口を思いっきり横に引っ張る。
「ひ、ひへえひへえ――にーはーほー」
「うあぉぉぉおぉぉお」
喧嘩がはじまる。けっきょくそのとき負けたのは私だろう。だって、記憶が途切れている。つぎに覚えている瞬間は、母に冷たくてしみる塗り薬を傷口に塗り込められている場面だった。隣にはその日出会ったばかりのゆかりがいて、やはりゆかりの母に怪我の手当を――してもらってなく、げんこつでしこたま殴られ、それにゆかりが果敢に、いや、無謀に抵抗するという大立ち回りだった。勝てるはずがない、と思ったけど、同時に負けてなるものか、とも思った。
そういえばなぜ私とゆかりは喧嘩してたんだっけ――
「――なに黙ってるの、にゃも? まさか道に迷ったとかー?」
「え? ああ。思いだしてたのよ。さっき通ったビルの前でね」
「ん――?」
助手席のゆかりが後ろを振り向くが、もちろんそのビルはとっくに彼方だ。
「もしかして、中1まで空き地だったとこ?」
「え? わかったの?」
「わからいでかー。この辺は庭だったしねえ。どこになにがあったっかもみんな覚えてるし、あちこちに戦歴を刻んできたからねえ」
「そうね――それで私はいつも連れ回されて、ゆかりに」
「子分Aだったもんなー」
「うるさい黙れ」
「なんだよー、本当のことじゃないかー」
「うっとうしい。首にまとわりつくな」
「もう、にゃもったら恥ずかしがってー」
私は激しくハンドルを切った。
「うわっ、事故を起こしたらどうするんだよ」
「あらごめんなさい」
「わざとのくせに、わざとのくせにー」
まったく、自分で運転するときはどんなに激しい横Gでも大声で笑ってるくせに、人が運転してるときはちょっとのことで騒ぐ。
「ゆかり、ついたわよ。ここでいいんでしょ?」
私は車を停めた。
「うん、ありがと」
その2階建てのアパートはとても古ぼけていて、ほんの10年近く前まで住んでいたとは、とても思えないほど落ちぶれてひどい有様だった。外側備え付けの階段に足をかけると、錆びてぼろぼろになった赤い鉄が垢のように落ちる。それはそのまま、歳月の重みのように感じられる。
とっくに寿命が来ているアパートはしかし、借家としての命数はまだ切れてはいないようだった。階段を数段登ったところに、備え付けの手紙入れが幾つか針金で吊されている。その中で広告に呑まれてない現役のものは、2つ。
「まだ2世帯、2階に暮らしているんだ」
「にゃもと私がいたころと、おなじ数だね」
「こんなに痛んでしまったのに、誰が借りるんだろ」
「さあてね? まあいいじゃん、行こうぜ」
思春期を迎えるか迎えないかという年齢まで住んでいた私の部屋は、今は誰も借りてなかった。鍵さえも壊れたドアを開けると、風圧でいきなり周囲が灰色に染まった。
「うわひどい埃! すごいね、畳なんて完全に腐ってるよ」
とっくの昔に管理を放棄され、もはや日本ブレイク工業辺りに解体されるまで永遠に誰も住むことはないであろう私の思い出の場。あまりの変貌ぶりに、感慨などまるでない。
「それでゆかり? いったいここに、なんの用があるの?」
「いやね、ちょっと忘れ物があってね。まだあれば、だけど」
ゆかりはおもむろに押入れのほうに向かってゆく。押し入れの上段によじのぼると、そのまま天井板を外し始めた。
いったいなにをしようというのだろう。私の部屋にたしかにゆかりも良く来ていたが、幼いころ、隠しものでもしたのだろうか? ――空き地に宝箱を埋めたことはあったけど。
「スカートが汚れるわよ、ゆかり」
「だいじょうぶにゃも、だいじょうぶ」
板を外し終えたゆかりは、そのまま天井裏によじのぼっていった。
「グンゼで熊さん柄なんて、お子さまよ、ゆかり」
「よけいなもの見るんじゃねー」
数分間、天井からごそごそと、まるでねずみが走りまわってるような音が聞こえてきた。もし私に槍があったなら、そのままぶすりと刺していたかも知れない。ゆかり、運が良かったな。
「お、あったあった」
目的のものを見つけたようで、ゆかりはネズミのように染まって降りてきた。
「埃だらけよ、車にのせたげないから」
「いいじゃんいいじゃん。そんな小さなこと、気にしない気にしない。ほれ、これだよ」
それは――小さなお菓子の箱だった。でもこれ、どこかで見たことがあるような……
「え、これ、もしかして……小学校卒業のときの、タイムカプセル?」
「ふふふ、その通り。えへん」
「でも、それって、空き地がビルになってしまって、その」
「ゆかりちゃんにぬかりなし。夜のうちに忍び込んで、ショベルカーでごそっと」
……そういえば、新聞でちらっと見た気がする。何者かがショベルカーで暴れていろいろ壊したとかなんとか。そのせいで、ビルの完成が1月延びたって聞いたけど――
「あの、その――でもなぜ私のとこに? というか、当時教えてくれても」
「だってうちに隠せねーもん。かーちゃん怖いしー」
……そういう問題じゃないよーな気がする。
「さてと」
部屋の真ん中に置いた箱。それをゆかりは、なんの躊躇もなしに開けようとした。
「ちょ、ちょーっと待った!」
私はあわててゆかりの腕を掴む。かつてと違っていまの私は体力的にゆかりを圧倒している。ちょっと力を入れたら、ゆかりは逆らえない。込められた力の強さに戸惑ったか、ゆかりは小さな悲鳴をあげ、そして抗議した。
「な、なにするのよ」
「だって、感動もなにもないじゃない!」
「えー、なんでー。ていうかさあ、タイムカプセル埋めてた空き地が工事で消えるって聞いても、にゃもほとんど関心示さなかったじゃん。あーそーか、当時片思い中だった近くの中学の男子生徒とかの写真なんか入れてあったの? 中坊になってそうそう失恋しちゃってたからどうでもよかったというか、かえって安心してたー?」
図星っ!
「が……学校行事のことは1年で忘れるのに、そんなどうでもいいことは覚えてるのね」
「あんな禿頭のどこが良かったんかねえ」
「もう! 怒るわよ!」
「隙ありぃ!」
「しまった」
私がゆかりのからかいに気を逸らした一瞬、こいつめ、まんまと私の腕を払って箱を開けやがった。ったく、ちょっとした策士だ。
ゆかりは興味津々にかつて私やゆかり、そして数名の仲良しグループで埋めたいろんなものを物色している。
「わー、見てこれ。メア助のやつ、自分の描いたへたくそな漫画なんて入れてるよ。そういやあいつ、まだ漫画家目指してるのかな――うえっ、なにこれ汚い人形。食パンマン……ああ! 五十三次のじゃん! なんでこんなの入れてるかなー」
メア助とか五十三次とか言ってるが、なんてことはない、堂々とした日本人で、ちゃんとした本名がある。徒名にするにはあまりにも無体な呼称だが、これがゆかりの変態的能力のひとつでかつ皆にその呼び名の多くを浸透させてしまうのだから恐ろしい力だ。ゆかりに目を付けられたら、平和な日常はあきらめろ。それは誇張ではあっても、絵空事ではない。私だってどうしてみなもでにゃもなのかさっぱり判らなかったが、なつみでメア助とか、東堂で五十三次よりははるかにましだった。さすがに多少大人になったのか、大学以降は下火になったが――
「……あ! やっぱりこいつ好きだったんだ」
「え?」
う、はっきり映っている、恥ずかしい思い出!
「わっ! いやっ、待って!」
「へへへーん。まったくこのときから基本的な好みって変わってないんだねー。奥手ー」
「きゃーきゃー!」
もうなにがなんだかわからない。見られたくない赤点のテストが親にばれたときのような、恥ずかしさが脳天から足先まで貫いた衝動が私を駆り立て、一刻一瞬でもはやくこの心理を解決しようと私を急かす。だがゆかりの奴は冷静に私の動きを掴んでいて、まるで私は赤いマントにただひたすら突進する猛牛のように追いすがっては宙を掴むということを繰り返していた。
「やめて、やめて! ゆかりー!」
「青いねぇー。青春だねえー。かわいいねー、にゃもー?」
「もう! もお!」
どたばたと狭い部屋の中を走りまわる。まだひよっことはいえ就職もしてるいい大人が、2人してこんなところでなにしてるんだか――と頭の片隅が冷静に警告を出しているが、体の大半を支配している本能がそれを封殺している。私はいま、ただのニワトリだ。餌をおいかける馬だ。ドッグレースの犬っころだ。
「うるせぇバカ!!」
当方にとっての悲劇、他方にとっての喜劇は、鶴に等しい一声にして終息してしまった。
扉がばたんと開かれ、もうもうと舞う埃のむこうに、仁王立ちになった女性のシルエット。背がすこし曲がり、丈もすっかり低くなっているが、聞き覚えのあるその声の主を、私が忘れるはずもなかった。
「やべっ」
ゆかりがそっぽを向き、窓にかけよってそこからぱっと飛び降りる。
私も床に置いてあった小箱を思わず拾い、ゆかりの後を追った。
「こらぁー、こわっぱども! ゆかアホ! みなバカ!」
管理人のおばあさん、相変わらずご息災でなにより。
――ゆかりは足を挫いていた。
私が肩を貸し、鬼管理人が降りてくる寸前で車を発進させ、なんとか逃げ出すことに成功した。就職して半年も経たずに、いきなり住居不法侵入で検挙だなんて、格好が悪すぎる。子どものときに何年もお世話になった人だけど、挨拶を仇にかえて悪いけど、ここは連絡先を知らないことをいいことに、とんずらさせてください。心の中でだけ謝って、私は助手席で痛そうに足をさすっているゆかりを見てみる。
「ちくしょう。あのババア、今度会ったら見ていろよ、目にもの見せてくれるわ!」
「はいはい、でも悪いのは私たちよ」
「うるせぇバカ!」
「はいはい、それ彼女の口癖ね」
「う……」
口をつぐむゆかりだが、管理人に鍛えられた関係か、ずいぶんと似ているところも多い。親と格闘し、管理人とやりあい、そんな中でゆかりの性格は形作られている――なんで先生になったのかだけは謎だけど。一番向いてない職業のように思えるかも、知れない。
私はさっと左手を伸ばした。
「なに?」
「返して、写真」
「あー、ないや」
「なに!」
「落としちゃった」
苦笑いをする。うっ、私の恥ずかしい写真が、まだあそこにあるのか……
「戻らないでね?」
なにやらかわいげにお頼みモードのゆかり。相手があの管理人でなければ、私はこの糞バカの嘆願なぞ無視してUターンしていたであろうが、いまはさすがに……
「やりぃ」
私の無言の返答で安心したのか、ゆかりはにわかにくつろぎだす。
後部座席に私が放り込んだタイムカプセルならぬ汚れた菓子箱を、よいしょと手に取り、残っているものをごそごそとまさぐった。
「あー、あったあった」
「なんなの?」
ちょうど信号で停まったので、私はまともにそれを見ることになった。
それは一本の、おそらく口紅だった。おそらくというのは、すっかり使い切り、黒い芯と持ち手しかのこっておらず、それもかなり年月が経っていることがあきらかに見て取れるほど、プラスチックが劣化して表面に粉を吹いていたからだ。
「……これは?」
「これはって、覚えてないのー? 私がにゃもから貰った、人生初の戦利品じゃない」
「え!」
得意げにいまやガラクタ以下となった物体を、ふるふると振ってみせる。
「覚えてるー? 私とにゃもが、はじめって会ったときのことを」
「……え。もしかして、これが……それ?」
「思いだしたー?」
「ええ……ちょっとずつ」
そうだった。あの日私は引っ越しのトラックの中で暇をもてあまし、ちょっとぐずついたので母が口紅を渡してくれて、私はコンパクトの小さな鏡で化粧した自分をいつまでも眺め、すっかりご機嫌だった。
トラックが停車し、父が付いたと言って降りたところに、ゆかりが立っていた。
最初は男の子かと思った。なぜならば、ズボンを穿いていたし、膝小僧に絆創膏を貼っていたし、帽子を被っていた。そしてちょっとかっこよく見えた。だから口紅を付けてすこし綺麗になってると思っていたおしゃまな私は、その子の前でくるりと回って挨拶をした。
「はじめまして。わたし、くろさわみなもっていいます」
母はちょっと上流社会に憧れていた部分もあって、私にこういったことを仕込んでいた。それが専門の先生に習うお金もなかっため、まったく素人教師もいいところ。すべてが我流であったため、私の仕草はすっかり芝居がかっており、それも彼女には気にくわなかったんだろう。
「べー!」
といきなり舌を出すと、私が手に持っていた口紅を奪い、走って逃げていった。
「……ま、待ってー!!」
追いかけっこがはじまった。
私は当時、体育が得意だった。母はまず体力はないといけないと言って、私を体育好きに仕込んでいた。だから足も速いというかものすごいほうだった。
「つかまえたー!」
しばらくして追いついて、口紅を奪い返した。その子は驚いた目をして、そしていきなり笑った。
「え?」
私はすこし戸惑った。どうして笑ったんだろう、と。
「すごい速いね。私にかけっこで勝つ子なんて、クラスにも学年にも、ひとつ上にも誰もいないのに」
「ええ?」
「いきなり奪ってごめん。私はゆかり、よろしく」
風が吹いて、ゆかりの帽子が飛んでいった。その下から長くて、きれいな黒髪がふわりと宙に舞い、私はおおきな勘違いを悟って平謝りにあやまった。
たった1時間ほどで、私とゆかりはまるで生まれてこのかたの親友みたいに仲良くなっていた。ゆかりは私が女の子っぽすぎるように無理をしているように見えたのが、ちょっと変だと言った。私はいままでそんなことを言われたことがなかったので、新鮮な気持ちでその意見を受け容れた。
「わたし、お母さんの言うことをちょっと破ったほうがいいのー?」
「そうさ。かーちゃんなんて、うるさくてイヤなことしか言わないんだ。顔をみるたび、それ宿題しろー、やれ手伝いしろー」
「ふうん。私のお母さんはそんなこと言わないよ? 口紅もくれるし。塗ってみる?」
「よせやい、にあわねーよ私になんか」
「にあうよー。だってわたしだって綺麗になったんだよ」
「にあもにもにあわねーよ」
「にあも?」
「みなもだとだめだ、いめーじじゃない」
「いめえじ?」
「だからさあ、かーちゃんの言いなりになんてならずにさあ、もっとこう、ふりーだむでえくせれんとだぜー?」
「ふりい? えくせー?」
よくわからなかったけど、なにか心に決めた意志みたいなものを感じ、幼心にうらやましくなった。ゆかりは、すごい。なんとなくそう感じ、私はますます彼女が好きになった。だけど、同時にくやしくなって、ヘソを曲げた。
「いやー。わたしは口紅がにあうのー。きれいになっていたー」
私は口紅をゆかりに渡そうとした。
「あげる。きれいになれるよ。もっと可愛くなれるよ」
「私は可愛くないよ、やめろよ」
お互いに意地になって、口紅のなすりつけあいになってしまった。キャップが外れ、おたがいの顔や服、手に口紅がぬめーっと塗られてしまう。
「あげるー」
「いやー」
いつのまにか、おっかけっこになっていた。ゆかりが逃げ、わたしが追いかける。それをどれほどつづけただろうか、気が付いたのは、吼え声に呼び止められたときだった。
「なに?」
ふりむいたところに、おおきな犬がいた。
「え――」
野良犬だったのか、飼い犬だったのか、いまではもう、覚えていない。私は犬と視線があった瞬間から、本能的な恐ろしさに体が動かなくなり、ただ、震えていた。犬が噛みつこうとしたのか、ただ甘えようとしていたのかも覚えていない。近寄ってきたことだけは、覚えている。いやそれも怪しい。常識論として、近づく、ということをそれとして後付けしているだけかも知れない。それほど私はショックを受けていた。なにしろ突発的だったからだ。だがそれは正しかったのだろう、なにしろ、つぎの記憶では私はすでに犬に組み伏せられ、犬の重みにひたすら泣きわめき、あらぬ助けを乞うていたからだ。
――ふつう、こういうときには助けの神は現れないと相場が決まっているはずだが、そのときは違っていた。スーパーマンならぬスーパーガールが、近くにいたからだ。どこかで調達した棒らしきものを持ったゆかりが、犬の背中を数回叩き、哀れな犬はきゃんきゃんと吠えて逃げ出した。
それだけ。
たったこれだけのなんてことはない事件だったが、当時の私にとっては地球が爆発するかのような一大事だった。引っ越しという大事でこれまでの友達ともみんな別れ、おいおい泣いていたのはつい1日前である。それも口紅という格好の相手と、ゆかりという魅力的な子に出会えたことですべてが飛んでいたのだが、別れという事件以上のなにかがすぐわずか1日後に起こるなんて、私にはまるで信じられなかったのだ。おおきな犬はいなかった、みだりに近寄ってくる犬もいなかった。10年も生きてない短い経験で、物心ついてからはまだ数年にしかならない期間が人生のすべてで、だからちょっと大きなことはそれが普通であっても、みんな大大大大事件だったんだ。
そして慰めてくれたゆかりがいらない一言をいって、さらにわけもわからず喧嘩した。それはおそらく、安心した反動だったんだと思う。気を失ったことは、そう、疲れたんだ。別れて、引っ越しして、出会って、事件が起こって――短時間でいろんなことがありすぎたんだ。
「ゆかり……あのとき私、この口紅すっかりなくしたと思っていた。でも、持ってたんだね」
「うん? どうしたんだ急にしおらしいとゆーかそんな態度して。こちらが気恥ずかしいじゃないか」
頬を掻くゆかり。妙に可愛らしく見える。いや、いまの彼女はじつに、そう、きれいだった。
「ねえゆかり」
「あん?」
「どうして私が体育教師になったかわかる?」
「なんでだ?」
「それはね、ゆかりに出会ったからよ」
ゆかりはしばらく私を見つめ、そして何気なく言った。
「……ふーん」
数分ほど互いに言葉はなかった。
私もゆかりも、当時の思い出をいろいろと回想するのに忙しかったんだ。
「ねえにゃも」
「はい?」
「わたしもねー、教師になったよねー」
「うん」
「なんで英語なんだろ」
「……はあ?」
「にゃはははははは。さ、夕方にもなってきたし、レッツゴー居酒屋!」
「――ったく、そんなこと出来るわけないじゃない。一度家に置いて、それからよ」
「えー、代行あるじゃん。それとも隠れて運転しても、ばれやしねー」
「あんまり余計なお金遣いたくないし、それに私たち教師よ!」
「公務員じゃねーっつーの。私学だから、重くないって」
「だー! そんなことだから彼氏できないのよ!」
「にゃんだとー? これだから幸せな女はいやだってんだ。ネクタイ結びの練習させてあげないぞ」
「え、こまる、それ困る。私まだよくわからないのよー」
「よしよし。だから今夜は、にゃもの奢りの日だよ?」
にぱっと満面の笑みを向けてきたひまわりに、私は苦笑して答えるしかなかった。
「わかったわよ。でもね、まずは家にこれ置いてからよ。わかった?」
「やったー!」
私はおそらくこうやって、ゆかりとまだまだ、長く不思議なつきあいを続けていくんだろう。
何気ない思い出と共に、車は成長した私と彼女を乗せ、赤くなった夕方の世界を走ってゆく――
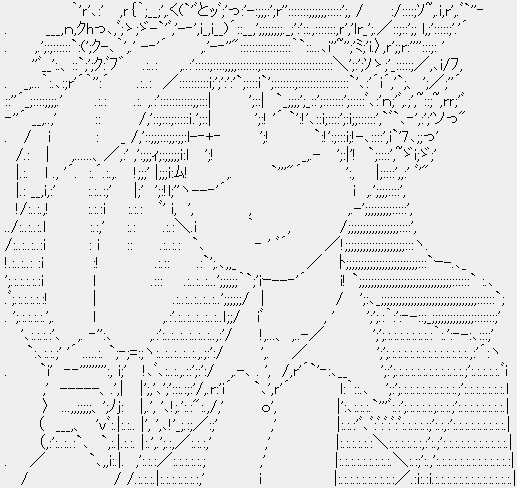
「ねえねえ榊、今度遊びに行ってもいいかな?」
私はふるふると首を横に振って、拒絶の意志を示した。
「どうして、いいだろ友達じゃん」
「その――汚れてるから」
「そうか……残念だなあ。せっかく3年生も一緒のクラスになれたのに」
神楽さんは本当に残念そうに言っていたが、それ以上突っ込もうとはしなかった。助かる。彼女は強引なところがあるが、根は優しくて意外と人のことを見てるので、引くべきときはちゃんと下がってくれるので助かる。これが智さんなら一向に構わなかっただろう。よかった。
私は高校にあがってからできた友達を、一回も家につれてきたことがない。友達の家に上がったことはあるが、逆はない。というのも、私には知られたくない秘密があるからだ――
猫が好き。
もう、溜まらないほどに。
部屋は猫で埋め尽くされている。
ぬいぐるみ、本、雑誌、アクセサリー、下着、服……
あらゆるものが猫であり、猫なのだ。私は猫とともにある。すばらしい時間、聖域。心のよりどころで、すべてで、それが私、榊の心を形作るのだ。
だから、部屋には誰も入れたくない。
親ですら。
「じゃあな」
「うん……」
神楽さんと別れた。
よし、目的のものを買いに行こう。
私はメガネをかけて変装すると、近くのビデオ屋に行った。
目的地は、アニメ売り場。
そうなのだ。私は無類の猫好きであるがゆえに、アニメであってもコレクトをおろそかにはしない。私の目的は――これですにょ!
家に帰って、部屋にまっしぐらですにょ。
DVDの封を切って、レコーダーに入れ、音はヘッドホンで聞きますにょ。
「にょにょにょにょにょ、ブロッコリーにょ」
にょにょー! デ・ジ・キャラットー!!!
♪うぇるかむつー、うぇるかむつー、うぇるかむつーまいはーと~……
ばたんっ!
「おーっす榊、途中で榊の母さんに会ってね、気が合って誘われたんで、やはり電撃で遊びに来てやった……」
「にょおおおおおおお!!!」
「榊……おまえ、その格好、猫なメイドさん……コスプレ……似合わねえ……アニメおたく……」
ばこっ
――……
「あれ? 榊、なにかなかったっけ?」
「いや、なんでもない」
「ここがおまえの……部屋か? かわいいな」
「ありがとう」
「えーと、なんか頭がくらくらするけど?」
「気のせいだ」
「そう?」
「気のせいだ」
「そうか」
「気のせいだ」
「うんうん……そうか……?」
ちりん
「なんだこの鈴?」
しまった……片づけ忘れてたか。
「気にするな」
「いや、なんかずいぶんとでかくないか?」
「気にするな」
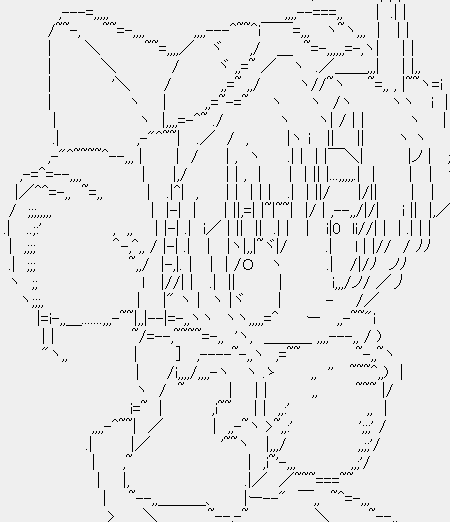
「あんなあ暦ちゃん、SSってなんやー?」
いきなり大阪が聞いてきて驚いた。
「なんだ大阪」
「インターネット見てたらやあ、小説ってジャンルのSSがあんねん」
「いや、それをいうならSSってジャンルの小説だろ」
「そうなんかー? 小説さんなんかー」
「SSは小説とは違う」
「えー、なんでー? どっちも文やでー」
「じゃあおまえは日記も小説って言うのか?」
「日記は日記やん。暦ちゃんおかしいで」
「たとえ話しとるだけじゃー!」
「怖いー」
脊髄反応で馬鹿言ってるし。
「……それでSSがどうしたって?」
「うん、私な、SS書こ思てんねん」
「文才のかけらもないくせになんでまたそんなことを。なにかアニメとか漫画とか見てたっけ大阪?」
「んーん、見てへんでお金かかるし」
「じゃあSSなんて書けるわけないだろ」
「どないしてー?」
「SSってのはな、既成の主に商業作品を土台にしたショートストーリーのことだ! 漫画を読まないおまえがどうやったらSSを書けるってんだ? ええ?」
「そんな深い意味があったんかー!」
「知らなかったんかい!」
「うん」
「じゃあなんの略だと思ってたんだ?」
「サムライセブン」
「どマニアックじゃー!」
ばちーん。
「暦ちゃん痛い、なんでハリセンなんか持ってるん?」
「気にするな」
大学を卒業し、研修期間を経て私は念願の獣医となった。
今日は初診察だ。朝から緊張している。高い鳴き声が私をはげましてくれた。
「マヤー……ありがとう。私は平気だよ」
一緒に暮らし初めて何年にもなるが、相変わらず私はこの子に救われている。きっとこの子以上の猫には私は生涯出会えそうにないだろう。
ドアが叩かれた。
「はい」
私が返事をすると、ドアがゆっくりと開かれた。
はじめてのお客さんは中年の女性だった。胸元に猫を抱えている。毛は全身灰色で、毛並みも良さそうだ。だが耳が垂れていて元気がないのが瞭然だった。
「どうしたんですか?」
「この子、昨日から急に元気がなくなって」
「わかりました。さっそく診察しましょう」
「はい――あの、ちょっとお聞きしてよろしいでしょうか」
「なんでしょう」
「そのお医者様の頭の上に寝ている猫は……」
「ああ、気になさらないでください。帽子です」
「でも……生きてますよ」
「帽子です」
「そうなんですか?」
「帽子です」
「しかもなんか……ちょっと見慣れない猫で」
「雑種です」
「先生、大丈夫ですか?」
「雑種です。とにかくその子をここに」
「はあ……」
飼い主はしぶしぶ診察台に猫を置いた。猫は小さく啼くと、私のほうに視線をあげる。
なんだろう?
奇妙な既視感が私の体を走った。かつての嫌な記憶、トラウマ、そういったものだ。だが私はもう医者だ。猫は平気になったし、もう私はかつての私ではない。私が猫に嫌われていたのは、猫が嫌がるような興奮した状態で接していたからだ。マヤーのときは緊張していた。そのおかげでうまくいったのだ。
「どうしたんだい?」
私は優しい声で、ゆっくりと手をさしのべた。すると急に猫の毛が逆立ち、口を大きく開けた。
「……あ!」
噛まれていた。見事な歯並びが、私の皮膚に食い込んでゆく。
「きゃあ、カミコちゃん!」
飼い主が驚いて猫を引き離そうとする。だが灰色のその猫は極上の小鳥を捕らえたかのようにあごに力を込め、ワニみたいにがぶりついていた。
そうか。
痛みのなか、私は理解した。
この猫は、カミネコの子供か、孫だ!
こんなときこそ、私の保険が生きてくる。
「マヤー! ゴー!」
……その日の夕刊にあるささやかながらエキサイティングな記事が載り、警察から解放された私は日が明けるのを待たずに夜逃げした。マヤーと共に。
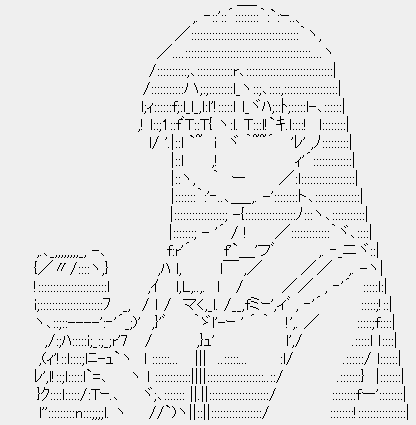
なぜなんだろう?
3年生になって、担任の木村に気に入られている。
親しくもなかったのに私を授業中に愛称で呼ぶし、鶴というか怪奇の一声で委員長にしてしまうし、榊さんとは別のクラスになってしまったし、私の3年生はこのままでは不幸の湖底で泥となってしまう。しかもその泥を木村という魚に掻き回されたのでは、もはやなんと形容していいか分からない。
すべては木村のせいだ。いったい彼は私のどこを気に入ったというのだろう。木村の基準は胸が大きく、美しいということのはず。私はサイズも普通だし、背も普通だし、容姿も目立っているわけじゃない。木村の奥さんはとても美人で、胸はとても大きく、いつか奥さんを見かけたとき男子が興奮しながら話題にしていた。
これにはなにか秘密が、裏があるにちがいない。私と木村の好みを結びつけるなにかが。それを解き明かし、木村を退け、私はあるべき自由を獲得するのだ。そう、これは私の戦いだ!
――その決心から、すでに2ヶ月も経過してしまった。一時的とはいえ木村から解放される夏休みはまだはるか彼方なわけで、私はいまだに木村の地獄から脱出することができないでいる。クラスメイトは誰もが木村を気味悪がっていて、私に蜘蛛の糸を垂らしてもくれない。みんな私ひとりだけを犠牲者として地獄に押し込め、天国でのうのうと暮らしている。
頼れるのは自分しかいない。
そうだ。他力本願はいけない。4月に誓ったじゃないか。これは私の戦いである、と。いままであまり行動に移さなかったけど、こうなったら木村の秘密がどうのこうのという以前に、その弱みを掴んで脅すといったくらいはやらないといけないだろう。
私は犯罪に手を染めることにした。お母さんお父さんごめんなさい。かおりは悪い子になります。
週末というか土曜日、木村は一家3人で車に乗って出かけたのを見計らい、木村の家に侵入することにした。金曜に木村が私に言っていたからだ。やつは気味が悪くて女子高生大好きでセクハラまがいのこともしでかす変態のくせに、やたらと家族想いで良い父親を演じている。きっとそれはそのままの演技に違いない。今日、私は木村の裏を暴き、英雄になるんだ。
木村の家はローンが20年残る一軒家で、まだ新しい。だけど犯罪があまり起こらない平凡で平和な団地にあるためか、戸締まりはいいかげんだ。新聞受けを開け、中に入っていた自転車用のオイル容器を取ると、ほら、娘さんのために用意してある、予備のカギが隠れてる。
簡単なものだ。
家の中を捜索する。普通の、幸せな家庭そのものだ。木村の奇人さを示す証左はそこにはなにもない。まるで文字通りの頼れる大黒柱に支えられた、完璧な理想の一家の香りが漂ってくる。だが騙されないぞ。私はついに木村の部屋とおぼしきものを2階で見つけ、ゆっくりと侵入した。私の父の部屋と雰囲気がよく似ているが、書斎にでもあるような大きな机が鎮座している。家でも仕事をするためだろう。古典の参考書や本などがたくさん並んでいる。私はその机に向かう。こういうところに大事なものも収納しているはずだ。
……あった。いきなり私の写真が出てきた! 学校の制服を着ていて、夏服だ。なかなか可愛く撮れてるじゃないか。カメラのほうを見て、にっこりと笑っている……おかしい。私は木村にこういう笑顔を向けたことはないし、写真に撮られた記憶もない。そもそも木村は学校にカメラを持ってきたのを見たことがない。木村は変人だが、真性の変態ではない。それならやつはとっくに職を失ってる。失業しないていどのきわどさで木村は自身の欲望を発散し、だからこそ私は耐え難い精神的な負担を受けているのだ。やつは決定的なことをしない。つまり終わりがない。それがかえってたちの悪さとなっている――そんなことはどうでもいい。この写真の正体だ……そうか。
これは私じゃない。
木村の、奥さんだ。そうだ、やっぱりそうだ。引き出しの奥をさらに探すと、ちいさなアルバムが出てきた。開いてみると、昔の木村がそこにいた。
「うわ木村先生って髪型もメガネもそのまんま!」
うちの学校ではない。詰め襟の黒い制服を着ている。となりには例の私によく似た、私の学校の制服を着た少女が立っている。背景は知らない学校の文化祭で、周囲には木村の学校の制服がわらわらと背景となっている。木村の通ってた高校で撮ったものだろう。二人は仲良く手を繋ぎ、あの変態がやはり大きく口を開いたまま、頬だけ染めて棒立ちだ。そして――ようやく得心した。少女の微笑みが、誰に似ているのか、わかった。
「奥さんなんだ……」
木村が私を気に入っている理由がわかった。奥さんの若いころに私はよく似ているのだ。顔形、髪型、背丈、そして胸のサイズまで。しかも学校までおなじ。あまりにも似ているので、私自身が奥さん自分と見間違えたほどだし。
いまの木村の好みはおそらく、現在の奥さんの体格そのまんまなのだろう。高校2年や3年の段階からあれほどのグラマーな体にどうやって成長できたのか分からないけど――私はどうだろう? きっとだめだな。私の母を見たらわかる。私は木村の奥さんのように美しくはなれないし、胸も大きくなれない。私はあくまで凡庸なままで終わるだろう。だけどいまの私はとにかく奥さんの若いころに似てるわけで、だから木村は私を気に入ってるんだ。
それだけ分かれば長居は無用だった。私は自分でも感心するくらい慎重に侵入者がいたという痕跡を消すと、家に帰った。秘密さえ分かれば、あとはなんとでもなる。
月曜、私は木村先生を校舎の裏に呼び出した。
「どうしたんだいかおりん?」
婉曲に言っても仕方ない。私はいきなり本題を切り出した。
「木村先生の奥さんって、若いころは私に似ていたんですってね」
「…………」
木村が黙った。反応しない。
「それで木村先生が私だけを特別扱いするのは、教師としてどうかと思います」
「…………」
「あのー。それで、できれば、今後は」
「一等賞ーー!!」
「ええええ?????」
「あなたは私の一等賞になってね。ぴったしかんかーん!」
「ええ?」
「髪の色が違いますね」
「……はい?」
「黒い髪のかおりんは、私の一等賞になってね、と言いました。だから私は一等賞になりました」
木村は完全にどこかの世界の住人になっている。私でない、誰かに語りかけるように。
「だけど! ――黒い髪の彼女は、私が大学3年生のときに、別の世界に旅立ったのです」
「え?」
木村の濃いメガネの間から、きらめく筋が垂れ落ちていた。
「召された彼女には、茶色の髪の妹さんがいました。彼女は私にいいました。二等でもいいから、私を側に置いて下さい」
「あの……木村先生」
「私はいいました。だめだ、君はボクの一等賞になりなさい、と」
重い話になってきた。これは、かなり秘密なんてどころじゃない話だ。
「だから互いに一等賞になったのです! おしまい!」
木村はそれ以上語ろうとしなかった。私をじいっと見つめ、そして奇声を発すると、そのまま怪しい足取りで私の元から去った。
……断片だけだが、なんとなく事情はわかる。黒い髪の私によく似た彼女は、すでにこの世の人ではない、ということが。妹なら、笑顔が似てるわけだ。髪の色も、体格も違っている。だけど笑顔はおなじだった――私の戦いはおそらく、私の敗北でその幕を閉じそうだった。私にはもう、これ以上「戦う」ことは、きっとできない。
「かおりーん、なんか最近、あまりキムリンのこといわなくなったな。どうしたんだ? なにかあるんなら相談してみろよ。クラスが違ったといっても、いちおうは友達なわけだしさ」
「え――ああ。滝野さん心配してくれてありがとう。でももうそれはいいの」
「どうしたんだー、かおりん。抵抗を止めたのかー?」
「うん、なんか疲れちゃって」
「大丈夫か、大事にしろよ」
「ありがとう」
で。
「滝野さん! あなたね! 私が木村先生と出来たって噂流したの!」
「えー、違うのー?」
「キー! 私は榊さんひと――とにかく、違うったら違う!」
 イラスト:makiさん
イラスト:makiさん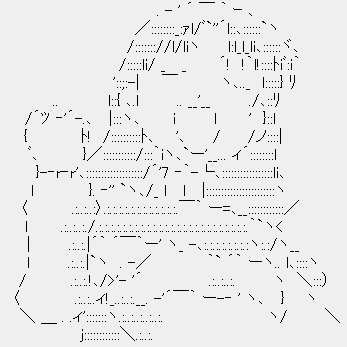
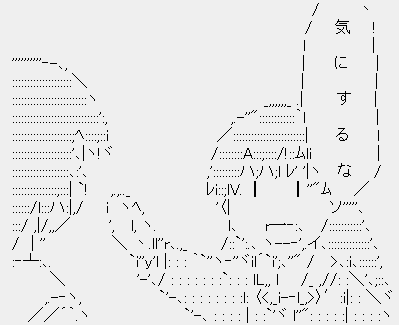
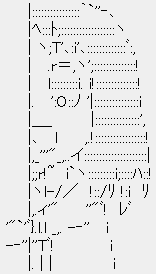
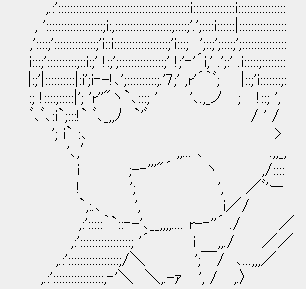
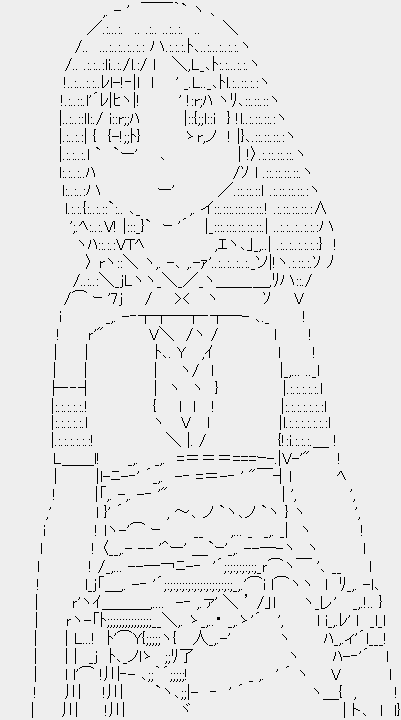
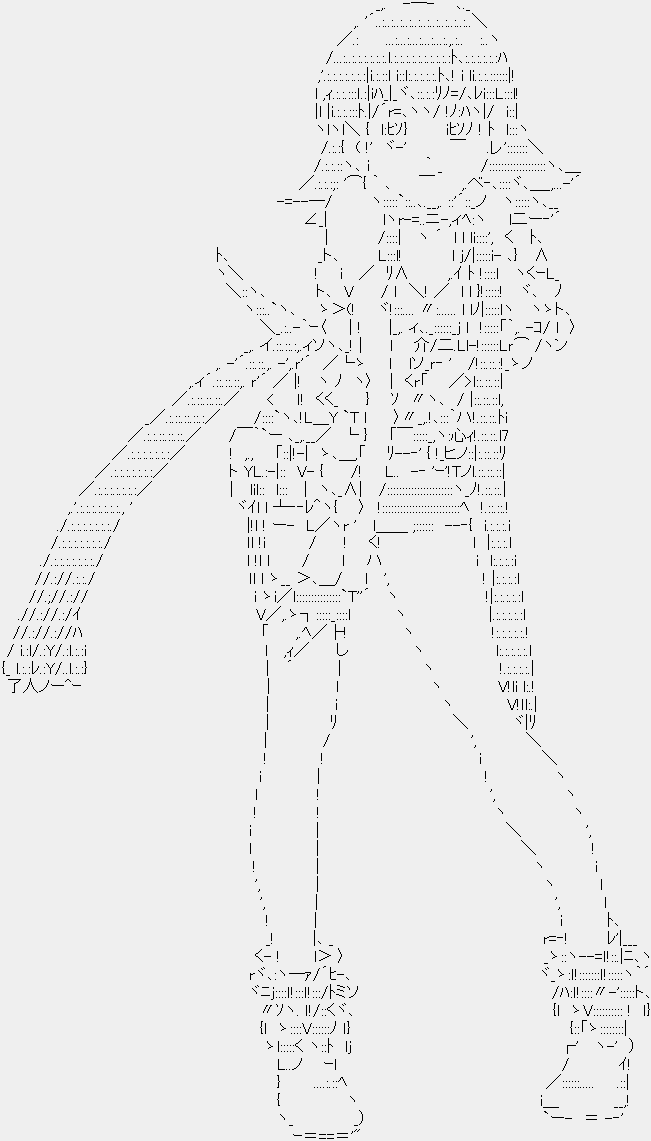
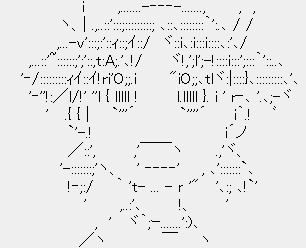
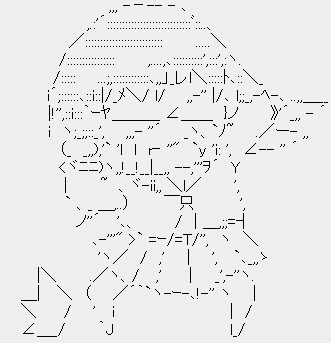

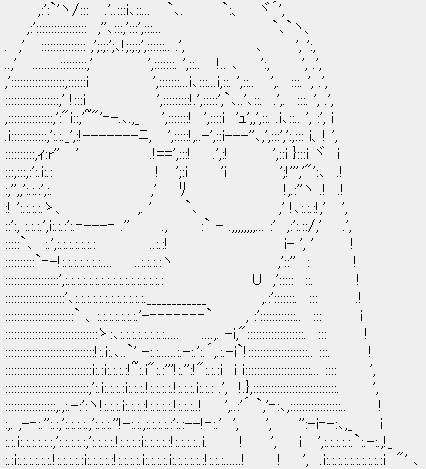
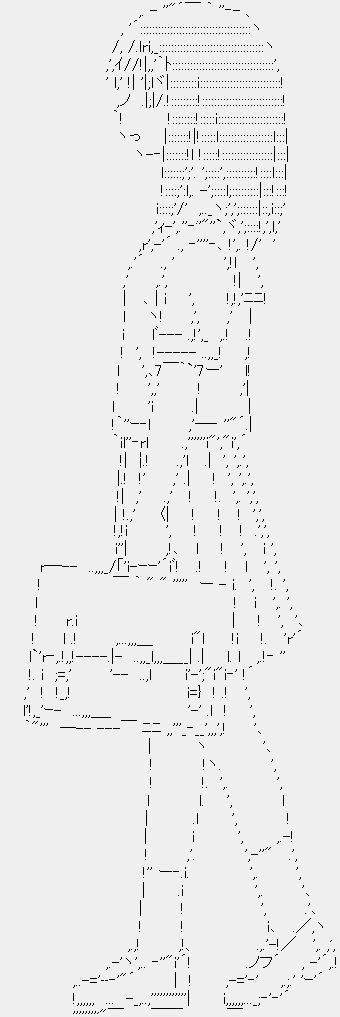
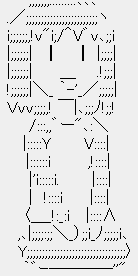
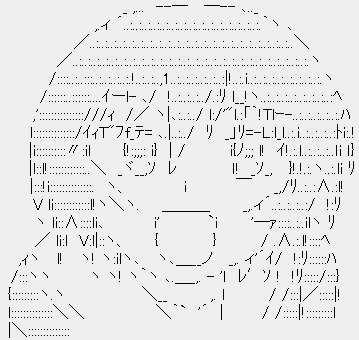

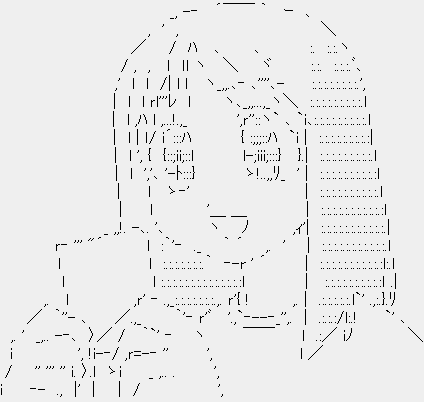
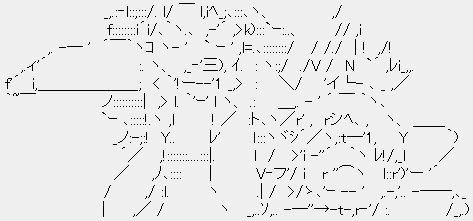
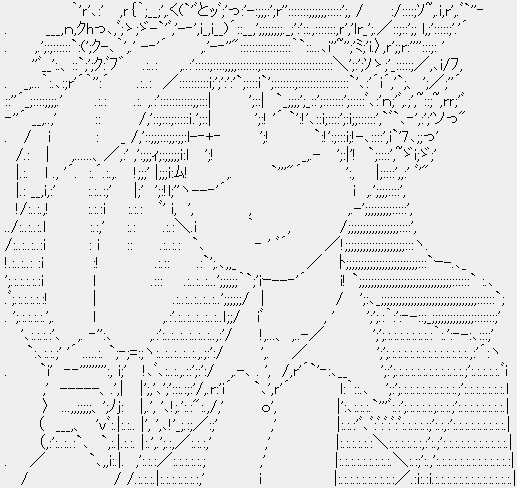
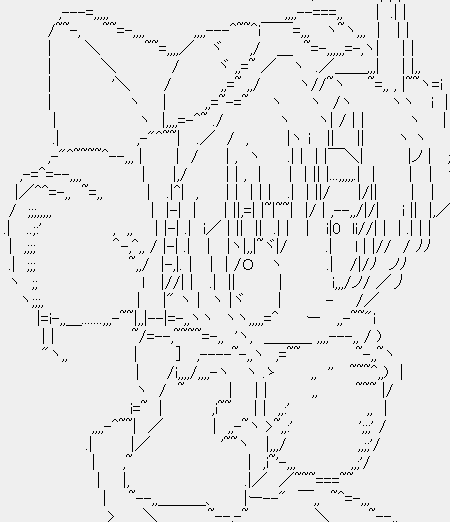
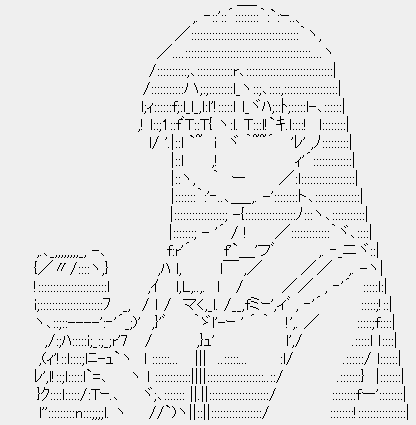







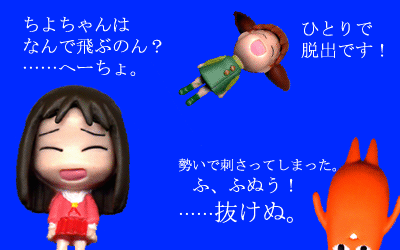 * *
* *